1 軽井沢
「お母ちゃまにあげるんだ」昴は背の高さほどもある草原の中を歩いている。
小さな手には手折ったばかりの桃色のヒメジヨオンの花。
涼風が木々の葉を揺らし杉の木立の中を通り過ぎて行く。
三歳になったばかりの昴は頬に当たる葉に顔をしかめながら桃色の花を夢中で追う。
短い軽井沢の夏を急ぐようにセミ達が騒々しく鳴き野鳥が負けまいとピュウピュウと喉を鳴らす。
その時降るように鳴いていたセミの声が突然途切れ、一瞬の静寂が起こった。
立ち止まる昴の目の前に草の中から突然大きな猫が姿を現し、昴の腕を蹴って押し倒して林の中に消えて行った。
一瞬の出来事だった。
猫はまるで空気の裂け目から飛び出したように唐突に現れ、瞬きをする間にかき消すように走り去った。
草むらにひっくり返った昴、手から離れ無残に飛び散った桃色の花。
お母ちゃまにあげる桃色の花。
|
シャンパングラスが午後の日に煌めいて、恵子は満足そうに目を細めた。
買ったばかりの別荘で友人を招いてのガーデンパーティ。
刈り込まれた芝生の上に丸テーブルが六つほど置かれてケータリングの料理が色とりどりに並ぶ。
正面に置かれたグリルから肉の焼ける香ばしい匂いがしている。
白いユニホームの男たちがグラスを乗せたトレイを持って客たちの間を回っている。
今日の客は夫の会社の社員と恵子の大学時代の友人と気楽なメンバーばかりなので恵子もリラックスしていられる。
夫のメディア事業の会社がここ数年で急成長をして夫婦の生活は、誰からも羨まれるセレブの仲間入りをした。
高級な都心のマンションに住みメルセデスに乗って、念願だった軽井沢の別荘も手に入れた。
別荘は中古ではあるものの、建物は贅沢な造りで広いリビングには暖炉がありゲストルームも4部屋ある。
何よりも気に入ったのはカーデンパーティが出来る広々とした庭だった。
|
 |
恵子は、近頃気になってきた日焼けのシミを恐れて庭に向かって開け放された部屋のソファに陣取って大学時代友人の早苗と話をしていた。
「恵子は幸せね、優しいご主人に可愛い子どもでこんな素敵な生活は夢のようだわ」恵子はさっきから繰り返し続けられる早苗の羨望の言葉を受けて優越感に浸りながら微笑みを返した。
「早苗、貴方の所はまだお子さんは作らないの?」
「欲しいと思って居るんだけど、病院で検査したらできにくいらしいの体外受精なんて、とても出せる金額じゃないしね」早苗は溜息をついた。
「早苗のご主人って建築業の人だったわよね」
「建築業って言っても普通の大工なのよ、彼に熱を上げて結婚しちゃったけど私は人を見る眼がなかったわ貧乏暮しもいいところよ」
「私だって、哲夫の会社がこんなに大きくなるとは思わなかったわ」
「嬉しい誤算ならいいじゃない、昴ちゃんが生まれてから良い事続きね」
早苗の言うとおり昴を授かってから今日まで次々と好運が舞い込んでいた。
昴は幸運を運ぶお守りのようだと恵子には思えてならなかった。
そう言えば昴は何処へ行ったのだろう。
パーティのお客の間を回って遊んでいたはずの昴の姿が見えない。
恵子は部屋を出て、女達の輪の中で笑っている夫の横顔に言った。
「哲夫さん昴を見なかった?」
「さっきまで、そこでワインのコルクを集めて遊んでいたけど」夫の哲夫は赤い顔を緩ませて言った。
夫と話していた女は振り返って言った。
「昴ちゃんなら向こうの杉の木の方に歩いて行きましたよ」
背中の大きく開いたドレスから出た肢体がみずみずしく、恵子を嫉妬させる。
哲夫は若い女と話す時は、こんなに上機嫌なんだわ。
恵子は苦々しく思った。
隣との境界線は杉の木が一列に植えられて、隣の土地は三百坪ほどの空き地になっていて雑草が茂っている。
杉の木の隙間から日に照らされた緑が鮮やかに見える。
恵子が杉の木に向かって歩みを始めた時、昴の火がついたような泣き声が空き地の方から聞こえた。
明らかに普通とは違う泣き声に、哲夫も顔色を変えて走り寄ると空き地の中程で、昴は草の上に座り込んでワァワァと泣いていた。
「昴どうしんだ?」哲夫が昴を抱き上げると昴は小刻みに震えて「ニャンニャが、ニャンニャが」と繰り返して大粒の涙を流した。
「どうしたの、怪我は無いの?」追いついた恵子は昴を胸に抱き寄せた。
「何か動物が居たみたいなんだ、猫かなぁでも熊だったら大変だ」
「お隣の奥さんがゴミをあさる熊が出るって言ってましたわ」恵子は不安そうに言った。
急ぎ足で昴を部屋に入れてベッドに寝かせたが、激しく泣くばかりで何が起こったのかは解らなかった。
昴は永い時間泣き続けて、ぐったりとして眠ったが眠りについても時々顔をゆがめて辛そうにする。
昴が左の腕を何回も摩るので見ると、二の腕の内側に皮膚が赤くなった場所があった。
花のような形の赤く変色した皮膚は虫に刺されたか何かにかぶれたのか、痒そうな感じだったので、恵子は買い置きの軟膏を付けておいた。
その夜、昴は熱を出してしまい恵子は添い寝をして一夜を過ごした。
|
2 家出
昴は、東京から少し離れた海沿いの町で育った。
海沿いの駅から踏み切りを渡り国道進む。
交通量の多い国道から脇に逸れて丘に続く急なコンクリートの階段を高層ビルの高さほど昇った小高い場所に昴の家は在る。
濃い緑の木々の中に埋もれそうな赤い小さな屋根が昴の家だ。
昴の部屋の窓からは、海が少しだけ見える。
あたりが夕闇に包まれ始めると港のオレンジ色のライトが夜空を赤く染める。
終わらない夕日のように港の灯は朝の光にその色を失うまで燃え続ける。
昴には、八つ違いの弟とその下に妹が居る。
弟は昴が小学校に入学する年に生まれた。
赤ん坊は、父の名前の一字を取って辰哉と名付けられた。
続いて、次の年には妹の奈津美が生まれ一家は五人暮らしとなった。
母の早苗は辰哉が生まれると、昴を呼んで「お兄ちゃんになったんだから、これからは弟の為に我慢するのよ」と言った。
昴は初めて弟が出来たのが嬉しくて、この小さな赤ん坊を大事にしょうと思
った。
母は兄として常に弟世話をするように言って、八歳だった昴に弟のオシメの交換を教え、それから次々に仕事が増えて妹が生まれた時には二人の子供の育児の為に同じ年頃の子供と遊ぶ時間など無いほどになっていた。
母親の「昴はお兄ちゃんだからね」の言葉で子供には重荷の事まで何だか誇らしく思えて昴は幸せを感じていた。
小さい弟も妹も母に似て、笑うと左の頬にエクボが出来る。
二重の丸い目に柔らかい髪が愛らしい良く似た子供達だ。
昴が中学までの間は平穏な日々が続いた。
弟の辰哉は、とても明るい子供で家族皆を笑わせていたし妹の奈津美は甘えん坊でお転婆な女の子だった。
父は、工務店に雇われている大工で無口で実直な男だった。
七時には、妻の手作りの弁当が入った大きなランチボックスを持って現場に行き夕方には汗の匂いのシャツと共に帰って来る。
筋肉質の大きな体、日に焼けた皮膚に深く刻まれた皺。
昴にとって、父はいつも頼れる存在だった。
東京より、南に位置するこの町は海に近い事もあって冬でも暖かい。
それでも、一月を過ぎると外に汲み置きしていた水に薄氷の貼るような寒さの日も数日はある。
その日も北風が強い寒い日だった。
午前の授業が終わりに近づいた頃、担任の教師が教室に入って来て「成川、お父さんが事故に遭われたすぐに帰りなさい」と告げた。
昴が病院に着いた時に父は、緊急手術が終わり包帯だらけの体をベッドに横たえていた。
足場からの転落事故だった。
この事故が平穏だった一家の生活を大きく変えてしまった。
長期の入院の後に父の怪我は一応に回復はしたが強打した腰椎は、後遺症となり度々強い痛みが現れた。
工務店の仕事に行けない日が月の半分にもなって成川の家の預金は瞬く間に底をついていった。
母は、収入の助けに近くの弁当屋にパートに行くようになった。
父は痛みや不満を紛らわす為に酒の量が増えて酔っては家族に当たりちらした。
笑い声が絶えなかった家は、父の怒鳴り声がするようになった。
酷暑の八月が終わり九月に入っても、暑さは衰えようとしなかった。
昴は学校からの帰り道、家に続く階段を汗にまみれになって登り終え玄関の
ドアを開けようとすると父の罵り声が聞こえて来た。
「お前、いい加減にしろ俺だって我慢の限界が在るぞ」
「今更何を言ってるの、私だってもう限界なのよ」
「昴を利用するだけ利用して、その上また金を剥ぎ取るのか」
玄関のドアを開けようとした昴は、自分の名前を聞いて立ち止まった。
「お前が昴を引き取ったのは親からの金が目当てだっんだろう」
「何よ!私ばかり悪者あつかいして、そりゃぁお金は欲しかったわよ、でも子供が出来ないからってアンタだって喜んで貰ったんじゃないの、四年も後で二人も生まれるなんて解らなかったわよ」
「ああそうさその通りだ俺だって予想は出来なかったさ、でもお前が昴をコキ使うのを俺がどんな気持ちでいたか解るか?」
「あら、あの子は喜んで手伝ったくれたのよ扱い易い子だからね」
「まったくお前は大した女だよ、金を貰った子を家政婦代わりに使って今更また親から金を引き出そうなんて」
「アンタにそんな事を言われる筋合いじゃないわ、アンタがドジって怪我さえしなければこんな事には成らなかったのよ」
昴は両親の言葉を聞いて体の振るえを抑える事が出来なかった。
暑いはずの気温なのに、全身の血が引いて寒さに身を震わせていた。
歯はガチガチと音を立ててぶつかり合い自分では抑えようもなかった。
頭の中は真っ白になって気が付けば、足は自然に昇って来た国道に続く階段を引き返して踏み切りを渡り駅の先に在る公園向かっていた。
父と母の会話が何回も壊れたレコダーみたいにリピートされて響いた。
金目あてに貰った子、家政婦代わりに使った子。
今までそんな事一度も考えていなかった、自分が実の子で無い事すら知らずにこの十七年間を過ごして来た。
昴は、公園の隅のベンチに座ってすぐ前の海を見て永い時間を過ごした。
公園がうす暗くなっても昴はその場所から動かずに海だけを見ていた。
今になって思えば、父の言った言葉の意味は思い当たる事だらけだった。
普通の子供ならやるはずの無い家事に毎日追われている事が昴の日常だった。
それでも、母の感謝の言葉や励ましで昴は不満を持った事はなかった。
母は微笑んで左の頬にエクボを作り、丸い優しい目で何を思って昴を見ていたのだろう。
悪意に満ちた母の声を思い出すと震えがするほど恐ろしくなった。
自分は意図的にうまく使われていたのだと、改めて解った。
母は、弟や妹をよく抱きしめていた。
|
自分は一度も母から抱きしめられた記憶はなかった。
思い出せば数多くの悲しい差別も自分が長男だからと我慢して来た。
昴は今ようやくその本当の訳を知った。
自分はなんて愚かな扱いやすい子だったのだと、唇を噛み締めた。
公園の街路灯が青白い光を灯している。
目前の海は、闇に包まれ黒い海面に港の僅かな灯だけが揺らいでいる。
昴は波間に消え入りそうな灯を見つめながら実の父や母の事を考えた。
自分の本当の父や母はどんな人だろう。
逢いたい気持ちと今更逢いたくない気持ちが押し合いをしていた。
|
 |
ほんの数時間前まで疑った事の無い成川の両親から、気持ちがどんどん退いて他人のように感じて行くのを止める事は出来なかった。
昴は大きく息を吸いこんで、潮の香りを胸いっぱいに入れて、それを大きく吐き出した。
「家を出よう」昴は言葉に出して言ってみた。
言葉は呪文のように昴の気持ちを解放し、瞳から大粒の涙が溢れ出て流れた。肩を震わせ昴は泣き続けた。
昨日まで何の疑いも無く過ごして来た家族が今は遠い他人のようだった。
一度思いを決めた昴は迷う事なくその足で駅に向かった。
東京に向かう最終の電車がホームを滑り出す。
トンネルを抜けて昴の暮らした家のあたりを通り過ぎる。
小高い丘が黒く濃い影を落とし影の中に星屑のように家々の灯が幾つも見える。
今頃、弟の辰哉も妹の奈津美も眠りについたのだろうか。
父と母は帰らない自分の事を気にかけているだろうか。
昴は不安を胸に、電車の揺れに身をまかせ目を閉じた。
|
3出会い
昴は、植え込みの縁石の上にしゃがみ込んでうつむき加減で通り過ぎる人の足元を見て永い時間を過ごした。
足早に通り過ぎる革靴、真っ赤な爪の素足に履かれたミュール、おなじみのブランドのスニーカーが雑踏の中を何処かへ向かって歩いて行く、そんな街の様子を無表情で目に写していた。
少し離れた植え込みの茂みに痩せて薄汚れた赤茶色の猫が顔を洗っている。
目の前のビルの壁には巨大な電光掲示板が相変わらずチカチカ変わって派手な色彩の広告を写し出していた。
残暑の残る新宿の街は言葉では言い表せないほど暑い。
道路から立ち上る熱気は陽炎のようにゆれて体中の水分をようしゃ無く吸い上げる。
排ガスの匂いにあふれた歩道で昴は、身動きもせずに座っていた。
最終の電車に乗ってから一週間、昴は新宿の雑踏の中に居た。
所持金は底をつき二日の間は何も食べていない。
頭の中が、がらんどうで立ち上がる気力さえなかった。
「ああ、またあの変な人が通る」と昴はぼおっとした頭の中で思った。
個性的なファッションをした人が多いこの街の中でも彼女は特別に見えた。
その人は異常に目立つタンポポ色の長い髪を巻き髪にし、ビラビラとフリルの付いた黒と紫の冬物のような長そでのワンピースを着ている。
まるでアニメに出てくる魔女のようだと昴は思った。
その女が、こちらをチラチラ見ながらまた通り過ぎて行く。
|
自分は浮浪者のように見下されているのだろうと悲しく思った。
このままでは直ぐにでも本当にホームレスの仲間入りをしてしまう。
昴は何の準備もせずに唐突に家を出た自分に激しく後悔をしていた。
もっと計画的に家を出ていれば。
後悔ばかりが頭の中を駆け巡る。
今だったら両親は許してくれるだろうか。
家に帰り両親に謝って、何も知らない振りをして高校を卒業しょう。
親の喜ぶ扱い易い子を演じて過ごそう。
そしてしっかりと準備をして、家を出て自活して一人で生きて行こう。
昴がやっと決心をして立ち上がろうとした時、目の前を黒い影が横切って植え込み端に置いてあったバックが消えた。
昴はとっさに「ドロボー!!」と叫んで立ち上がったが、足元がふらついて走れない。
バックを盗んだ男は、短距離ランナーのように猛スピードで走り出す。
昴はヨタヨタした足取りで男を追うが、前を走る男の方は引き締まった両足で力強く地面を蹴って行く。
長いチャ髪が左に右にと宙を切り揺れている |
 |
男との距離はみるみる遠く成って行く。
昴は、最後の力を振り絞って走る。
心臓は、最大限の鼓動を繰り返し目の前が暗くなる。
もう駄目だと思ったその瞬間、二十メートルほど先を走っていた男がいきなり視界から消えた。
チャ髪の男は地面に倒れ、側にはにさっき見たタンポポ色の髪の毛の女が地面に横倒しになっている。
チャ髪の男は、瞬時にバネのように飛び起きて人並みの中に走り込んで消えて行った。
昴は、ようやく二人が倒れていた場所まで追いつくとタンポポ色の髪の毛の女はまだその場所に倒れ込んでいて昴のバックは男のすぐ横に無残に埃まみれになって転がっていた。
昴は、埃まみれのバックを自分の手の中に収めほっとした。
安堵の瞬間、全力疾走で使い果たした疲れがどっと溢れ出した。
「あ、あ、痛い、痛い!」
声にはっとして見るとタンポポ色の髪の毛の女は海老のように背中を丸めて植え込みの横に倒れている。
「大丈夫ですか?」昴は戸惑って顔を向けた。
「大丈夫かって、大丈夫な訳ないでしょ骨が折れてるかも知れないわよぉ」女は、昴を睨みつけた。
「ごめんなさい、僕のカバンが泥棒にあって」
女はやっと上半身を起して、黒い服に着いた汚れを叩いた。
「ああ痛い、痛い、ともかく謝ってもらっても仕方がないけど、このままじゃ歩けないから肩を貸してよ」タンポポ色の髪の毛の女は足を撫でなから言った。
昴は体を支えて立ち上げると、タンポポ色の髪の毛の女は思った以上に長身でその上、体格も良かった。
もしかして、この人は男なのかも知れない。
「何よ、何ボットしてるのよぉ」女は低い声で怒鳴った。
「すみません、ごめんなさい」昴は心を見透かされたようで赤面した。
女の指示でタクシーを止めて、昴が先に乗り込み片足しか地面に足を着けない女をひっぱり入れる。
体格の良い女に潰されそうになって、痩せた昴は往生した。
女は指定した整骨院に着くまで一言も話さないでひたすら苦痛に耐えているようだった。
タクシーの運転手の助けを借りて女を整骨院の中まで入れた。
長椅子に倒れ込むように座った女は受付の事務員に手まねきで合図した。
「紅花先生、どうなさったんですか?」整骨院の受付の事務員が驚いた顔でカウンターから出て来た。
「どうも、こうも無いわよぉ骨折してるかも知れないのよぉ至急診てちょうだい」
紅花と言われた女は待っていた数人の患者を後回しにしてさっさと診察室に入り、二十分後にはギブスを足に巻いて車椅子で戻って来た。
「どうもすみませんでした、やっぱり折れてましたか?」
「貴方の責任よ、どおしてくれるの治療費はもちろん払ってよ」
「ごめんなさい、僕お金持って無いんです」昴は泣きそうな顔で言った。
紅花は、しばらく昴を見つめて「それじゃあね仕方が無いから私が治るまで面倒を見なさいよ、家出少年」と言って口元を曲げて少し笑った。
こんな偶然から昴は紅花と言う占い師と暮らすようになった。
紅花の住まいは繁華街の路地を入った古い雑居ビルの三階にある。
恐ろしく年代物のエレベーターを降りると目の前に貸金業者の看板が目に入る。
半透明のガラス扉の向こうにぼんやりと人影が見えるが、危ない所のような気かして昴は目をそらした。
フロアの反対側にはダンボール箱がうず高く積まれまるで倉庫のようだ。
突き当りかと思われたダンボールの横をすり抜けて進むとグレイの鉄の扉に「占いの館Blue heaven」と書いたプレートが掛っている。
ここが住まいだと紅花は言う。
飾り気のない鉄の扉を開けて電気のスイッチを入れると壁に付けられたローソクの形をした照明が灯った。
玄関の奥は狭い廊下が続いていて、薄暗い所にまだらに照明の光が当たっている。
廊下を通り過ぎる時、白いジャッが蛍光色に変わって見えたので昴はブラックライトだなと思った。
紅花が部屋の電灯のスッチを入れて華やかな光が目の前の部屋を照らす。
天井から幾重にもドレープを寄せた淡い色のシフォンが柔らかなアーチを作って入り口を囲っている。
濃紺と紫の混じった織物のような壁紙には金色の唐草の枠に納まった多くの絵画や鏡が掛っている。
壁際にある螺鈿のチェストの上にはブロンズのドラゴンが二匹球を咥えて向き合っていてその横の花瓶には大量の百合の花が生けてある。
ローソクの形のシャンデリアは天井から下がり真下に六角形のテーブルが置かれてそれを囲んで、一人掛けのゴブラン織のソファが二つと奇妙な動物の木彫付いた革張りの椅子が置いてある。
金属のワゴンにはクリスタルの燭台が十個ほど置いてあり色とりどりの蝋燭の燃え残りが乗っている。
昴はむせかえるようなユリの香の中、物珍しさできょろきょろと部屋を見渡した。
窓の無いこの部屋は天井が低く、圧迫された気分になってしまう。
「ここは私の仕事場でお客様を迎えて占いをする大切な場所よ、何ひとつこの場所に在る物は動かさないで」紅花は有無を言わせない様子で言った。
昴は黙ってうなずいて紅花を見た。
この人にはどこか人を圧倒する雰囲気がある。
紅花は病院で借りた車椅子を自分で押して姿見の前に出て鏡の端を手で押した。
姿見だと思った大きな鏡は外側に開いて、別の部屋が見えた。
中に入るとやっと生活感の在る風景が見えて昴はほっとした。
部屋の奥の窓からは日の光がさしている。
手前に小ぶりの流し台が付いた台所とダイニグテーブルが置いてある。
壁際には、ダブルベッドがありワンルームマンションのようだと昴は思った。
天井の低さと壁と天井に貼ってあるエンジ色の壁紙を別にすれば、普通の部屋に見えたのは占いの部屋が余りにも別世界だった為だろう。
紫色のサテンのベットカバーで黒い物が動いた。
丸くなって眠っていた大きな黒猫はゆっくりと顔を上げると、びっくりした様子で飛び起きて四本の脚を突っ張って背中の毛を逆立て緑の目を大きく見開いて昴を見た。
「わぁ!!」昴は猫に驚いて悲鳴を上げた。
「どうしたのよ、ブナが驚くじゃない」紅花は言った。
「僕、猫ダメなんです」昴は後ずさりして言った。
「あら、困ったわねブナはおとなしい猫だから大丈夫よ、馴れてちょうだい」紅花は取り合わない様子で言った。
「そこにお掛けなさい」と言われ昴はダイニングの椅子に怖々と腰を落とした。
猫は音もなくベッドから降りて、昴の横を通り抜けて占いの部屋に入って行った。
緊張して固まっている昴を前に表情を柔らかくした紅花が言った。
「成り行きでこんな事になったけどしばらくの間仲良くしましょう、私は紅花って言いますこのあたりではちょっと名前の知れた占い師なのよ、私が動けるように成るまでは家事や身の回り事をやってちょうだいね」タンポポのような黄色の髪の紅花が言った。
この人はいったい何歳なんだろう、三十歳ぐらいかもっと年上なのか女か男なのかも解らない不思議な人だ。
「僕は成川昴です怪我をさせてしまって本当にごめんない僕、家事は掃除とか料理とか少しは出来ます」昴はやっとそれだけを言った。
「まぁいいわ、細かい事はおいおい話すけど貴方は第一にのその匂いを何とかしなくちゃね、あなた相当の間お風呂に入って無いでしょ、まずシャワーを浴びてきなさい」
紅花に言われて昴は汗で変色したシャツを見て情けなくなった。
家を出て一週間、公園で水浴びをしたものの一度も風呂には入っていなかった。
|
4 宝石占い
昴がシャワーを浴びて浴室から出ると着ていた洋服は無くなっていた。
ドアの外で紅花が誰かと話している。
「ちょっとぉ、大丈夫なのぉ健司の洋服は持って来たけど得体の知れない子でしょ」
「心配ないわよ、私は当分こんな足で動けないから外の事をマリアが教えてもらえるかしら」紅花が言った。
「それは構わないけど足が治るのは当分掛るんでしょ、災難ねぇ」
昴はバスタオルを腰に巻いてみたが外に出る勇気もなくて困ってしばらく待ったが、客の帰る様子もないので仕方なくドアから顔だけを出した。
「あのぉ、すみません」昴は顔を赤らめた。
「あ〜ら、アンタが昴ちゃんね」濃いピンク色の花模様のワンピースを着た女はダイニングの椅子から身をよじって言った。
女は長い髪をアップにまとめ上げ後れ毛をカールし、しっかりと化粧しはいるものの女性にしてはどうも変に見えた。
顔はゴツイし、いかり肩で手足だって随分大きい。
昴は始めて見たオカマを目の前にして固まっていた。
「何をぼぉっとしてるのよ」紅花が可笑しそうに言った。
「あ〜ら、この子ったら私の美しさに感動しちゃってるのね」オカマは作ったような高い声で言って太い指を口元に当てて笑った。
昴はますます真っ赤になって陸に上がった魚みたいに口をパクパクさせてうつむいた。
「マリアったら、昴が驚いているわよ」
「あらそうだったわね、私はマリアよお察しの通りニューハーフなのぉゴールデン街の金魚ってパブに出てるのよろしくね」オカマは肩をちょっと引いて胸を突き出して赤い唇で笑った。
「始めまして、成川昴と言います」昴はとやっとそれだけ言ってドアの中に顔を引っ込めた。
ドアの外ではマリアの甲高い笑い声が響いている。
「可愛いわねぇ〜赤くなっちゃって、あの子だったら真面目そうだし大丈夫だわ」マリアの笑いはなかなか治まらなかった。
その夜は、マリアの持って来た材料で鉄板焼きの夕食が昴の歓迎会になった。
賑やかに食事が始まりオカマのマリアが大騒ぎで鍋奉行ならぬ鉄板奉行になって焼ける具合を指揮っている。
食べろ食べろと昴の皿は肉でてんこ盛りになって、昴は嬉しい悲鳴をあげた。
紅花はワインばかり飲んでマリアに怒られていた。
「紅ちゃん、もっとお肉もお野菜も食べなさい、あっまたピーマンを避けている」マリアは子供の世話する母親みたいに二人の世話が楽しそうだった。
昴はお腹も心も満足になった。
次の朝、昴は型ガラスから差し込む光で目を覚ました。
眼の先にはダンボールが天井までうず高く積まれて残った空間には、石膏ボードの天井が見た。
こんなによく眠ったのは家を出てから始めてだった。
昴は昨日の出来事を思い出し布団から身を起した。
昨夜はマリアが帰ってから占いの部屋から続いた納戸を使うよう言われて布団を運び入れて眠った。
今朝明るくなって納戸の中を見回せば、古い家具や扇風機などごちゃごちゃと置かれた手前に三帖ほどの空間があって、そこに布団をひいて昴は眠っていた。
淀んだ空気を出そうとダンボールの奥にある窓に手を掛けると外にぼんやり映っていた白い影が動いた。
建て付けの悪いサッシをガラガラと音を立てて開けると猫が一目散にアルミのベランダから飛び降りて隣の軒に乗って疑り深い目でこちらを見ている。
また猫か、と昴は思った。
こんな危うい三階の手すりに何を物好きに上がるのか猫の気まぐれに呆れたが、昴は猫が嫌いだった。
嫌いと言うよりむしろ怖かった。
幼い頃、たぶんとても幼い頃なのだろう。
記憶の断片に大きな猫に飛び掛られた思い出がある。
その時の恐ろしかった思いをずっと引き摺って今でも猫が恐ろしい。
それに怖いと思って居る為か、町を歩いていると妙に猫と目が合う。
気配を感じるとそこに猫が居て昴を見ている事は度々で、偶然にしては数が多いと思っていた。
窓を細めに開けたまま、納戸を出ると鏡のドアの外で黒猫のブナが待ち構えるように座っていた。 |
昴は不意打ちを食って驚いたが、ブナの方は平然と開いた
ドアの隙間から納戸の中へ入って行った。
昴はブナを追い払う気力も無くなって諦める事にした。
「馴れてちょうだい」と紅花から言われた事を思い出して馴れるより仕方が無いとため息をついた。
何しろこの家では自分の方が居候の身なのだから。
紅花の部屋のドアをノックすると「お入り」ときげんの良い声が帰ってきた。
「おはようございます、あの今納戸を開けたら猫が中に入ってしまったんですけど」昴は言った。
|
 |
「ああ、納戸はねブナのお気に入りの場所なのよ彼の好きにさせてあげてちょうだい」
昴はしぶしぶ、うなずいた。
「それより朝の仕事をしてちょうだい、ブナの食事は缶を一つ開けてあのお皿に入れてね、お皿は食べ終わったらすぐに洗う事」
「私は、朝はジュースだけだから貴方は適当に食べて食事が終わったら十時までに掃除を済ませてね、今日は占いの予約が三組あるのお客様がいらしたら占いの部屋にご案内をしてちょうだい、占いが始まる前に納戸に入って出ない事、音も立てずに静かにね」紅花は紫色のジュースを飲みながら言った。
昴は夕食に肉をイヤと言うほど食べたのに、今朝はもう腹ペコだった。
家を出てから忘れようとしていた食欲が戻って、昨夜の残り物を冷蔵庫から出してガツガツと食べた。
体に満たされた血液回ると気力も戻った。
昴は部屋の隅々まで掃除機をかけ、雑巾で拭きあげた。
掃除は成川の家で小さい頃からやっていたので手際が良かった。
十時を過ぎるとチャイムが鳴って客がやって来た。
紅花は占い部屋の六角形のテーブルの前に在る奇妙な動物の木彫付いた椅子に腰かけて客を向かい入れた。
豪華なドレープのカーテンを背にしてに座った黒いドレスの紅花の姿は妖艶に見える。
占い部屋と紅花の怪しげな雰囲気がお互いを引き立てあって神秘的な雰囲気を醸し出している。
客は太った中年の女性で顔色が悪くとても疲れているように見える。
女性は馴れた様子で廊下を進み紅花の前の椅子に座った。
昴は客に見えないように気を配りながら納戸に入りそっとドアを閉めた。
「お辛かったでしょうね」紅花の声が聞こえる。
「先生、先生だけが私の気持ちを解ってくれるのですね」客の女は言った。
「今は試練の時です、これをどう乗り切るかで貴方の未来が変わりますよ」
「先生、先生!どうか私を助けて下さい」女の人は涙声になっていた。
「それでは貴方の未来を石に聞いてみましょう」昴は興味をそそられて細くドアを開いた。
ユリの花瓶の陰から紅花の横顔が見える。
紅花は銀の箱から色とりどりの光る小石をビロード上に投げ落す。
ゴールドの煌びやかな指輪で埋め尽くされた指からこぼれ落ちたクリスタルは不思議な形を作って広がる。
「そうね、やはり今は動いてはダメよ現状維持を心がけて、解るわ貴方の痛みは良く解ります、そう貴方は逃げ出したいのね」客の女は大きくうなずいた。
「でも今が我慢のしどころよ、言葉には十分に注意してつまらない失言で信用を失わないように、人を羨んではいけないわ解るわね、そうその事を言っているのよ、今 貴方が考えをふらつかせて行動すれば大きな失敗が待っています」
「先生お願いです御力を、御力を私に分けて下さい」客の女は紅花の手を掴んで言った。
「そう仕方がないわね、それではいつもの癒しをしますがお解りよね、終わった後は少しの間眠くなりますよ、いいわね」
紅花はビロードのきんちゃく袋を開いて透明なクリスタルの粒を女の手の中に落とした。
女は両手でクリスタルを包み込むように握り、向かい合って座っている紅花がその手を両手で包みこんだ。
目を閉じた紅花の唇が少し動いて何かを呟いている。
女の体が僅かに揺れる。
昴はドアの隙間から息を殺して占いの様子を見ていた。
強いユリの香で頭がクラクラする。
ほんのりと淡い緑色のモヤのような物が女の体から浮き上がった。
それはほんの一瞬の出来事で昴が瞬きをしている間に、緑色のモヤは次の瞬間には消えていた。
客の女はカクッと首を折って、動かなくなった。
昴は怖くなって慌ててドアを閉めた。
沈黙の時間が続き、昴の心臓だけがドキドキと体の中で音を立てる。
チャリーン、チャリーンと金属のチャイムの澄んだ音がする。
「さぁ目を覚ましましょう、貴方の体は安らぎで癒されました」紅花は静かに言った。
「ありがとうございます」客の女の声がして昴はほっとした。
女が支払を終えたので昴は納戸のドアから出て、玄関まで見送りをした。
玄関を出る女の顔は晴れ晴れとして見えた。
客の後ろ姿を見送りながら紅花の占いの凄さに驚いていた。
でも、あの緑色のモヤはいったい何だったのだろう。
目の錯覚化かもしれないと思いながらも、昴の心に何か気に掛るものが残った。
|
5 花屋の美少女
午後の客が来るまでに帰ると言って紅花は車椅子を匠に操って出かけて行った。
一人残った昴は紅花の占いを思い返していた。
占いが終わった時の客の安らいだ顔が昴の目に焼きついていた。
紅花の占いは苦しみから救ってくれるのだろうか。
今まで占いに興味を持った事などなかったが、もしも紅花の占いが自分の進む道を教えてくれるなら聞いてみたいと思った。
実の両親と思っていた成川の父も母の本心を聞いてしまった今は、故郷に帰って以前のように暮らすのは辛い事だった。
自分が扱い易い子と言われ家政婦変わりにされていると知りながら毎日を過ごすなんて耐えられるだろうか。
実の親はいったいどんな人だろう、どんな理由で自分を捨てたのだろう。
成川の父が言っていた事が事実だったら実の両親は金を払って自分を厄介払いしたのだろうか。
昴は自分の居場所がすべて無くなってしまったようで孤独に震えていた。
膝を抱え泣いていた昴はいつの間にか寝ってしまいチャイムの音で目を覚ました。
午後の客が来たのだろうか、紅花は戻っていなかった。
ドアホーンのモニターを見ると花束を抱えた少女が映っている。
「こんにちは、フェアリーローズです」と言って綺麗な少女がモニターの中で微笑んだ。
昴は涙の跡を見られないように袖で顔を拭いドアを開いた。
ドアを開らくと背の低い少女が両手いっぱいに花束を抱え立っている。
「あら貴方誰なの紅花先生は?」
「べ、紅花先生は出かけています僕、昨日からここにお世話になって」
「そうなの、紅花先生に頼まれてお花入れ替えに来たのよ、フェアリーローズの優衣って言いますよろしくね」少女は白い歯を見せて笑った。
昴の反応を待たずに優衣はスタスタと廊下を通って占い部屋の花瓶の前に花束を置いた。
青いシートを出して床に広げ花瓶に活けてあった花をビニール袋に入れる様子は手際良がいい。
大きな花瓶の水を入れ替えるのは思った以上に大変で昴は優衣を手伝って何度もバケツの水を運んだ。
優衣は昴の手伝いをとても喜んで感謝した。 |
「このピンクのユリは随分大きな花ですね」昴が言った。
「これはソルボンヌって言うのよ紅花先生はこの花が好きで必ずソルボンヌを入れて活けるように言われているの私はこっちの白いカサブランカが好きなんだけどね」
「そうですね、優衣さんには白い花の方が似合いますね」
「ありがとう嬉しいわ、ねえ私たちって年も近そうだし友達になれるかしら」優衣の言葉に昴は有頂天になった。
「僕で良ければお願いします」昴は頬を赤らめて言った。
優衣は可笑しそうにクスクス笑いをして頷いた。
「でもね、紅花先生には当分の間は秘密にしょうね先生ってとっても厳しい人なのよ」
優衣が帰って昴は占い部屋の花瓶の前で白いユリの花を見つめていた。
目はユリの花を映しているが昴の心は優衣の姿を見ていた。
黒い潤んだ瞳、形の良い鼻、時々すねたように尖らす唇。
地味なエプロンに無造作に黒髪を束ねた優衣。
それでも優衣はとても美しく見えた。
ユリのむせかえるような強い香りに包まれて昴の頬は緩んでいた。
|
 |
夕方近くに紅花が帰って留守の間に優衣が来たのを知って眉根を寄せて不機嫌な顔をした。
「今日は来る日じゃなかったのに」紅花は呟いて人差し指で机を小刻みに叩いて苛立っているように見えた。
「貴方に何か」紅花が言いかけた時にチャイムが鳴って占いの客が来た。
昴は素早く玄関に行って客を迎える。
その間に紅花は占い部屋のドレープのカーテンの前に座りずっと前からそこに居たようなポーズを作る。
客は若い女でターコイズブルーのミニのワンピースを着て金色に染め上げた髪を頭の上で高く盛り上げている。
長いつけまつげとアイランで目を縁取り人形のような化粧をしている。
昴は新宿の町でよく見かけた出勤前のキャバクラ嬢だと思った。
占いは恋愛問題はがりで紅花は前の客と同じく銀の箱から光る小石をビロード上に投げ落して石の形を読んでいた。
紅花の占いの半分は人生相談のようで相手の話を丁寧に聞いて同感し時には叱るようにアドバイスをする。
客は紅花に話す事で気持ちが和らいでいるようだった。
「今日はどうしますか?」紅花が言った。
「残念だけど今日はやめときます、癒しをしちゃうと眠く成るでしょお店に出る前だから」
「そうね、またいらっしゃい」紅花は抑揚のない声で言った。
「昴、お客様がお帰りよ」紅花に言われて昴は慌てて納戸から出て先頭に立って客を誘導する。
昴は廊下を出る寸前の所で客に腕を掴まれて驚いて立ち止った。
「あら綺麗なタトゥーね、それシールなの」客の女が言った。
「えっ、タトゥーって何ですか?僕何もしてないですけど」
「ほらここよ、こんなに綺麗に光って、でも何か貼ってあるようでも無いし何処のお店でやったの教えてよ」女は昴の左腕の内側を指差した。
昴は自分の腕を見て驚いた。
左の二の腕の内側に花のような模様が虹色に輝いている。
指で模様を擦ってみたが何か付いているようでも無い。
何か知らないうちに薬品でもついてしまったのだろうか、昴は首をひねった。
店を教えてくれと煩く言う女をやっと送り出して玄関の中で改めて腕を見るとタトゥーは消えていた。
昴は訳が解らなくなってしまった。
いったいあの模様は何だったのだろう。
タトゥーの出ていた腕を摩りながら廊下へ戻ると消えていた虹色の模様が輝き出した。
昴はその輝きを見てはっとした。
ブラックライトだ、この廊下にはブラックライトが灯ている。
白いシャツが蛍光色のように光るのと同じように模様もブラックライトに光るんだ。
考えを確かめる為に玄関まで戻るとタトゥーは消え、廊下のブラックライトに当たると虹色の模様は輝き出した。
昴は玄関と廊下を何回も行来して確認をした。
次の客は昴が占い部屋に戻る前にやって来た。
仕立ての良さそうなスーツに身を包んだ四十過ぎの男は初めてのようで落ち着きが無い。
占い部屋の椅子に腰かけても物珍しそうにキョロキョロ首を動かしている。
紅花は静かに微笑んで男が落ち着くのを待っているようだ。
昴は占いよりもタトゥーの事が気になってさっさと納戸に入った。
床に座り壁に寄り掛かって左の二の腕を丹念に見る。
指で擦ったり匂いを嗅いだり舐めてもみた。
タトゥーの浮かんだ皮膚は蛍光灯の下では何の変化も見えなくて変わった所は無いようだった。
きっと何かが付いたんだろう、シャワーで流せば落ちるはずだ。
でも落とす前にこの綺麗な模様を優衣に見せたいと思った。
優衣もさっきの人みたいにこの模様を気に入るだろうか。
昴は優衣の笑顔を思い出して心が温かくなった。
ドアの外でガタンと大きな音がして昴は驚いて立ち上がった。
ドアに耳を押しあると紅花の声も男の話声もしない。
昴は心配になってドアを細く開け隙間から占い部屋を見た。
昴が見たちょうどその時、六角形のテーブルにうつ伏せになっている男の体から淡い緑色のモヤが湧き上がった。
モヤは一筋の帯となって一瞬で紅花の中に吸い込まれて消えて行く。
男はうつ伏せのまま微動だにしない。
午前に来た女の人の時は見間違えかとも思ったが、今度は見間違えでない事は確かだった。
紅花の占いはいったい何だろう。
紅花と客の男は時間が止まってしまったように動かない。
紅花は蝋人形のように表情のない顔で男を見ている。
沈黙の時がやっと過ぎて紅花は柄の付いた銅製のチャイムを振った。
チャリーン、チャリーンと涼やかなチャイムの音が響く。
「さぁ目を覚ましましょう、貴方の体は安らぎで癒されました」紅花は静かに言った。
男はテーブルからゆっくりと身を起し、大きなあくびをした。
「ごめんなさいね、癒しの途中で酒井さんが気を失ってテーブルに額を当ててしまったのよ、痛むかしら」紅花が言った。
「ああ、それで額がね、構いませんよ」男は額を摩りながら言った。
「お陰さまで気持ちが楽になりました、緊張していた物が抜けて行ったような感じです、ありがとうございました」男は額が赤くなった顔で笑った。
昴は安心して納戸のドアを閉めた。
やっぱり紅花先生の占いは凄いんだ、自分もあの人のように占ってもらいたい。
昴は考えながら床に座り込んでダンボールの山に何気なく目を向けて驚いて声を上げそうになった。
ダンボールの積み重なった一番上の箱の上でブナが緑の目を見開いて昴を睨んでいる。
いつの間に入り込んだのか困った事にすぐに納戸を出る事は出来ない。
昴はブナの方を見ないようにして息が詰まる思いで客が会計を終えるのを待っていた。
|
6 見守り
ブナは困っていた。
天井裏の隠れ部屋から戻る途中を昴に見つかってしまい床に降りる事も出来ずにいた。
眼下では昴が怯えたような顔でブナを見ている。
こんなに猫を嫌いな人間にどうやって接したら良いものかとブナは迷っていた。
このまま少し待つしか無いとダンボール箱の上で毛づくろいを始めたが、気持ちは焦るばかりだった。
状況は悪い方へと向かって進んで居るのは確だった。
一刻も早く昴を紅花から遠ざけなければいけない。
ブナは肉球が汗でベタつくのを感じて、前足をなめた。
先代の猫の後を継いで七年の間、ブナは紅花から目を離さず監視を続けて来た。
紅花は要注意人物として代々猫たちの監視下にあったが、少量のナトランを盗む以上の事は確認されていなかった。
それが先週になって不審な動きを見せた。
占いの客をキャンセルして五日間も連続して外出したのは珍しい事だった。
不審に思ったブナは紅花を追った。
紅花は繁華街を何かを探すように歩まわり、場所を決めると立ち止まり永い時間そこに留まった。
立ち止った紅花に見つからないように注意してブナは庇の上に飛び乗って紅花の視線の先を追いかけた。
視線を辿った先には、植え込みの縁石の上に少年がしゃがみ込んで居た。
青いタイリーマークが入ったシャツを着た少年の後ろ姿を見てブナは驚いた。
少年の背中からは見た事とのない大量のナトランが立ちあがっている。
ナトランは緑色に煌めきながら陽炎のようにゆらゆら揺れている。
ブナはこれほど濃い色のナトランを見るのは初めてだった。
生あるすべての生き物はナトラン持っている。
多くの人のナトランはぼんやりと体を包む程度の輝きで緑や青の淡い色をしている。
色の濃さや輝きに多少の差はあっても、目の前に居る少年は特別だ。
この少年に紅花が目を付けるのも当然だった。
これほどのナトランが奪えたら紅花は、百年は楽々と生き伸びるだろう。
ブナはやっと歩き出した紅花の後ろ姿を目で追っていた。
紅花が去った後に少年を改めて見ると、少し離れた植え込みの影に痩せて汚れた赤茶色の猫が座っていた。
ブナは低い声で鳴いて赤茶色の猫の注意を引きつけた。
赤茶色の猫はブナをすぐに見つけて、歩道を歩く人の間の足元をすり抜けて進みブナの居る庇に飛び乗った。
「私をお呼びになりましたか」赤茶色の猫は予想もしない丁寧な言葉で言った。
ブナは赤茶色の猫の言葉使いと意志の強よそうな目を見て確信を持った。
「貴方は、あの少年の身守りの方ですね」ブナは言った。 |
「いかにも、昴様の身守りをしていますチャスケと申します、失礼ですが黒猫殿は伝説のブナ様とお見受けしましたが」赤茶色の猫はブナの目をまっすぐ見て言った。
「伝説とはたいそうな事ですねテレますなぁ、しかし私を知って居るのでは話は早い、早速ですがチャスケ殿の任務についてお聞きしたいのですが」
「貴方様の緑の目を見ればブナ様と間違える事もないでしょう、ここでお会い出来たのは幸運でした、これは是非にもお伝えしなければならない事です」
ブナとチャスケは、不安定な庇から隣のベランダに飛び移った。
ここなら眼下に居る少年を見失う事もなくゆっくり話が出来る。
「私ども一族は三代前より、バルク様の命令を受けて昴様の身守りをしております。
昴様はここから南に三日ほど下がった海辺の町に暮らしており、見守りは先々代より永い年月を危うい事も無く平穏に過ぎてまいりました。
それが先週になって昴様の身に只ならぬ事が起きたようでございます。
昴様が何に心を痛めて居るかは私どもには解りませんでしたが、あの時のナトランの揺らぎは恐ろしいほどでございました。
普段から特別に濃い色のナトランがあの夜は焚き火の炎のように立ち上がって昴様の体を覆っていました。
|
 |
昴様が泣かれるとナトランも青み掛った色になり悲しみが全身から溢れ出て居るようで、見ている猫たちも心を痛めました。
昴様はその夜に住み慣れた海辺町を出てこの新宿にやって来たのです。
見守りをしていた猫の中で私だけが運よく電車に乗ることが出来まして、昴様の御姿を見失わずに来られました。
実はたった一匹なので仲間への伝令の方法もなく困り果てていた所でございます。」チャスケは眼下に居る少年から片時も目を離さずに言った。
「それは遠い所をお一人で良く来られましたご苦労を御察し致します、お身内への伝令は私にお任せ下さい、連絡がつくまでは我々の仲間がチャスケ殿のお手伝いを致しましょう」ブナは労いの気持ちを込めて言った。
チャスケが数日間ほとんど食事もしないで見守りをしていたのは彼のやつれた様子が気の毒なほど表していた。
チャスケは海辺の町から一人追跡を続けて疲れ果てていることだろう。
「肝心な事をお聞きしますが、彼のナトランが特別な訳をチャスケ殿はご存じですか」ブナが言った。
「私達見守りの身分では確かな事は知らされてはいませんが伝え聞いたところに寄りますとバルク様と縁の在る方らしいです」チャスケは声をひそめて言った。
「バルク様と縁ですと!」ブナは桃色の口を開いた。
バルク様と縁があるとはいったいどんな関わりなんだろう。
ブナは胸騒ぎがしてならなかった。
何かが動いている、ブナは目の前の少年を見つめてブルッと身を振った。
紅花は少量のナトランを人から奪って自らの命を継いできた。
ナトランを奪われた人は確実に命の時を減らすが、紅花が一回に盗む僅かな量では数ケ月が短くなるだけの事だろう。
生命を持つ者は皆ナトランを消費しながら生きている。
ナトランを持つ事はすなわち生なのだが、生には悩み苦しみ、怒り喜びと諸々の事がつきまとう。
生きて行くと言う事は試練なのだとブナは思う。
僅かの善き事多くの悪しき事、ナトランを持て余す者が居ても不思議はなかった。
紅花からナトランを盗まれた者が癒されたように感じるのはブナにも理解の出る事だった。
青の組織の生き残りの紅花と永く暮らすうちにナトランを求め続ける彼女を哀れに思うようになっていた。
ブナは、紅花がこれ以上の悪事をしないよう祈っていた。
ブナの思いに反して昴を見つけた紅花は獲物を逃す事はなかった。
数日後にはまんまんと昴を家に招きいれ一緒に暮らすようになってしまった。
その上に悪い事に昴は紅花の占いに興味を持ってしまっているようだ。
このままでは昴のナトランが奪われるのは時間の問題だった。
昴に警告の念を送っても、こんなに猫を嫌いな人間が自分の思念を受け止める事は難しいだろう。
海辺の町に帰ったチャスケからの連絡はまだ届かない。
ブナはダンボール箱の上で考えこんでいた。
|
7 嵐の予感
昴が紅花の家で暮らして一週間が過ぎた。
昴は無計画に気持ちのままに家を出てから浮浪者のように町を彷徨っていたのを偶然のきっかけで紅花の家に住むようになったのを幸運に思っていた。
Blue heavenに来てから昴は三度の食事と安心出来る清潔な寝床を得て、落ち込んでいた気持ちも明るさを取り戻してきた。
故郷への思いはいつも心の中に刺さり痛みを感じたが、両親に電話をして居場所を知らせる気持にもならなかった。
昴は怖かった、母からもう帰らなくて良いと言われるのも辛い、反対に何も心配しないで帰りなさいと優しい言葉を掛けられても信じられず自分を利用する為の芝居と思えてしまう。
両親との関係を完全に絶ってしまう勇気もない半面、元に戻る気持ちにもなれず考えはいつも迷路に入り込んでいた。
昴は行く道が見えないまま紅花の脚が治るまでは、ここに置いてもらおうと思っていた。
紅花は昴について何も聞かない。
それが紅花なりの優しさなのか、単なる無関心なのかは解らない。
もしかしたら、占い師の紅花は聞かなくても全てを感じでいるのかも知れないと昴は思っていた。
紅花が占いで見せる不思議な様子を何度も見るうちに、紅花が自分の気持ちを解ってくれるような気がしていた。
昴は紅花に自分の将来を占ってもらいたいと思う気持ちが強くなっていが、占いに払えるお金などは持ち合わせていなかったのでタダで占って欲しいと言うのも図々しい気がして言い出せずにいた。
紅花の友人のマリアは始めて会った日から昴を気遣って世話を焼いてくれる。
今日もマリアのマンションに招かれてオムライスのランチを御馳走になった。
ニューハーフのマリアは女性よりも細やかな気働きをしてくれる。
昴はポーカーフェイスの紅花よりも喜怒哀楽の激しいマリアに、ついつい気持ちを許して甘えてしまう。
マリアの方も言いたい事は隠さず言うし歯に衣を着せない。
そんなマリアだから昴は紅花にも話して居なかった家出の話をしてしまった。
「マリアさん僕、紅花先生にもまだ話していないんだかんら、ここだけの話にして下さい」
「解ってるわよ、でもね紅花だったら聞かなくてもアンタの事くらい見透かしてるわよ」
「やっぱり紅花先生って超能力者なんですか」昴は真顔で言った。
「キャハハァ〜超能力ねぇアンタ面白いこと言うわねぇ紅花が聞いたら何んて言うかしら」
「僕また変なこと言っちゃいました、マリアさん紅花先生には言わないで下さい、お願いします」昴は慌てて言った。
「ホント昴って可愛いわぁアンタ素直な子ね、こんなにイイ子なのにまったくねぇ」マリアの笑顔は曇った。
「それでこれから先、どうするつもりなの?」マリアは言った。
昴はしばらくの間考えこんでやっと言った。
「僕いろいろ迷って気持ちがまとまらないんです、家に戻って高校だけは卒業しょうかとも思いましたけど決心がつかないし、戻らないなら生活出来るように働く所を見つけないといけないと思うし」
「そうね、家に戻るのは相当の覚悟が居るでしょうよ、紅花の脚が治るまでにはどうするか決めないとね、もし仕事を探すのだったらアタシも協力するわよ」
「マリアさんありがとうございます僕、本当は紅花先生に将来を占って欲しいと思って居るんです」
「あら、それはいい考えかもね紅花に頼んだらいいわよ」マリアが言った。
「でも僕・・・・占いの支払が出来るお金が無いから」昴が言った。
「あ、アンタそんな事気にしてるのぉ紅花が昴からお金を取る気なんて無いわよぉ、それぐらいだったら家に置いたりするもんですかぁ」マリアは呆れたように言った。
「でも僕、余りに申し訳なくって」
「その遠慮深い所が昴の良い所かもね、いいわ今度アタシが紅花にそれとなく言ってあげるから任しときなさいよ」マリアは長いまつ毛でパチンとウインクをして言った。
「マリアさん今日は本当にありがとうございました、オムライス美味しかったです」昴はお礼を言ってマリアのマンションを出た。
エントランスのドアを開けて空を見上げると雲行きが怪しくなって、湿気を含んだ生暖かい風が吹いている。
そう言えば、朝の天気予報で台風が来ると言っていた。
朝は日が差して晴れていた空が嘘のように変わりどんよりとくすんだ空に鉛色の雲が風に飛ばされて東の空へ流れて行く。
昴は四谷から新宿御苑の側道を通って帰り道を急いだ。
御苑の森の木々がゴウゴウと生き物のような唸り声を上げて揺れている。
灰色の空からはポツポツと雨粒が落ちてきて乾いた歩道に吸い込まれ埃っぽい臭いがする。
昴はシャツに付いているフードを頭に被り急ぎ足で進む。
雨はだんだん大粒になって容赦なくシャツに浸み込む。
昴は家に帰るのを諦めて、フェアリーローズに寄って優衣に傘を借りようと交差点を曲がった。
横断歩道の向こう側にフェアリーローズの赤い日よけが見える。
昴は信号を待ちながら優衣の笑顔を思い出して頬が緩んだ。
「友達になりましょう」と優衣から言われて一週間二人は紅花に悟られないように密かに電話で話をし、待ち合わせをして毎日欠かさず会っていた。
昴は合う度に優衣に惹かれて行く。
紅花に隠し事をするのは、気持ちが咎めたけれど一度も女の子と付き合った事がなかった昴は優衣への気持ちを止める事は出来なかった。
信号が変わる寸前に店の前にタクシーが止まった。
タクシーのドアが開いてタンポポ色の髪の毛見えて、それがフェアリーローズの中に小走りで入っていった。
昴は自分の目を疑った。
紅花先生どうして・・・・昴は車椅子の紅花が身軽に走って行ったのを見て呆然となった。
信号が数回青に変わっても昴は目の前の出来事が理解できないで立ち尽くしていた。
ますます激しくなった雨に濡れながら目だけはフェアリーローズから離せない。
歩けないはずの人が歩いている、紅花先生はなぜ僕に嘘をついたのだろう。
あんなに急いで花屋に行くなんて、どうしたのだろう。
不安と好奇心にかられて昴は店から見えないように気を付けて横断歩道を渡った。 |
フェアリーローズの隣の美容室の傘立てから紺色の傘を無断で借りて、反対側の路地に回り込んで傘で顔を隠した。
ガラス超しの胡蝶蘭の鉢の影に紅花の横顔が見える。
いつも顔色の悪い紅花が今日は一層青ざめて厳しい顔をしている。
話をしている相手は誰だろう柱に隠れて姿が見えない。
昴はウィンドウにピッタリと耳を付けて店内の音を聞こうとするが雨の音と車の騒音だけしか聞こえない。
ガラスの向こうの紅花は時折顔をしかめて頷きまるで叱られている子供のように見えた。
紅花の唇が大きく動いて何かを言った。
その瞬間、タンポポ色の髪の毛が大きく揺れて胡蝶蘭の鉢が倒れ紅花の背中は勢いよくウィンドウに押しつけられた。
昴はガラスに伝わった振動に驚いて傘の中に潜り込み、足早に店を離れた。
紅花と昴の距離はウィンドウを隔てて十センチもなかった。
昴は震える指で傘をしっかりと握りしめて横断歩道を渡った。 |
 |
横殴りの雨の中をしばらく歩いてマクドナルドを見つけて壁際の奥の席に座った。
店の中は混んでいて買い物帰りらしい女性のグループ賑やかな笑い声がしている。
昴は顔を壁に向けてなるべく目立たないようにして頭の中ではフェアーローズで見た光景を始めからリピートさせる。
胡蝶蘭の鉢が倒れた時、紅花先生は誰かに突き飛ばされたのかもしれない。
突き飛ばしたのは話していた相手だろう。
フェアリーローズの店の人?だけどどうして紅花先生がそんな事に。
昴は紅花の青ざめた顔を思い出して心配でならなかった。
優衣さんはあの様子を見ていたのだろうか。
昴は優衣に聞いてみようとフェアリーローズに戻る決心をしてマクドナルドを出た。
雨は小降りになっていたが、空は夕方のように暗く沈んでいた。
店の前まで来ると赤い日よけの下で優衣が鉢を運んでいた。
「優衣さん」昴は無理に明るい声を作って言った。
「あら昴出かけていたの、さっきBlue heavenに電話したのよ」優衣は少し微笑んで言った。
「ごめんなさい、マリアさんのマンションへ行ってたので」
「いいのよ、台風が直撃しそうなのでお店は早じまいなのそれで会えないかなと思って電話したのよ」
「帰って紅花先生に占いの予約を聞かないと時間が解らないので」
「こんな天気だし大丈夫じゃない」優衣が言った。
「僕も聞きたい事があって、優衣さん三十分ぐらい前からお店に居ましたか」昴が言った。
「何かしら、配達があって出かけていたけど」優衣は一瞬、顔を曇らせた。
「あっ、何でも無いんですマリアさんの家から電話したんだけど」昴は慌てて嘘を言った。
「今夜はゆっくり会えるといいわね」優衣は言って鉢を持ち上げた。
「優衣さん僕も手伝いますよ、変わった花ですね青いビーズが一杯付いてるみたいで綺麗ですね」話題を変えようとして昴が言った。
「いいわ、私の仕事だからそれより早く帰って連絡してね」優衣は昴の手を優しく握って言った。
|
8 ブナの警告
優衣が触れた手の感触が無くならないように昴はジーパンのポケットに手を入れて帰り道を急いだ。
昴はBlue heavenに戻り自分の部屋に入り濡れたシャツを着替えた。
何となくタンボール箱の奥に目をやると窓の外に白い影が動いている。
以前も猫が来ていた場所だけどまさかこんな雨の日に猫が来るなんて、と思いながら昴は建付けの悪いサッシを引いて窓を開けた。
窓の外に居た濡れた白い猫は驚いて一目散にアルミのベランダから隣の軒に飛び乗り、それと同時に黒い猫が凄い勢いで昴の脇腹をかすめて部屋の中に入って来た。
ブナ?昴は呆気にとられて黒い塊を見た。
ブナは床の上にトンと降りて足を突っ張って立ち背中をブフルブルと震わせて水滴を飛ばした。
昴は目を丸くして隣の軒でこちらを睨んでいる白い猫と濡れた前足を舐めているブナを交互に見た。
「もしかして雨の中でデートしてたの?」昴はつぶやいた。
「そんな訳ないだろ」
え?誰か何か言った? 昴は声がしたような気がして部屋の中を見まわした。
ブナはドアの隙間を前足で広げて、スタスタスと部屋を出て行った。
濡れた足跡が占い部屋から紅花の部屋まで続く。
昴はモップで床を拭きながら紅花の部屋のドアを叩いた。
「お入り」紅花の声がして昴はドアを開いた。
紅花はフェアリーローズで見た姿が嘘のように前と変わらず車椅子の上で本を読んでいた。
「今呼ぼうとしていた所よ、ブナが水浸しでしょ捕まえてタオルで拭いてちょうだい」紅花が言った。
「僕・・・猫は触れないので」歩けるのに自分で捕まえてよと昴は思った。
「このままじゃしょうがないでしょ、ブナはおとなしい猫だから引っ掻かないわよ」紅花は譲らない態度で言った。
昴は紅花に言い返す訳にもいかずに、怖々と猫の後ろに回って背中にタオルを掛けて水を吸い取った。
紅花先生は何で歩けない振りをしているのだろう、車椅子の不自由な生活をしていて何の得になるのだろう。
昴は不思議でならなかったが、先生の脚が治れば昴はこの家から出る事になる、そう考えると歩けない芝居が何の目的でも昴には都合の良い事だった。
「さっきマリアから聞いたけど将来を占って欲しいですって?」紅花が言った。
「マリアさんもう電話したんですね」昴は猫の背中を拭きながら言った。
「台風でお客のキャンセルが出たから今夜だったら占ってあげるわよ」紅花が言った。
「お願いします、僕ずっとどうしらいいか解らなくて」
「でも言っておくけど占いで行く道を決める事は出来ないわよ、自分の進む道は自分で決めるしかないの」
「はい、ありがとうございます今夜がとっても楽しみです」昴は思いっきりの笑顔を紅花に返した。
夕方になって嵐は益々激しさを増して紅花の部屋の窓ガラスを激しく揺すった。
テレビのニュースで東京は暴風圏内に入ったようで、台風は夜半には房総沖に接近すると言う。
昴は夕食にパスタを茹で缶のミートソースで和えた。
紅花はパスタに手を付けず赤ワインとチーズを一切れ食べただけだった。
ブナは窓際のソファの上に座って尾をパタパタと座面に打ち付けている。
嵐の音が部屋の中まで響いて落ち着かない気分にさせる。
「逃げるんだ」どこかで突然声がした。
昴は紅花の顔を見たが紅花は無表情にテレビの画面を目に映している。
テレビの音声ではなかった、嵐の音を聞き間違えたのか昴は耳の穴に指を入れて探ってみた。
「さあ立ち上がって」声がして昴は無意識に立ちあがった自分に驚いて部屋の中を見回した。
「十時になったら占いを始めるから」紅花が言った。
昴は立ち上がってそのまま座るのも変に思われると思ってお願いしますと言い紅花の部屋を出て自分が使っている納戸に入った。
納戸の型ガラスの窓に雨が当たって斜めの縞模様を作っている。
強い風に押されて建付けの悪いサッシが煩い音を立てる。
昴は折りたたんである布団の上に腰を降ろそうとして驚いた。
さっきまで紅花の部屋に居たブナがちゃっかり布団の上に座り込んで顔を洗っている。
ブナは昴を上目づかいに見上げて口を小さく開けて小声で鳴いた。
昴は始の頃よりはだいぶ猫に馴れたものの苦手には変わりがない。
布団の上に座るのを諦めて窓際のダンボールの隙間に避難した。
占いが始まるまでの一時間、マリアから借りたアイポットで音楽聞こうとイヤホーンを耳に押しこむ。
昴の知らない女性アーチストが気だるい声でジャズを歌う。
マリアの音楽の趣味を意外に思ったが、嵐の音とジャズのサンドは妙に似合っていた。
昴はジャズの音を聞きながら浅い眠りに落ちていた。
「急いで、すぐにここを出て」ジャズの音楽の合間に声がした。
昴は飛び込んで来た声に驚いて、急いでイヤホーンを外し部屋の中を見まわした。
納戸を隅々まで見ても昴と猫以外の生き物は居ない。
ブナは布団の上で昴をまっすぐに見つめて居る。
まさかね、そんなバカな事は無いよね。
昴は自分の考えに苦笑した、猫がしゃべるはず無いもの。
その時、はっきりとした声が聞こえた。
「昴、オレの言葉が聞こえるのか?」
昴は驚いて飛び上りそうになった。
猫は耳を下げて不審そうに昴を見ている。
「そうだオレだブナだよ、どうやらオレの声が聞こえるらしいな、こっちで人間と会話できるなんて事は初めてだよ」猫の口は動いて居ないが昴の頭の中に声が響いている。
昴は襲われそうな気がしてダンボールの窪みに体を沈めた。
「怖がらないで、危害を加えたりしないから・・・困ったなぁ」声が聞こえた。
「本当に猫がしゃべったそんなバカな事、これはきっと夢なんだ」昴はそう思った。
猫は緑色の目でまっすぐに昴を見つめる。
「夢かぁ、そう夢だよ、猫が喋るんだもの夢だからオレの話に付き合ってくれないか」ブナは言った。
昴は疑いながらも夢だと解ってホットした。
夢の中だったら猫だって怖くは無いぞ、少しは苦手だけど・・・・
猫が自分の考えを読んで頭の中で会話するなんて、夢に決まっていると昴は思った。
ブナは慎重に距離をとりながら昴に近づいて言った。
「今日紅花を花屋で見た時の事をどう思う」ブナは唐突に言った。
「どうって、紅花先生が歩いていた事、何でブナが知ってるの?」
「さっき外に居た白い猫からから聞いたんだ、紅花が嘘を言って居るのが少しは解っただろう、だいたい昴がここに来た事も紅花が仕組んだ事なんだ」
「それは・・・・先生が歩いて居るのを見て僕も変だと思ってるけど、僕に嘘を言っても紅花先生の得にならないでしょ、僕は何も持ってないし僕に何をしょうって言うの」昴が言った。
「何も持って無いだと?自分の持っている物が解らないとは人間ってヤツは」ブナは尾をピシッと布団に強く打ちつけて言った。
「僕が何を持ってるって言うの、お金も無いし盗られるような物は無いよ」
「命はどうかな」ブナは桃色の口を少し開いた。
何て嫌な夢を見ているのだろう、昴は思った。
「紅花先生が僕を殺すって?」
「殺す訳では無いんだ、命を削られてしまうんだよ」ブナが言った。
「訳が解んないよ、それってどう言う事なの」
「君には見えないから理解出来ないかも知れないが生き物はナトランを持って生まれナトランを消費しながら生きて行く」
「ナトランって何だよ、そんなの聞いた事ないよ」
「まあ話を聞きなさい、ナトランは生命の元を司る物、物と生き物の差は何だと思う」
「それは命が在るかどうかでしょ」
「命が在るかどうかは、どうして決まるのかね」
「それは、生きているかどうかって事」
「生きているかどうかは、どうして決まるのかね」
「それは、心臓が動いて居るかどうかって事だよ」
「植物には心臓は無いが生きて居る、それでは答にならないよ」ブナは言った。
「答えは簡単だ、ナトランが宿ると物は生き物になり、ナトランが去ると生き物は物に帰る」
「ナトランって命の元って事なの」昴は言った。
「まあだいだいは、そう言う事だ」
「でも紅花先生が僕の命を削るって訳が解んないよ」
「そうかな、しもナトランを少し盗まれたら君はどうなると思う」
「命の元を減らされたら寿命が縮まるでしょ、そんな事あり得ないけど」昴は苦笑いをした。
「紅花は占いの客から癒しをすると言ってナトランを少しづつ盗んで居るんだ」ブナの言葉に昴は顔がこわばった。
昴は癒しの最中に客から浮かび上がった淡い緑色のモヤのような物が一筋の帯となって一瞬で紅花の中に吸い込まれていったのを鮮明に思い出した。
「やっと解ったようだな、だがお前が客達と同じだったら俺は黙っていただろう、昴お前のナトランは特別なんだ」昴は青ざめた顔でブナを見つめた。
昴は胸の心臓の鼓動を強く感じながらこの嫌な夢から早く覚めてしまいたいと思っていた。
昴は言葉を失ってブナを見ていた。
その時、ブナの耳が入口の方に向かってねじれた。
ドアが開く音がして昴とはぎょっとした。
|
9 嵐の夜
紅花が車椅子を押して納戸に入って来るのは初めてだった。
「何をしてるの、もう十時よ早くしなさい」紅花は機嫌の悪そうな声で言った。
「ごめんなさい、すぐ行きます」昴は言って立ち上がった。
ブナがにゃぁと低く鳴いた。
「おい、やめろ今すぐ逃げ出すんだ!」頭の中でブナの声が聞こえる。
「でも、そうもいかないから・・・」昴は頭の中でブナに答える。
紅花は占い部屋の六角形のテーブルの前に在る奇妙な動物の木彫付いた椅子に前かがみに座り昴を待ちかまえていた。
昴はテーブを挟んだ向かい側の椅子に腰を下ろす。
部屋の中は薄暗く、テーブルの上に或るローソクの形のシャンデリアがオレンジ色の淡い光を灯している。
紅花が金属で出来たワゴンをテーブルの横に引き寄せクリスタルの燭台に乗った蝋燭に火を灯す。
昴は強いユリの香に頭の芯が痺れていく。
豪華なドレープのカーテンを背にして座った紅花は静かに微笑む。
昴の目に映る紅花は怪しく謎めいて見える。
「私には解ります、貴方がどんなに悩んでいたのか」紅花は静かに言った。
昴は何も言わず紅花と目を合わさないようにうつむいた。 |
「試練の山を乗り越えてこそ道は開けるのです、道に迷わぬよう貴方の未来を石に聞いてみましょう」
紅花は銀の箱から虹色に輝くクリタルの小石を手のひらにすくい取りビロードの布に投げ落す。
黒い布の上に落ちたクリスタルは星空のように広がる。
紅花はクリスタルの上に手をかざして、目を細めて言った。
「貴方は他人にどう思われているか随分気にする人なのね、他人に認められれば自分に自信が持てると考えてしまうことがあるでしょ、それ
は間違いでは無いけれど、この考えに依存してしまうと自分を認めてくれる相手を求めて自分がここち良い相手ばかりを選ぶ事に成るわ、 |
 |
でもそれはどうでしょう貴方を認めない批判的な辛口の言葉を言ってくれる相手こそが貴方を成長させる人でしょう」昴は紅花の言葉にうなずいた。
昴は幼い頃から父や母から褒められる事が嬉しくて家の手伝いや弟妹の世話をして来た。
母はいつも微笑んで左の頬にエクボを作り「昴ありがとう助かるわ」と優しく言ってくれた。
金目あてに貰った子、家政婦代わりに使った子そんな母の言葉を聞いた今でも自分はつい相手にどう思われるかを考えて行動してしまう。
そんな自分の考え方が行く道を閉ざす事に成るとは思ってもいなかった。
「まず自分自身を知りなさい、そして自分がどう感じているかそれを尊重しなさい」紅花は言った。
紅花は散らばったクリスタルの石を中央に集め指の腹を使って布の上に帯状に押し広げた。
「貴方は今運命の分岐点に居るようね、まぁこれは・・・・」紅花は眉根を寄せて石を見た。
沈黙の時間が永く感じられる、嵐の音は部屋の中まで響いて蝋燭の炎がチラチラと揺れている。
「先生・・・・」昴は耐えきれなくなって言った。
紅花はやっとテーブルから顔を起して昴を見つめた。
「運命は自分で切り開くもの占いで行く道を決める事は出来ないのよ、何が幸か不幸かは貴方自身が感じるもの」紅花はこわばった顔で言った。
「先生、でも何か」
「そうね、せっかく占ったのだから一つ言いましょう、石は貴方の未来に女性が大きな関わりをしていると言っているわ」紅花は言った。
「女の人ですか?」
「そう彼女との出会いが貴方を変えそうね、今の貴方の心は堅くて疲れているわ、今夜は特別に癒しをしてあげるからテーブルの上に手を出しなさい」昴は癒しと聞いて全身の毛穴が縮むのを感じた。
客達が癒しを行った時に見た光景を思い出した。
僕もナトランを盗まれてしまう、助けて!
昴は頭の中でブナに叫んだ。
今、頼れる者はブナしかいなかった。
紅花は昴を真っ直ぐに見つめ両手をテーブルの上に置いて、昴が手を重ねるのを待っている。
紅花の視線が刺さったように昴を捕え、昴は逃げ場のない事を感じた。
昴が震える手をテーブルの上に置こうとした時、ガシャンと大きな物音が納戸から聞こえた。
「何だろう僕、見てきます」昴は飛び上がるように椅子から立ち上がった。
占いの部屋から鏡のドアを開いて一目散に納戸の中に滑り込む。
「早くドアを開かないようにして!」納戸の中に居たブナが言った。
昴はスチールの棚を横倒しにしてドアに押しつけた。
「窓から外へ逃げるんだ」ブナが言った。
昴は急いで建付けの悪い窓を力いっぱい引いた。
強い風と雨がいっきに部屋の中に入って来る。
一瞬で昴はずぶ濡れになった。
「ブナ無理だよ、隣に飛び移るなんて出来ないよ」昴は言った。
嵐の中を足元の危ないアルミのベランダから三階の高さを隣の軒まで飛び移るなんてとても出来ない。
「昴どうしたの、ドアを開けなさい」ガチャガチャと音がして紅花がドアノブを揺すっている。
「仕方がない、昴ついて来るんだ」ブナは部屋の隅に置いてあるダンボールの山に駆け上がった。
ドンドンとドアを叩く音が聞こえる。
「何やってるの!ドアが開かないじゃない」紅花が金切り声で叫ぶ。
納戸の中は開け放された窓から嵐が飛び込んで部屋中を駆け回っている。
昴は必至になってダンボールの山に這い上がった。
ダンボールを頂上まで登ると死角になった部分の天井に点検口らしい小さな入口が開いた状態になっている。
ブナは後ろ脚でダンボールの箱を強く蹴って、四角の闇の中に飛び込んで行った。
昴も続いて四角の闇の中に頭を突っ込む。
薄暗い天井裏のコンクリートの壁の向こうは真っ暗な闇が深く続いている。
「早く昇るんだ」ブナは闇の中から言った。
昴は体がぎりぎり入る小さな穴に上半身を入れてやっとの思いで闇の中に入った。
天井裏は埃っぽい臭いで息苦しい。
体を少し起こしただけで頭が当たってしまった。
これじゃぁ這って行くしかないようだ。
「上がったら扉を閉めて」ブナは前方の闇の中から戻って来て言った。
点検口の扉を閉めると天井裏は漆黒の闇に変わった。
「ブナこれじゃぁ進めないよ」
「手間のかかる奴だな、俺が案内するから大丈夫だまずはそのまま進め」
昴はひじを付いて闇の中を這って進む。
下の納戸からは風の荒れ狂う音とガシャンガシャンと金属がぶつかる音がする。
ドアの間に挟んだスチールの棚がいつまでもつのか、紅花が納戸に入るのも時間の問題だ。
「右に四十度曲がって」ブナが言った。
昴は鼻をつままれても解らない暗闇の中で向きを変えた。
「違う!もう少し左だ」
「ブナまだ遠いの」昴は埃と暑さにうんざりしながら言った。
「もう少しだ紅花が納戸に入って来るぞ、音をたてないようにしろ」
昴は自分が蛇にでもなったような気分でズリズリと天井裏を進んだ。
もう限界だと思った時にカチャと音がして闇の向こうに線のような光が漏れた。
ドアが開いてブナの黒い影が見える。
昴は残っていた力を振り絞って光に向かって進んだ。
闇からの出口の扉はバスタオルほどの大きさで古びた木で出来ていて牛の鼻輪のような形の金属の取手が付いている。
ビルの点検口の出口のドアにしては余りに不釣り合いだ。
これじゃぁまるで不思議の国のアリスだな、昴は思った。
昴は体を斜めにしてやっと闇から出て光の溢れる部屋の中に出た。
縮んだ腰を伸ばして部屋の中を見て昴は仰天した。
目の前の部屋は全体が古い石で出来ていて、素朴な木製のベッドとテーブルが置いてあり家具はどれも子供向けのように小さい。
その上考えられない事に窓の外に澄み切った青空が見え、鳥の鳴く声まで聞こえている。
昴は言葉が出ずにブナを見た。
ブナは意地悪そうな顔をして「アリスちゃん不思議の国にようこそ」と言った。
|
10 遺跡の町ゾハラン
昴は頭が天井に付きそうな部屋の中をうろうろと歩きまわっている。
天井裏を這いまわったせいでシャツは真っ黒だ。
ブナはベッドの上で後ろ足の指をめいっぱい広げて肉球をていねいに舐めている。
昴は窓から外を眺めたり、机の上の小物を物色したり落ち着きがない。
「いい加減、落ち着かないか」ブナが言った。
「そりゃぁ夢だって解っているよ、こんな事実際に在る訳ないもの」
「まったく面倒なやつだな、何だって真面目に考え過ぎなんだよ夢の中だぜ危ない冒険だって夢だから楽しんだらいいじゃないか」
台風の真っただ中、紅花の部屋の天井裏を抜けて出た場所は余りにも変だった。
いったい自分は何処に来てしまったのだろう。
どう見てもここは、新宿の町の中じゃない。
外の青空は昴が今まで見た事の無いほど鮮やかで太陽の日差しがとても強い。
遠くに見える茶色の岩山も森もコントラストが強くはっはりした色合いだ。
古い石組で出来ているブナの隠れ家は何もかも子供サイズで、使い込まれた道具が永い年月を語っている。
「ねえブナここは君の家なの?紅花先生はもちろん知らないよね」昴は言った。 |
「俺が人間をここに連れて来たのは初めてだよ、紅花は知らないしここまで追いかけては来ないよ、しばらくここに居て成り行きを見た方がいい」ブナは言った。
「人間が居ないの?ここって猫の国なの」
「人間が居ない訳じゃない、昴もしばらくはフレハラスで暮らすんだから少しは教えておこう、ここは猫の町ゾハラン俺の故郷だ」
「フレハラス?ゾハラン?いったい何処に来ちゃったんだ」
「フレハラスは南の海に浮かぶ島さ、地図には載っていないが地上に実在する。ここは秘密の場所なんだ、ここでの生活は人に話してはいけない、おい昴これが夢だって事を忘れないようにな」ブナは言った。
|
 |
夢、夢なんだ昴は何度も自分に言い聞かせないとつい忘れてしまう。
こんなに、はっきりした夢を見るなんておかしいとは思いながらも目の前に起こっている現実の方がもっと理解不可能だった。
「ねえブナ、僕帰れるんだよね」昴が不安そうに言った。
「ああ、夢が覚めれば現実に戻るのは当たり前じゃないか」
「うん、そうだけど紅花先生きっと怒っているだろうと思って」
「お前な、まだ解ってないな」ブナは鼻をフンと鳴らした。
「僕がナトランを盗まれそうになったのは解ってるよ、でも紅花先生がそんなに悪い人には見えなくて」昴は言った。
「紅花は哀れな人なんだよ、まぁやってる事は盗みだから同情はしちゃぁいけないけど紅花だって生きる為に盗んでいるんだから」
「もしかして紅花先生ってナトランを食べて生きてるの?」
「ナトランは食い物じゃないけど、まぁそう言う事だ」
「だったら僕のも少しだけだったら分けても良かったのに、あんなにお世話になったんだもの」
「お前って人がいいのも程度があるぞ、それにお前のナトランは盗まれてはいけない訳があるんだ」
「それって、僕のが特別って言ってた事なの?特別って何が特別なの」
「お前のナトランは並の人間と比べたら数十倍いや単位が違うな、なにしろ比べようもなく強力なんだ」
「僕はそんなに長生しなくてもいいよ」
「ナトランが強力って事は長生きする訳じゃ無いんだ、俺たちはお前のナトランが狙われないように長い間見守って来たんだ」
「僕にそんなに強いナトランがあったって何の価値があるの、それに監視されてたなんて嫌だな」昴はイライラして床板をちょっと蹴った。
「僕これからどうしらいいのかな」
「そうだな、まずそのシャツを洗うんだな」
昴は汚れたシャツを引っ張って見た。
「バスルームを貸してくれる、僕汗だらけで気持ち悪いんだ」
「お前なぁ、俺が猫だって事忘れてないか?猫が風呂を使う訳ないだろう」
そうだ、ブナは猫だったんだ。
ブナが余りに普通に会話するので、猫だと言う意識がすっかり消えていた。
あんなに怖いと思っていた猫とこんなに近くに居るなんて、昴は自分で驚いた。
「僕、ブナが猫でも大丈夫みたいだ」
「お前が猫嫌いでどんなに苦労した事か、猫が怖いなんて変な奴だよ」
「ごめんなさい、でももう大丈夫みたいだから猫の町に来たんだから慣れないと住めないものね」昴が言った。
「いい心がけだ、それだったら町の広場に泉があるから、そこで水を汲んでシャツを洗っておいで」ブナが言った。
「でも、ブナこの部屋を出る出口って何処なの?」
昴は部屋の中を歩きまわってドアが一つしか無い事を確認していた。
ただ一つのドアは昴たちが天井裏から入って来た木のドアだった。
「出口はそこに在るだろう」ブナは木のドアに視線を送って言った。
「でも、このドアは入って来たドアだよね」
「そうだけど、何か問題でも?」ブナはすました顔で言った。
またあの暗闇に戻ってから外に出るものだと納得して昴は仕方なくドアを開いた。
ドアを開いた瞬間に太陽の眩しい光に照らされて昴は思わず目を細めた。
窓の外に広がっていた鮮やかな青空がすぐ手の届く所にあった。
昴は背を低くしてドアをくぐりぬけて家の外に出る。
眼下には遺跡のような石積みの建築物が階段状に広がって濃い緑色の森のずっと先に青い水面がキラキラ光っている。
家々を囲む扇形をした石の道はまるで巨大な野球のスタンドのようだと昴は思った。
谷を切り開いて作ったゾハランの町はかりの大きさがあってブナが住んでいる石積みの建物と同じようなものが横並びだけでも二十件以上あり谷の下までの段数を数えたら五十段ありそうで、その大部分は壊れて朽ち果てていた。
ブナの家は階段の最上部に近い場所にあり、近くに或る石積みの家の中では崩れた部分が少ない建物だった。
谷の北側にはヤシの森がありその向こうに窓から見えていたうす茶色の殆ど木の生えていない岩山が見える。
階段状の住居の数は百もありそうなのに真夏の太陽の下で町は静まりかえり動く者の姿は見えない。
この場所が賑わいを見せていたのは遠い昔の事なのだろう。
今は何匹の猫が暮らしているのかは想像もつかなかった。
昴は谷に向かって階段を下り、眼下に見えた広場に着くまでに汗でびっしょりになっていた。
泉は広場の真ん中にあって木をくり抜いて作った桶が積み重なって置いてあった。
「その桶に水を入れるんだ」ブナが突然、現れて言った。
「ブナいつの間に来たの?」昴が家を出るまでブナはベッドの上で寝ていたはずだった。
「まぁな、泉の水を汚さないように使えよ」ブナは昴の問いを無視して言った。
昴はまず泉の水で喉を潤してからシャツを脱いで洗い、上半身を拭った。
泉の水はここち良く昴の喉と体を潤した。
「桶に水を二杯汲んで家まで運んでくれ」ブナが言った。
「えーっ、あの階段を桶を二つも持って上がれないよ」昴は膨れ面で言った。
「ちゃんとエレベーターが在るから心配するな」ブナは緑の目を細めて言った。
「もしかしてブナはエレベーターで来たの、始に教えてよ」昴は口を尖がらせた。
水がめいっぱい入った桶を両手に下げてブナの後について行くと昴が下って来た階段の脇にドーム型の入口があった。
太陽に遮られた建物の中はひんやりとして気持ちがいい。
中に入ると通路の壁にもたれて二匹の猫が座っていた。
白黒の模様の猫は顔の半分が斜に色が分かれていて体がとても大きい。
丸い顔の赤い毛のトラ猫は小がらで、脇腹に渦巻の模様が入っている。
二匹が座っている脇にはリュックのような形の草で編んだ籠が置いてあった。
二匹はブナの後ろに居る昴に気が付いて、驚いたように体を硬くしている。
「トゴ、マキ、ホンドラの実は沢山とれたかね」ブナが言った。
「ブナさんお帰りでしたか、ご苦労さまでした」赤い毛の猫が言った。
「ホンドラは良く実ってますよ、お連れの人はどなたです?」白黒の猫が言った。
「今夜、皆を集めて紹介するつもりだったが、昴と言うんだ、これからしばらくフレハラスで暮らすからトゴもマキもよろしく頼むよ」ブナが言った。
「ブナさんの頼みとあればもちろんです、ブナさんお帰りになったばかりでは新しいホンドラも無いでしょう良かったら一籠持って行って下さい」マキが言った。
「それは有難い、次に実を取りに行く時は昴も誘ってもらえるかね」ブナが言った。
「人間の力があればホンドラ取りもはかどります、是非に行きましょう」トゴは髭をピクピクさせて言った。
「ブナ、ホンドラって何なの?」昴が言った。
二匹の猫は昴が言葉を発したと同時に背中の毛を逆立て耳を伏せ後ずさりをした。
「驚かせて悪かったな、昴は話が出来るんだ」ブナが言った。
「人間が話せるなんて、こりゃぁ驚きました」トゴが言った。
「細かい話は集会の時にしょう」とブナが言って夜にまた会う約束をして二匹と別れた。
ホンドラの実の入った籠を背負い水の桶を両手に下げて、暗いジメジメした道を進むと水の流れる音がした。
幅の狭い水路が暗がりの中に流れている。
ブナは水路の始まりに在る丸い石の部分に乗るように言った。
二人が石の上に乗ると、石は水路を滑るように進みしばく突き当りの壁の手前で止まった。
ブナに促され壁の所にあった別の石に乗り換えると石は上へと持ち上がる。
「凄い仕掛けだね、水の力で出来たエレベーターなんだね」昴が言った。
「自然エネルギーって奴だな、古代の人間は大したものだな」ブナが言った。
「ここって、やっぱり古代遺跡なの?」
「そうらしいが、俺も詳しくは知らん」
エレベーターは暗がりを出て地上の光の中に上がった場所はブナの家すぐ側だった。
「昴、この丸い石はあちこちに在るから注意する事だな行き先は印を見れば想像できるが馴れないと思わない所へ出てしまう」ブナが言った。
丸い石は降りてしまえばただの敷石のように見えた、うっかり知らずに踏んだら大変だ。
昴はまた泉に行く時の為に石に刻んである模様をしっかりと見た。
|
11 月夜の集会
桶の水を台所のカメへ移し、ホンドラの実を布の上に開けて鞘から中身を取り出しバスケットに入れた。
鞘の中には猫のドライフードのような焦げ茶色の粒がびっしりと詰まっている。
味はブナに言わせるとチーズ入りのパンみたいだと言う。
昴も食べられるかどうか試してみた。
思ったよりも美味しい。
ホップコーンみたいな感じで、これだったら充分に食べられそうだった。
猫達はホンドラの実の他に森で狩をしたり、海に行って魚を取り新鮮なものはそのまま食べて、残りは人間に渡して干した魚と物々交換して貯蔵しておくと言う。
猫がどうやって、そんなに沢山の魚を獲るのかブナに聞いたが、ブナは「今に解るさ」と言っただけだった。
ブナが捕まえたネズミを食べる訳にもいかず、昼も夜もホンドラの実だけを食べ昴はうんざりしていた。
虫の声が高くなって丸い月が海の上に昇ると、ブナは昴を連れて遺跡の一番上まで上がった。
海から涼しい風が吹いて来て、気持ちの良い夜だった。
遺跡の上部は石積みのテラスのような場所があって、先に来ていた猫達が皆一定の距離を置いて草の影から目だけを光らせていた。
ブナは昴を後に従えて尾を高く上げて猫達の間をすり抜け、テラスの縁の少し高くなった場所に座った。
ブナの大きな黒い体が月の光に照らされて、堂々と見える。
「もう少し前に集まって」ブナの言葉に促されて、草むらに潜んでいた猫達がブナの周りに集まった。
五十匹以上の猫が昴を好奇心の目で見つめる。
猫に少しは馴れたと思った昴だが、この状況はやっぱり恐ろしい。
「うぉほぉん!!全員集まって居るようだな、それではまず皆さんも気になって居るこの人間を紹介しょう」昴はブナに促されテラスの縁に上がった。
「このお方は昴様と言います、しばらくフレハラスで暮らす事になりました皆に承諾なしで決めた事を不満に思う者も居だろうが、これは緊急事態だ」ブナは緑の目を見開いて言った。
「昴様は皆が見て解るようにクグル地区に住んでいる人間とは違う、猫の言葉を理解し話す事も出来る、見守り猫がバルク様の命令を受けて三世代もの永きに渡って見守って来た大事なお方じゃ、皆も心してお世話に努めるように」ブナが言い終わると猫達はいっせいにどよめいた。
猫達はバルク様と言う言葉と昴の体から立ち上がっている濃い色のナトランに驚いたようで、興奮はしばらく収まらなかった。
昴がテラスの縁から降りると側に居た猫は頭を下げて、後ずさりした。
昴を見つめる猫たちの目は、好奇から尊敬へと変わっていた。
ブナの話の後に、トゴ猫がテラスに上がって島の警備についての話をしていた。
その後に三毛猫が狩の報告と収穫場所について話した。
集会が終わるとブナの周りに四匹の猫が集まって、ひそひそ声で話しをしていた。
二匹は昼間出会ったトゴとマキで、ひときわ目を引く白に茶色のブチの入った長い毛が美しい猫がシオン、太った三毛猫はミスと言った。
猫達の態度からホンドラの町で重要な役目を担って居るのは、この四匹のように思えた。
帰り途に遺跡の上部を降りかかった時、草むらの中から二匹の仔猫が飛び出して来た。
「とうちゃん、何処へ行ってたのぉ」縞模様の仔猫はミャーミャーと鳴きながらブナに頭を擦り付けた。
岩陰から足の短いずんぐりした縞模様の猫が出て来て、ブナに言った。
「あら、お帰りだったのね〜」
ブナは雌猫の言葉を聞いて、慌てて走り寄った。
「昴、わ、わるいが先に帰ってくれ」ブナはそう言い残すと、しっぽを下げてトボトボと雌猫の後について行った。
いつも偉そうにしているブナが奥さんに叱られるのかと思うと昴は笑いをこらえるのに必死になった。
それから二日間後の事だった。
太陽がやっと顔を出した早朝に、トゴとマキがやって来た。
二匹とも上機嫌ではりきっている。
ブナに今日は魚獲りに海岸に行くと言われて、昴も笑顔になった。
フレハラスに来て海は始めてだった。
魚獲りの合間に泳げるだろうし、今日は楽しい一日になりそうだ。
海岸までは石のエレベーターに何回も乗り換えた。
フレハラスの島は地下に水路があちこちに繋がっていて、それを利用して移動出来る。
水の圧力を巧みに使い、登りも下りも移動する事が出来た。
エレベーターが地上に出ると潮の香りが強くした。
入江にはマングローブの木が生い茂り、赤い色の砂浜が弧を描いている。
濃い青色の海は地平線まで、何一つ遮る物がない。
昴はズボンの裾を織り上げて靴を脱いで、波打ち際まで走って行った。
足に伝わる砂の熱さが気持ちがいい。
猫達は、熱い砂が苦手なのか足を振りながら波打ち際までやって来た。
昴はズボンもシャツも脱ぎ棄て、白い波頭をかき分け胸まで海水に浸かる。
海の水は足の指が透けて見えるほど澄んで、冷たく気持ちがいい。
水平線に向かって思いっきり泳いでみる。
しばらく泳いで浜を振りかえると猫達の側に四人の人間が立っていた。
フレハラスに来て初めて見る人に昴は喜んで、浜に向かって泳ぎ始めた。
近づくに従って、人の様子ははっきりと見えて来た。
四人は欧米の人のようで黒人の男が一人、白人らしい男が二人と白人の髪の長い女が籠を抱えて立っていた。
昴は砂浜が近づくと困った事に気がついた。
どうしょう、女の人が居るのにパンツしか着けてない。
パンツが濡れて体に張り付いた姿を見せるなんて恥ずかし過ぎる。
「昴さっさと海から上がれ、魚とりを始めるぞ」ブナが言った。
「ブナお願いだから、女の人にちょっと後ろを向くように言って」
「まったく世話の焼けるヤツだな」
ブナは文句を言いながら伝えてくれたようで、女の人が後ろを向いた間に水から上がりシャツとズボンを慌てて着た。
「すみませんでした僕、昴と言いますよろしくお願いします」昴は男達に向かって言った。
男達は昴の顔を眺めるばかりで言葉に無反応だ。
「やっぱり日本語は通じないのかなNice to meet you. My name is Subaru」と言った。
人の良さそうな顔をした丸顔の黒人も太った白人の男もどこか目がうつろだ。
メガネの神経質そうな男は怯えたような顔で昴を見ている。
昴の頭の中に女性の声が飛び込んで来た。
「その人達は耳が聞こえないわ私はノア、話が出来る人間は珍しいわね」腰まで伸びた赤っぽい髪の少女が微笑んで立っていた。
たぶん年齢は十四、五歳ぐらいだろう。
少女は色褪せたシャツを着て腰の周りを布で巻いている。
すらりと伸びた手足は良く日焼けしていて、小動物を連想させる小さな顔には目ばかりが目立つ。
「初めまして僕、昴と言います」昴は声に出さずブナと話すように頭の中で会話した。
「スバル、変わった名前ね何処から来たの?」ノアは海のように青い瞳で昴を見つめて言った。
「僕、東京から来ました」
「トウキョウ?何処なの、フレハラスでは聞いた事が無いわ、貴方も船が難破して流れ着いたのね」
「船が難破したのですか?」
「話はそれぐらいにして、魚取りを始めるぞ」昴が言いかけた時に、ブナが強い調子で言った。
猫達は並んで波打ち際に座り海に向かって思念を送る。
「危ないぞ、危ないぞ、海の水は熱すぎる、跳ねて空に飛びあがれ、陸に上がって体を冷やせ」猫達は海に向かって同じ言葉を繰り返す。
波打ち際で海水に足を浸していた昴は急に海水が熱湯になったような気がして、慌てて浜辺に避難した。
猫達は尾をゆっくりと上下させながら一心に思念を送り続ける。
浜の近くの海面から魚が数匹飛び跳ねた。
見る間に沖の方で魚が銀色の体を見せてピョンピョンと海面から飛び跳ねる。
魚達は海面を飛びなから岸に向かって近づいて来る。
「危ないぞ、危ないぞ海の水は熱すぎる、跳ねて空に飛びあがれ、陸に上がって体を冷やせ」魚は猫達の言葉に操られ自ら砂浜に向かってジャンプした。
砂浜は次々に飛び込んで来た魚でいっぱいになった。 |
大量のカマスやハタに混じって小型のサメまでも砂浜を尾で叩いている。
ノアと男達は手際よく魚を種分して籠に入れた。
ずっしりと魚の入った籠を背負って、人間の住むクグル地区まで全員で運ぶ。
クグル地区に行くのには古代のエレベーターが無かったので、重たい籠を背負ってジャングルの道を一列になって進んだ。
猫達は何も持たずにシダの生い茂る森の中を軽快に進む。
昴は肩紐のツルが荷物の重みで肩に食い込んで辛かった。
ジャングルの蒸し暑さで息があがりもうダメだと思った時に前方の視界が開けてヤシの木で作った小屋が見えた。 |
 |
先に到着していた猫達の他に、黒人と白人の堂々とした体つきの女達と黒人の三人の子供が待ち構えていた。
女達はノアの後ろから歩いて来た昴を見つけて互いに顔を見合せて目配せをした。
子供たちは、ワァーワァーと言葉にならない叫び声をあげて嬉しそうに走り寄って来て、黒人の男の脚にまとわりついた。
黒人の男は、笑顔で籠の中の魚を見せる。
女達は籠を受とると、魚を数匹出してバナナの葉で包み焚き火の中に入れた。
「魚が焼けるまで、私の家でお茶を飲みましょう」ノアが言った。
ノアの家はヤシの木を支柱にして回りを葉で覆った簡単作りだが、中は涼しくて意外に快適だった。
猫達は待ち切れず、生の魚を美味しそうに食べて居る。
ノアと昴は土間に敷いたゴザの上で、ヤシの実の器に入った甘酸っぱいお茶を飲む。
「ここの方達は皆さん船が難破して島にたどり着いたんですか?」昴が言った。
「ここに住む大人は皆さっき漁をした砂浜に流れ着いた者ばかりよ私とトムの三人の子供たちは、この島で生まれたの」
「ノアの両親はどの人なの?」
「私の親は両方とも死んでしまったわ、お爺ちゃんは生きて居るけど」ノアは青い目に陰りを見せて言った。
「ノアは島から出た事が無いの?」
「昴!解っているな」ブナが不機嫌な声で言った。
ブナは、ここに来たいきさつを話さないように注意しのだとすぐに解って、昴はうなずいた。
「この島を出るなんて考えた事も無いのよ、だってあの海を超えるには危険があるでしょ、お爺さんが死んでしまったら私と話が出来る人間が居なくなってしまう、それは寂しいけどね」
「僕が居る間は話が出来るよ」昴は言った。
「そうね嬉しいわ、今日はお爺ちゃんの具合がいいみたいだから逢ってみない」ノアが言った。
どうしていいか返事に困って昴はブナを見た。
ブナが許可をしてくれたので、ノアの祖父と会うことになった。
ヤシの木の小屋の裏は山へと続く岩肌になっていて、無数の洞窟が口を開けていた。
殆どの人間はこの洞窟の中に住んでいると言う。
ノアは昴だけを伴って入口にシダの葉の飾りの在る洞窟に入って行った。
洞窟は入口の近くに石積みした場所があり焚き火の跡が残っていた。
入口から十メートルぐらい場所は何とか外の光で洞窟内の様子が見えたが、その先の道は二つに分かれ闇の中へと消えていた。
ノアは馴れた様子で左の道の暗闇の中へ入って行く。
昴も遅れないように後を追う。
天井から下がった岩に何度か頭をぶつけながらしばらく進むと前方にぼんやり明かりが見えた。
「お爺ちゃん起きている、ノアよ」
明かりの中に置かれたベッドから皺だらけ手が上がった。
「お爺ちゃん、具合はどう?今日は沢山魚が捕れたのよ後でホンドラの実と一緒に煮て持って来るわね」
ノアの言葉に老人は弱々しくうなづいた。
「ノア、その人は誰なんだ」老人は体を少し起こして昴を見た。
「この人はスバルと言ってブナと住んでいる人よ、言葉が話せるから連れて来たの」
「言葉が話せる人間じゃと、ブナは何処から連れて来たのじゃ」
「お爺さん、初めまして」昴は頭の中で言った。
「おお、本当に声が聞こえるぞ死ぬ前に人と話が出来るとは思っても居なかった、見たところ東洋人のようだが何処から来たのじゃ」
「僕は東京から来ました」
「トウキョウ、トウキョウ・・・・ああジャパンじゃな、あの海域もまた歪みが酷くなったものじゃ」老人が言った。
「あの、僕・・・解らない事だらけで、皆さんは何で言葉が話せないんでしょうか」
「スバル、君は船が漂流してここにたどり着いた訳では無いようだな、
あの海域を通った殆どの者は異常な音を聞いて耳が聞こえなくなってしまう、ワシもそうだった耳が聞こえなくなって何年も音の無い世界に暮らすうちに今は声さえも出なくなってしまった」
「変な事を聞いてすみませんが、皆さんはいったい何処の海域で遭難したのですか?」
「わしは千九百五十三年にマイアミを出港した貨物船に乗ってポルトガルのリスボンに行く途中にバミューダ島の近くで
暴風雨にあって船が転覆してこの島に流れ着いたのじゃ、あの暴風雨の中に聞こえた恐ろしい音は一生忘れられない、鼓膜だけでなく脳みそまでも揺すられるようなおぞましい音だった、わしは元々耳が少し悪かったのが幸いして脳みそは何とか無事じゃったが、音を聞いて頭をやられてしまった者が殆どじゃ」
マイアミ、バミューダから漂流したとすると、このフレハラスはどうやら北米大陸の西の大西洋上に在るらしい。
それが新宿の古いビルの天井裏と繋がって居るなんて、夢にしてもこんなバカバカしい事と昴は思った。
「お爺さんは、この島に五十年以上も暮らしているんですね」昴は言った。
「五十年か、それもそろそろ終わりじゃのお」老人は淡い色の瞳をしばだいた。
「お爺ちゃんそんな事、言わないで」ノアが言った
「ノア人間はいつか死ぬのじゃ昴、もし君がこの島から出られる時が着たらノアを連れて行ってくれないか」老人は皺だらけの手で昴の腕を掴んだ。
老人の手は冷たく、節くれだっている。
夢の中の約束でも、残り少ない命のを灯している人に気休めは出来ない。
昴は返事が出来ずにただ黙って立ちつくした。
|
12 ホンドラの森
フレハラスに来て二度目の満月の夜が過ぎた。
不思議の島に迷い込んだ昴は戸惑った事も多かったが自然に囲まれた島での生活に慣れるにしたがって楽しい事が増えて行った。
最近の一番の楽しみは滝での水遊びだった。
トマネ川の支流の岩場に十メートルほどの高さほどの滝があり、滝の上部から岩場を滑り台にして滝壺に向かって滑り込む、自然のウォタースライダーがある。
昴は滝の一番上からのスライダーは怖くて滑れないで、いつも冷やかされていた。
クグルの子供たちとノアは勇敢にも滝の上から滝壺に直接ダイブした。
昴はいくら冷やかされても、滝の上からのダイブは足が震えて無理だが滝の上部からのスライダーはいつの日か滑ろうと思っていた。
ブナの家も昴が暮らすようになって、随分と様変わりした。
掃除に手慣れた昴は、ブナの家の大掃除をして部屋の中を磨きあげた。
テーブルや床は本来の色を取り戻し、ベッドの干し草も清潔になった。
フレハラスでの暮らし方はノアから学ぶ事も多かった。
人間が食べられる果実や草の見分け方を教わったり、草で籠を編む事も覚えた。
ブナリの葉はすり潰すと良い香りの泡が出て石鹸の代わりに使える。
トトシミの葉は虫ささの痒みを鎮め、ソナチの葉は切り傷に貼っておくと治りが早かった。
魚やカエルの肉、パパイヤ、マンゴーやバナナなども手に入って食生活も豊かになった。
始めは灯りもなく不安だった夜も、ハウラ虫と言うホタルに似た虫を集めて灯にした。
ハウラ虫は、ライラ草の花の蜜を器に入れておけば自然に集まり集団を作って明るい灯になった。
昴は、太陽が東の空に上がり始めた早朝に目覚める事が多かった。
あたりが薄墨色になった夜明け前に目が覚める。
寝起きにハイビスカスを干して作ったお茶入れそれを持って家の外の石積みに座り明け始めた空を眺める。
遺跡を噴き上げる朝の風は冷たくここちが良い。
黒ぐろと見える森の上の雲が茜色に輝き、やがて太陽が金色の光を放つと虫の声に変わって鳥たちが朝のさえずりを始める。
ゆっくりと、空も森も色を得てその息を吹き返す。
昴は酸っぱいハイビスカスのお茶を喉に流し込みながら、一日の始まりを眺めるのが好きだった。
フレハラスは自分の心が自然に帰れる場所だった。
心が癒されるのを感じながらも昴は何度も考えた。
今ここに居る自分は夢の中で彷徨っているのか。
目覚めた時に自分は何処へ戻るのだろう。
うたた寝をしたBlue heavenの嵐の夜だろうか。
あの夜は優衣と会う約束をしていた。
黒目がちな瞳で見つめる優衣の姿を昴は思い返す度に昴の胸は熱くなった。
もしかしたら、優衣との出来事も昴が作りだした幻想なのか。
そうだ。
そうに、違いない。
家を出たのは全部が夢の中の出来事で、自分はまだ実家の布団の中かなんだ。
目を閉じると側で寝ていた辰哉の幼い寝息が今も近くに感じられる。
父さん、母さん辰哉も奈津美も今頃はどうして居るのだろう。
瞬間に夢の世界が壊れて、実家の布団の中に戻る。
汗で湿ったシーツの匂い、柔らかなタオルケットの感触。
台所から聞こえる包丁がまな板をたたく音。
そうだ、明日は数学の小テストの或る日だった。
昴は目をギッユと閉じて、ゆっくりと開く。
東の空は日の光があふれ森は色を取り戻し、朝の風にヤシの木が揺れている。
昴は浅いため息を漏らし残りのお茶を飲み干して、部屋の中に戻って行った。
朝の食事が終わり、ブナは丁寧に顔を洗っている。
ブナが耳の後ろまで丁寧に洗うのは何処かへ出かけるサインだった。
「ブナ今日は何処へ行くの」昴は言った。
「いや、ちょっとな」ブナは口を濁した。
ブナは住まいを別にしているが、奥さんと子供が居た。
ブナの言葉の中に歯切れが悪い物が混ざる時は、家族に関する事が多いようだった。
この黒猫は、家庭サービスなんて雄の威厳に関わるので秘密にしておきたいとでも考えているようだった。
それでも、奥さんには頭が上がらないのは隠しようがなかった。
昴はニヤニヤしてブナを見たがそれ以上は何も言わなかった。
ブナがそわそわと落ち着かない様子だったので、昴は気を利かせてトゴとマキを誘ってホンドラの実を採りに行く事にした。
待ち合わせの泉の前にはトゴとマキに加えて若い二匹の猫が来ていた。
ネズミ色の猫はグレイ、白黒の猫はブーツと言う。
白黒の猫は四本脚が全部黒くてまるでブーツを履いているようだった。
二匹は生まれて一年もたっていないような若い猫で、何をしても楽しそうで泉の側で飛び跳ねていた。
四匹と一人はそれぞれに草で編んだ籠を背負って水のエレベーターでトマネ川の上流まで行き、そこからジャングルを歩いてホンドラの森に到着した。
ホンドラの背の高い木が生茂った森は日の光を遮って涼しい。
木漏れ日が地面にレースのような影を落としている。
風がざわざわと葉を揺り森の中を吹きぬけて行く。
昴はマキと協力して地面に落ちたホンドラの実を集めた。
マキは気が小さい猫で何をするにも遠慮がちでいつも一匹では行動したがらない。
昴は二匹の若い猫にさえ気を使っているマキを自分と重ね合わせて何だか気の毒に思った。
トゴは森に入ってすぐに別行動で奥深く入って行って、帰った時には籠に山盛りの実を背負っていた。
若い二匹は見習い中の猫だそうで、ブーツはトゴの子供らしい。
ブーツの態度の大きい所は父親似かもしれない。
すばしっこいグレイとは良いコンビで、ホンドラの実の収穫も初めてにして手際が良かった。
それぞれが籠いっぱいの実を背負っての帰り道はジャングルを抜けるのには来た時よりも苦労をした。
グレイとブーツは先頭をきってシダの葉の間を進む。
若い二匹はまだ元気が余っているらしくシダの葉を揺らしてふざけ会いながら歩いている。
遅れがちに成るマキを助けてやっとジャングルの出口に近づいた時、シダの葉がムチのようにしなって勢いよくマキの目の前に現れた。
驚いたマキは籠を落として、ジャングルの中に走って隠れた。
グレイとブーツが悪戯をして、マキが通るのを狙ってシダの葉を曲げて離したらしい。
マキの慌てた様子を見てグレイとブーツは大笑いして喜んだ。
置き去りにされた籠からホンドラの実がこぼれていた。
トゴは目を三角にして怒った。
「大バカ者!!何て事をするんだ」トゴの大声に若い二匹は耳を伏せて縮みあがった。
トゴは二匹の頭に猫パンチをした。
グレイもブーツも尾を下げて後ずさりしてトゴのお説教をおとなしく聞いていた。
昴はマキが心配になってシダの葉の割れ目を頼りにジャングルの中を進んだ。
葉の折れた後を辿って行くと木の影にマキのオレンジ色の毛がちらっと見えた。
マキは藪の中に頭を突っ込んで、うさぎのような尻尾の付いたお尻だけを見せている。
「マキ大丈夫だよ、グレイとブーツが悪戯をしたんだ」昴が声を掛けると、オレンジ色の猫は藪から顔を出して恥ずかしそうに目をしょぼしょぼさせた。
「ごめんなさいオイラびっくりしちゃって、すぐ戻りますから」マキが言った。
「急がなくてもいいよ、少し休んでいこう」若い猫達が叱られているのでタイミングを外そうと思い昴が言った。
マキは気分を落ち着かせようと、胸の毛を舐めた。
昴はマキの側に腰を降ろして、シダの葉の先に見える青空を眺めた。
シュークリームのような形の雲が東の空にゆっくりと流れて行く。
「マキはこの島で生まれた猫なの?」昴が言った。
「いいえオイラもトゴも外から来たんです、この島で生まれた猫は六本指だからすぐ解りますよ」
「マキは元の場所に帰らないの」
「帰りたいとは思わないけど・・・でも皆どうして居るんだろうなぁオイラ何も言わずに出て来たから、お役目が終わったら帰るかも知れないし自分で決める事じゃないから」マキは遠い目をして言った。
昴はこの臆病な猫が、何の役目でこの島に来ているのか不思議に思った。
「昴さん、そろそろ戻りましょう」マキに言われて立ち上がった時、遠くでバリバリと聞きなれない音がした。
昴はつま先立ちになって、音のするジダの向こうを見た。
「マキあれは何だろう、遠くの木が凄い速さで大きくなっている」
「えっ、何ですって木が伸びている?オイラにも見せて下さい」
昴はマキを抱き上げて、ジダの葉の向こうの森を見せた。
マキは鋭い声で一声鳴いた。
昴の手に硬直したマキの体の震えが伝わる。
「大変だ森が成長している、逃げなきゃぁ!!」マキは叫んだ。
「マキ先に行ってトゴ達に知らせて」昴はマキを地面に降ろして言った。
「昴さんも早く逃げて、もし森に追いつかれたらしまったら地面の穴を見つけて入って下さい」オレンジ色の猫はそれだけ言うと、後ろ脚で地面を強く蹴ってシダの茂みの中に走り去った。
木々の向こうに遠く見えた森はどんどん昴の居る所に近づいて来る。
若い色をしいた木は瞬く間に成長し幹や葉の数を増やし天に向かって延びている。
成長をしている森からは空高く陽炎が立ちあがって周りの景色が歪んで見える。
恐ろしい音に追い立てられて昴もシダの茂みの中を全速力で走る。
空に逃れ飛び発った鳥たちが、けたたましい声で鳴いている。
森に住んでいる野ネズミが逃げ惑って、昴の足元を駆け抜けて行く。 |
青葉の匂いと異常な熱気が背後からどんどん迫って来る。
昴は頭を低くして、シダの葉をよけながらオレンジ色の猫が走り去った後を追う。
森が怒ったような凄まじい音は鳴りやまない。
昴が走っても、走っても森の成長は背後から追って来る。
機械のように意思だけで動かしていた足も限界になって棒きれのように痺れて昴は茂みの中に倒れ込んでしまった。
すり傷だらけの顔を拭って体を起しながら後ろを振り返ると、森の成長はすぐ近くまで迫っていた。
もう逃げられない、昴はマキに言われた事を思い出して地面の穴に逃げ込む覚悟を決めた。
目を凝らして、シダの根元を探してみる。
深く緑の生い茂った大地は、猫が入りこめる場所はあっても昴の体を隠してくれるような場所は見当たらなかった。
その間も森は容赦なく昴に迫って来る。
空気を震わす緑の陽炎は昴を飲みこんで行く。
成長した森からはちぎれた木の葉が雨のように降り注ぐ。
昴は背丈ほどの段差の在る場所を見つけ体を隠すように片側だけの |
 |
崖の背にへばりいた。
体を丸くして頭を手で覆った。
足元の雑草がフィルムを早回ししたように瞬く間に伸びて行く。
バリバリと木の擦れ合う凄まじい音がする。
昴は体から何かが吸い取られて行くような嫌な寒気がした。
熱風に包まれても昴の体はまるで冬山に居るように凍えていく。
強い風の音も昴には聞こえない。
昴の意識は白く輝く光の中に落ちて行った。
|
13 戻された体
温かな手が昴のほほに触れた。
静かな音楽が聞こえる。
「昴ったら、寝ちゃったの?」
昴はゆっくりと瞼を開く。
目の前には大きなスクリーンからエンドロールの文字がゆっくりと流れている。
昴は靄の中から抜け出たような気分でゆっくりと目を開いた。
隣のシートでは優衣がいたずらっぽい微笑みうかべ昴を見つめている。
「ごめんなさいね、映画つまらなかったんでしょ」昴は何も言えず優衣の横顔を見た。
「今日は台風が来たから朝から忙しかったよね」優衣が言う。
「あっ、そうですねそう言えば台風は」昴は戸惑いながら答える。
「台風は映画を見ている間にたぶん通り過ぎたわよ」
昴は優衣に話を合わせてみたが、頭の中は混乱していた。
フレハラスに居たはずがどうしてしまったんだろう。
ホンドラの森で森の成長に巻き込まれて、それから僕は。
昴は目の前の出来事に戸惑って呆然としていた。
エンドロールの文字が終わり音楽も止んで館内の照明が点いた。
映画館の中は人もまばらで、青い椅子の背が行儀よく並んでいる。
昴は優衣に続いて席を立ったが、映画館に入った記憶さえ無かったので出口の方向も解らなかった。
外に出ると嵐はすっかりおさまっていて、歩道には街路樹のプラタナスの葉やビニール袋の切れ端、壊れた傘までもが吹きだまりに転がっていた。
濡れた車道に派手なネオンの色が映って光っている。
「私、お腹空いちゃったわご飯食べに行きましょう」優衣は昴の返事も聞かずに腕を絡ませて行先をリードする。
賑やかな商店街を抜けて住宅地の細い路地へと入りこむ。
昴は最近流行りの住宅地の中にある一軒家のレストランかと思って看板を探す。
「優衣さん、隠れ家レストランですか」
「そうよ、とっておきの隠れ家レストランよ、あの白いタイル貼がそう」
指さす建物は五階建ての小ぢんまりとしたマンションだ。
優衣は馴れた様子でエレベーターを降り、五〇四号の部屋の前でバックから鍵を出した。
「優衣さん、ここって」
「いらっしゃいませ、カリスマ料理人の優衣です」優衣はおどけた口調で言って笑顔を見せた。
十帖ほどのワンルームは、可愛らしいインテリアで飾られている。
レースのカーテンには造花の花が縫い付けられていて花畑のようだ。
チェストの上には動物やキャラクターの人形ぎっしりと並んでいる。
白いラブチェアーにはパステルカラーの水玉模様のクッションが幾つも置いてある。
昴はクッションに埋もれるように座ってショートパンツの部屋着で料理を運ぶ優衣を眺めている。
白いテーブルには料理が次々と並ぶ。
サーモンのマリネにジャガイモのチーズ焼き、バジルのパスタはトマトソースの味がすばらしい。
昴は勧められるままに、慣れないワインを飲んで上機嫌になった。
優衣は食事が終わるとワイングラスを持って、ラブチェアーのクッションの間に身を滑り込ませた。
昴はクッションに挟まれて、優衣と体がぴったり寄り添っている。
むき出しの白い足が眩しく見える。
優衣はワインを一口飲むと昴の口元までワイングラスを運んで飲ませた。
黒目がちな瞳が間近で昴を見つめる。
優衣はゆっくりと瞼を閉じて昴に唇を重ねた。
温かく柔らかい唇は昴を包み込んで、溶かしてゆく。
昴は初めての口づけに全身を貫かれたように痺れていた。 |
優衣は昴の胸にもたれて体を預ける。
髪の甘い香りに包まれて昴は幸せに包まれる。
「さっきね映画館でうなされて何か言ってたわよ,悪い夢でも見たの?」優衣は優しい声で言った。
昴はフレハラスの事を思い出して体を硬くした。
「これ御守りよ悪い夢を見ないように、私がいつも昴と一緒に居る印、二人の秘密にしょうね」優衣は自分の胸に付けていた青い石の付いたペンダントを外して昴に付けた。
昴は頷いて、胸に掛ったペダントを握りしめた。
「凄く苦しそうだったよ、よっぽど怖い夢だったのね、どなん夢だっの?」
「僕、変な夢を見ちゃったんです、夢なのにまるで現実みたいに細かい事まで解っていてそれでも現実には在るわけ無い事だから、どう考えても夢だし」
「もったいぶらないで話してよ」
「聞いても、笑わないで下さいよ」
「笑わないから早く話して、聞きたいわ」優衣は甘えた口調で言った。
「僕、夢の中で不思議な島で暮らしていたんです、そこは話が出来る猫達や喋れない人間が居て。」
|
 |
「猫が話すの面白そうね、どうしてその島に行く事になっちゃったの」優衣が言った。
昴はフレハラスに行くきっかけになった嵐の夜を思い出して背筋が寒くなった。
紅花はあれからどうしたのだろう。
「そうだ、いけない遅くなってしまって紅花先生心配しているかな」
「あら、紅花先生は出かける時に今夜は台風でお客が来ないから早く寝るからって言ってたじゃない」優衣が言った。
昴はまったく記憶が無かった。
「そうでしたっけ、じゃあ大丈夫ですよね」
「それで、その島へはどうやって行ったの」
「それは、よく覚えてなくて」昴は紅花先生に追いかけられた事を言うのは悪口を言うようで話せなかった。
「苦しそうにしていたから、その島は怖い場所なのね」優衣が言った。
「いいえ、フレハラスは楽しい所ですよ、遺跡の町も自然もきれいだし滝の滑り台は最高でしたよ」
「島の名前はフレハラスって言うのね」優衣は目を輝かせて言った。
「猫の町はゾハラン、遺跡の中にあって島全体に水のエレベーターで移動出来るんです、凄いでしょ」
「猫と一緒に遊べるのね楽しそうな島ね、私の知って居る猫は住んでいたの」優衣は言った。
「紅花先生の所の黒猫のブナが僕と一緒に住んで居るんですよ」
「まぁ、あの無愛想な黒猫ねあの子も言葉を話すの」
「もちろんですよ、僕ブナから色々教えてもらって・・・・」昴は、はっとして息を飲んだ。
フレハラスに着いたその日に、ブナから言われた言葉が頭に響いた。
ここは秘密の場所なんだ、ここでの生活は人に話してはいけないとブナに言われた事を思い出した。
昴は喉が詰まったように、咳ばらいをして急に黙りこんだ。
「ブナはどんな事を教えてくれたの?」優衣はじっと昴を見つめて言った。
あれは夢なんだ、夢の中での約束なんて今目の前に居る大事な優衣とはまるで重さが違う、でも・・・・。
「どうしたの、貴方なんだか変よ」優衣は昴の顔を覗きこんだ。
優衣の瞳に昴はぐいぐいと惹かれていく。
魔法がかかったように、優衣から目が離せない。
「ねえ教えてよブナは何と言ったの?」
「ブナは、フレハラスは地図には無い南の海に或る島だと言いました」昴は優衣に導かれて話し出した。
「フレハラスへはどうやったら行けるのかしら」優衣の唇が動く。
「僕一人では、行けないんですブナと・・・・何か聞こえる」昴が言った。
遠くから高い音と低い音が不思議に混じりあったような歌美しい声が聞こえた。
昴がその声に耳を傾けると歌声は少しづつ大きく成る。
波の音のようなメロディ、温かく懐かしくそして悲しい女の声。
昴の目はなぜか、涙で濡れていた。
「昴どうしちゃったの?」優衣の声が遠くで聞こえる。
涙で滲んだ視界から優衣の顔がぼやけて見える。
自分を呼ぶ優衣の声が遠くなる。
心が歌声に同調するように胸の鼓動が速くなる。
歌声はどんどん高くなり昴は吸い込まれるように瞳を閉じた。
|
14 目覚め
透明な水の中に煌めく沢山の空気の泡。
昴の体は水の中をゆっくりと漂う。
澄んだ滝壺の水中は光にあふれて美しい。
火照った体を滝の水が癒してくれる。
優しい歌声は子守唄のように穏やかに聞こえる。
かすかな香りがした。
グレープフルーツとペパーミントを混ぜたような爽やかな香り。
香りはどんどんと増して鼻先をムズムズとくすぐる。
昴は耐え切れず小さなくしゃみをした。
「昴、気がついたな」ブナの声が頭に響く。
ブナ、マキ、トゴ、グレイ、ブーツ、トムとクグルの人達の姿も見える。
皆の目が昴を見つめている。
ブナの黒い顔がすぐ近くにあった。
耳を後ろに寄せて、髭をピクピク動かしている。
枕元にはビッシリと香草が敷き詰められて強い香りを放っている。
「僕、どうして・・・」
「昴、お前危ないところだった助かって良かった」ブナが珍しく優しく言った。
「昴さん、オイラ先に逃げたから心配で目を開けてくれて嬉しいです」赤く腫れた目をしたマキが鼻水をすすりながら言った。
昴は頭が重くはっきりとしない。
首を左右に振りながらベッドから体を起そうとするが、体は重く力が入らない。
昴が口を開こうとした時、ドアが勢いよく開いてノアが入って来た。
「昴、昴、助かったのね」ノアの声が頭の中に聞こえる。
形の良い唇からは漏れるのは、あぅ、あぅ、と言葉にはならない音。
ノアは昴の首に小麦色の腕を絡ませ頬を押し付けた。
亜麻色のウェーブした髪からココナッのような香りがした。
「もし、お前のナトランが普通の人間並みだったら助からなかっただろう」ブナが鼻をヒクヒクさせて言った。
「僕いったいどうしちゃたの、森の木がすごい勢いで大きくなって、それに巻き込まれたのは覚えているんだけど」
「珍しい事なんだが、この島では森の成長が暴走してしまう事があるんだ、成長が始まると森は生きる為の力を周りから奪おうとして根から水や養分を吸い上げるように、すべての物から貪欲に生きる力を奪ってしまうんだ」
「僕のナトランは盗られちゃたの」
「だいぶ吸い上げられたみたいだな」ブナは言った。
「じゃぁ、僕もう永く生きられないの?」昴は心配顔で言った。
「まぁ千年は無理だろうな、普通の人間並みには生きられるよ」
「あ〜良かった、夢の中の出来事だって解ってても寿命が短く成るのは嫌だからね」昴は頬をゆるませて言った。
ブナとマキは怪訝な顔して目配せをした事を昴は気がつかなかった。
「体力が戻るまでは寝ていた方がいいぞ」ブナが言った。
「僕は起たくても、まだ歩けないと思うよ」昴は言った。
「私が毎日来て、世話をするから心配しないで」ノアが静かに言った。
「ありがとう」それだけ言うと昴は優しい眠りに導かれて行った。
優衣の黒い瞳が近くで見つめているような気がした。
それでも昴の体は優衣の元へと帰れない。
手を伸ばしたら掴めそうなのに、伸ばした指は空を切るばかりだった。
暗闇の中で目覚めた昴はわずかに差し込む月明かりに自分の指先を見詰めていた。
ブナの部屋が薄ぼんやりと見える。
目覚めた場所はフレハラスだった。
本当の僕は優衣の部屋で眠ってたるのだろうか。
すり傷やあちこちにぶつけたらしい打撲した体の痛みや疲労感は現実のように昴を辛くさせる。
夢だから痛くないなんて嘘だと昴は思った。
今、目に映っているブナの家の細々とした様子も腹をゆっくり上下して眠っている黒猫の息づかいもすべて自分の作り出した夢の中の想像なのか。
この夢の世界は現実のようにあまりにも緻密だ。
フレハラスの夢は楽しいけれど、早く夢から覚めて優衣との時間を過ごしたいと切実に思った。
優衣の香りを思い出しながら、唇を指でなぞってみる。
昴は胸元で違和感を感じ触ってみるとペンダントが掛っていた。
優衣からもらった青い石の付いたペンダントだった。
悪い夢のお守りに優衣が掛けてくれたペンダントは二人がいつも一緒の約束だった。
次の満月が過ぎて昴はやっと日常の生活を取り戻した。
体のだるさも取れて体調はすっかり良くなったが、気持ちはいつも沈んでいた。
優衣に会いたい、そればかりを考えて昴は毎日を過ごした。
眠りに就く前には毎晩ペンダントを握りしめて、今夜こそは優衣の元に戻れますようにと願った。
元の世界へ続くブナの家のドアを、期待を込めて何度も開いてもみた。
何度開いても、紅花の部屋から辿った屋根裏の暗闇は現れずドアの外は輝くフレハラスの青空ばかりだった。
ペンダントは優衣の存在をいつも感じさせる大事な物だった。
優衣の元で早く目覚めたいと思う昴の願いは叶えられず数日が過ぎて行った。
風も止んで空が輝くように晴れた朝に、バナナとホンドラの実が入った籠を抱えてノアがやって来た。
「昴、具合どう?」色あせたシャツを着た亜麻色の髪の少女は白い歯を見せて笑った。
「ノアおはよう、体は随分良く成ったよ手足に力も入るようになったしもう大丈夫だよ」昴は手を振り回して元気をアピールした。
「そう、それだったら今日マレイアの岬まで一緒に行きましょう」
「マレイヤの岬って行った事が無いよ、遠いの?」
「そんなに遠くないし、途中まで滝のエレベーターに乗れるから大丈夫よ、とても綺麗なところだし磯で美味しいカニが獲れるから焼いてお昼に食べましょう」ノアは、持ってきたバナナを数本を籠に戻して言った。
滝のエレベーターに乗ってトマネ川の河口に出て、そこから湾沿いの道を南へ進む。
岬に囲まれた湾の中は穏やかで澄んで青い空が溶け込んでいるようだ。
ノアは昴の体力を気づかって、途中で何回も休みながら歩き蟹とりの時の話をして昴を笑わせる。
「蟹は磯の石の間に住んで居るから石をどけて蟹を探していたんだけど、見つけてもすばしっこく逃げちゃうのよ、それで
餌で釣り上げようって事になって棒の先に魚の肉を結わえて石の隙間に差し込んだら、上手に捕まえられるようになったの、でもある日蟹を追って、岩の割れ目に腹ばいになっていたら、私の髪の毛に蟹が食いついてね、それも二匹もよ、
私の髪の毛が餌の藻と似て食いついたみたい、それから蟹獲りの度に皆が私の髪の毛を欲しがるのよ、まっくハゲになりそうだわ」
昴はノアの髪を蟹が挟んだ様子を想像して大笑いした。
話しに夢中になって、湾沿いの道を進むと砂浜の道は上り坂に変わり見渡す限り背の低い草に覆われた草原に白い可憐な花がぽつぽつと咲いている。
ノアは昴に荷物を預けて、白い花をつんで茎を絡ませて首飾りを作った。
花の輪が完成するとノアは急に無口になってマレイヤの岬の突端へと急いだ。
真上に来た太陽に照らされて、水面が光っている。
岬の突端はテニスコートの半分ほどの広さになっていて、先は遮る物も無くストンと海に落ちている。
ノアが真っ直ぐに進んだ場所には木で作った古びた十字架が海に向かって建てられていた。
ノアは花の輪を十字架に掛けて、ひざまずいて手を合わせ長い時間微動だにしなかった。
そよ風が岬を渡り草原と少女の髪を揺らす。
濃い青色の空に浮かんだ白い雲がゆっくりと形を変える。
「ここは、お母さんとお父さんのお墓なの」ノアはぽつりと言った。
昴も草はらにしゃがんで手を合わせた。
二人は崖の淵に座りだまって海を眺めた。
ゆるやかに曲線を描いた湾の反対側に尖った岬が見える。 |
「あそこは嘆きの岬って呼ばれていて、フレハラスに流れ着いた者は故郷を思って岬の先端から海を見るのよ」ノアは目を太陽の光に細めながら言った。
「ねえ、この島から出る方法は無いの?」昴は言った。
「昔は森の木で船を造って海を渡ろうとした人が居たらしいけど、船は
海に出てもどう言う訳かこの島に戻って来てしまうの、真っ直ぐに進んで居たのにたどり着く場所はフレハラスなの、そんな事が何回もあって皆島を出るのは諦めたのよ」
「島の周りに強い海流が流れているのかな」昴が言った。
「海流のせいもあると思うけど、それだけじゃないみたい、島から出る、ただ一つの方法は嘆きの岬から海に飛び込む事よ」 |
 |
昴は湾の向こうに見える岬を見た。
茶色の岩に覆わた岬は、十階建てのビルぐらい高さはありそうで崖の下の岩場には白い波頭が踊っている。
「あんな所から飛びこんだら死んでしまうよ」昴は驚いて言った。
「そう、それで何人もの人が亡くなったわ、でも数人の人は海面に届く前に吸い込まれるように空中で消えて行ったの、それできっと違う場所に行ったんだと信じられているのよ」
昴は嘆きの岬を見つめてため息をついた。
「昴、貴方は飛び込んではだめよ」ノアは冗談のように軽く言ったが眼差しは真剣だった。
「さあ、お腹が空いたわね蟹を獲りに行くわよ、先に行っているからね」ノアはそう言うとマレイヤの岬の先端まで小走りに進み、青空の中にダイブして消えて行った。
水音がして昴が恐る恐る崖の下を覗くと瑠璃色の海面にノアの長い髪が広がって見えた。
ノアは大きく手を振って下の磯に来るように合図をする。
昴は荷物を持って岬の坂道を下る。
優しい歌声が海から聞こえる。
ノアが海中から嘆きの岬に向かって歌っている。
悲しく切ない歌声、昴を死の淵から呼び戻してくれた歌声。
昴はあの時の歌声がノアだったと知った。
昴を救って、その後も細々とした処まで手の届く看病をしてくれたのもノアだった。
昴はもう一度お礼を言おうと、磯に向かう道を急いだ。
砂浜に入る前の草原に、青い小さな花が藪の中に隠れるように咲いていた。
青いビーズが房のように付いた花でといても可愛らしい。
あ、この花は・・・・
台風が来た午後のフェアリーローズの前での光景が思い出された。
あの日に優衣さんが店の前で片づけていた鉢の花と同じだ。
昴は思わず花を数本摘んで、籠の中へ入れた。
岩場を抜けて、波打ち際の磯にたどり着くと、ノアが岩の割れ目に腹ばいになって蟹獲りの真っ最中だった。
岩の狭い隙間にノアの抜いた髪の毛が数本束になって下がっている。
手に持った長い髪の毛をゆっくりと引き上げると爪が十センチもある大きな蟹が吊りあがって来た。
餌も付いていない髪の毛で蟹が吊れる様が可笑しくて昴は肩を揺らして笑った。
ノアは吊りあがった蟹を素早くつる草に巻いて数珠繋ぎにする。
「どう、随分獲れたでしょ火を起こして焼いて食べましょう」ノアは得意そうに言った。
「ノア君の髪の毛は大したもんだよ」昴は笑いながら言った。
美味しい蟹で二人とも満腹になった。
西の岬に太陽が傾き始めたので、二人は帰り仕度を始めた。
沢山獲った蟹はクグルの皆へのお土産だ。
蟹を籠に入れようとしたノアの手が止った。
「昴、この花はどうしたの?」険しい顔つきでノアが言った。
「綺麗な花だろう、砂浜の手前の藪の中で見つけたんだよ」
ノアは籠に入っていた布で花を包み急いで海の中に放り投げた。
「どうしたの、その花に毒でも入っていたの?」昴は言った。
「この花はナトランを吸う危険な花なのよ、そばに近づいたらダメよ」
「エッ、本当にそうなの?僕が住んでいた町では花屋で売っていたけど」昴は言った。
「それって違う花じゃないの、このホスマの花は島のピンクサンドの土でないと育たない花よ、フレハラスでも咲いているのはこの浜辺の近くだけ、私は外の世界へは行った事が無いから断言は出来ないけど、お爺ちゃんもクグルの人も外で見た人は居なかったわ」
昴はノアを見つめながら、頭ではあの日の優衣を思い起こしていた。
花の鉢を持ったエプロン姿の優衣。
プラスチックの鉢の中には青いビーズのような可憐な花。
根元の土は、桃色だったような気がした。
でも、きっと僕の思い違いだ。
そんな危険な花が花屋で売って居る訳がない。
ああ、そうか、そうだった。
僕は今、夢の中のフレハラスに居るんだった。
優衣さんの事ばかり考えているから、あの日の花が夢に出て来たんだ。
昴は納得して照れくさそうにノアの顔を見た。

|
15 嵐の後
台風の去った新宿の街は朝からぬけるような青空だった。
ビルの隙間から差し込んだ朝日を背にして紅花は納戸の中で仁王立ちをしていた。
タンポポ色の髪の毛は爆発したようにめちゃめちゃに乱れ血のけの無い顔に眼だけがギラギラとしている。
まったく忌々しい、あの小僧はいったい何処へ行ったんだ。
昴がスチール棚で塞いだ納戸の扉をやっとこじ開けたのは夜明けだった。
納戸の中は台風の最中に開けられたままになった窓から雨と風が吹き込んで酷い有様だった。
横倒しになったスチールの棚から落ちた本や新聞紙が部屋じゅうに散乱して床や壁にぬれ落ち葉のようへばり付いている。
窓際のダンボール箱は水を吸ってひしゃげて中の衣類も全滅のようだ。
壁際に積み上げてあったダンボール箱は一部が崩れ落ちて中身の古い料証書の束を床に吐き出していた。
もう一歩の所だったのに、怯えやっがって。
窓から飛び降りて逃げたならこの高さだ、足ぐらいくじいだろう。
まだそう遠くに行っていないはずだ。
マリアの所に行ったのかもしれない。
とにかく青姫様に知られる前に昴を連れ戻さなくては大変な事に成る。
携帯電話をポケットから出して開いた時、玄関のチャイムが鳴って紅花の体はビクッと震えた。
胸騒ぎがして背中に冷たい悪寒が走る。
玄関の外には青姫が居るような確かな予感がする。
青姫の怒りの波動が紅花の胸を締め付ける。
紅花は玄関まで小走りで進み、ドアホーンのモニターを見て息を飲んだ。
モニターには百合の花束を抱えた優衣が上目使いでこちらを見ている。
紅花は黙ってドアを開いた。
「お待たせいしまた、ご注文の花をお持ちしました」優衣はそう言って微笑むと紅花を追い越してつかつかと占い部屋に入って行った。
紅花は優衣を追って占い部屋に入る。
背中を見せて立っている優衣を紅花は青ざめた顔で見つめる。
永い沈黙の後、優衣はいきなり紅花と向き合って手に持っている百合の花束を紅花の顔にめがけて振り下ろした。
紅花の頬に当たった百合の白い花弁が宙に舞って床に落ちた。
紅花よろめき、恐怖で目を見開いた。
優衣は攻撃の手を休めず何度も何度も花束を振り下ろす。
散乱した花弁や葉の上に力無く紅花が座り込む。
百合の黄色い花粉が紅花の顔や紫色のドレスにまだら模様を付ける。
「青姫様お許し下さい」紅花はうめくような声で言った。
「お前は、何を許せと言うのか」優衣は頬笑みを浮かべなから冷たい声で言った。
小柄で儚げな少女の外見から創造できない、憎悪に満ちたパワーが体から立ち昇っている。
「昴のナトランをもう少しで採れるところだったんです、でも怖気づいて逃げてしまって、きっと遠くには行っていません大丈夫です必ず連れ戻します」
「手出しはするなと言ったはずだよ。お前、昴のナトランを独り占めしょうとしただろう」
「そんな、滅相もございません、ちょうど良いチャンスだったのでナトランをごっそり奪って青姫さまにお渡ししょうと、
あっ!」
優衣は紅花の腹を強く蹴りあげた。
腹を押さえてうずくまった紅花の背を怒りにまかせて、強く蹴り続ける。
紅花は抵抗する事も出来ず、優衣の怒りが収まるのを体を丸めてじっと待つ。
優衣は百合が活けてあった大きな花瓶から花を引き抜いて床に打ち捨てる。
「お前は百合の香りなんぞ嗅いで良い気持ちになるなんて許さないよ」優衣は憎々しく言う。
紅花の襟を掴んで引きずり占いに使っている奇妙な動物の木彫付いた革張りの椅子に掛けさせ、ビニールのロープで椅子ごと縛りあげる。
急ぎ足で玄関に戻るとドアを開いて、廊下に置いてあった台車を引き入れる。
紅花は台車の荷物を見て、ヒィと悲鳴をあげた。
台車にはピンク色の砂に植えられた、青いビーズのようなホスマの花の鉢が三十ほど乗っている。
優衣はホスマの鉢を占いのテーブルや椅子の下に紅花を囲む位置に置いた。 |
「青姫様、お願いです。もう一度チャンスを下さい、きっと昴を連れ戻して来ますから」紅花は顔を歪ませて懇願する。
「連れ戻す・・・・もちろんじゃない」優衣は口角を引き攣らせて笑った。
「こんなに沢山のホスマの花の側に居たら私のナトランはすべて吸われてしまいす、何でもしますお願いです」
「そうよ、何でもしてもらうわ。当然よ、お前の仕出かした事はお前が責を持つのよ」
「でも、死んでしまってはお役に立てません」紅花は激しく震えながら言った。
「死ぬなんて、そんな簡単な事で許しはしないよ、昴は今何処に居ると思う?」
「たぶん、マリアのマンションか実家に帰ったのだと思います」
優衣は紅花の黄色の髪の毛を掴んで引っ張った。
「フン、昴はねお前の猫がフレハラスに逃がしたのさ」優衣は燃えるような眼で紅花を睨んで言った。
「猫、猫ってブナが逃がしたってそんな事、それにフレハラスって何処ですか」 |
 |
「お前は自分の猫に監視されてた大バカ者だよ」
優衣は占いのテーブルの上の銀の箱から色とりどりの光る小石を一握り取り出しテーブルに投げた。
小石はテーブルの上で波紋を作り中心から黒々とした穴が空いたようなスクリーンが現れだんだんと色を増して石造りの部屋を映し出した。
優衣はスクリーに手をかざして遠隔カメラを操るように映し出される景色を移動した。
窓際の出窓の上で黒猫が顔を洗っている。
黒猫はブナにとてもよく似ている。
窓の外は濃い青空をバックにヤシの木の森が広がり遠くに奇妙な形の岩山が見える。
「昴は起きているようだな、今は夢に入り込むのは無理のようだ」優衣がチッと舌を鳴らした。
「ねえブナ今日は、何処にも行かないの」突然昴の声が聞こえた。
「ああ、明け方まで狩りで森に居たから出かけるつもりは無いよ」
黒猫の言葉が頭に伝わって紅花は驚いた。
ブナが喋るっている。
音声では無い言葉を操る猫、南国のような景色の場所。
紅花は混乱する頭で、くいいるようにテーブルに浮かんだスクリーンを見つめた。
床に打ち捨てられ百合の花が腐ってひどい匂いを放っている。
紅花は薄目を開けてため息をついた。
椅子に縛られて昼と夜が三度過ぎ四度目の朝が開けたところだった。
後何日生きられるだろう。
今は手も足も痺れて感覚が無い。
紅花の椅子を囲んで置かれたホスマの花はナトランを吸って青いビーズのような花を紫色に変えている。
ホスマの花が血のように赤くなる時、自分の命は果てるのだろう。
もしかしたら、マリアが偶然に来てくれれば自分は助かるかもしれない。
いや、青姫が手抜かりをするはずが無い。
誰も来ないように策をめぐらしているに違いない。
「もう十分に生きたのだから」紅花は自分に言い聞かせた。
紅花は半世紀前に生を受け、子供の頃より僅かな予知能力があった。
その能力を生かし祈祷師になった紅花は戦国の世で戦いの未来を占う影の存在として安濃の武将の元に仕えた。
武将の側室だった青姫に永遠の命を授けると言われ、紅花は青姫に忠誠を誓った。
青の組織に自分が入った事は後になって知らされた。
紅花は半世紀の間、時の中に紛れ組織の為、青姫の為そして自分の命を永らえる為にナトランを奪ってきた。
紅花が一度に奪うナトランは微量で人の命を奪うような事はなく、罪悪感は持たなかった。
青の組織が何なのか実態も目的も知らず集めたナトランを石に封じ込め青姫に貢いでいた。
ある日突然に青姫の姿は変わる。
初めは、まったく違う若い女性に変わる青姫に驚き戸惑う事はあったが、今ではそれにも慣れてしまった。
自分は平穏な生活のまま、永遠に続く命があると思っていた。
ふらりと現れて、偶然のように住み着いた黒猫に監視されていたなんて、紅花には今でも信じがたい事だった。
青の組織を監視するブナはいったい何者なのだろう。
生命の元となるナトランの存在を組織以外の人間、まして猫が知っているなんて。
ブナもナトランを集めているのだろうか。
昔のように、明日を見渡す力があれば失敗は無かったはずだった。
紅花は予知の力を呼び起こそうと懸命に意識を集中させたが、未来を感じる力は遠の昔に消えていた。
後数日で、紅花の肉体は消えてしまうだろう。
青姫は「お前のナトランを体から引っ剥がしてフレハラスに送ってやる」と言った。
肉体が無くなったら自分はどうなってしまうのだろう。
青姫の命令に従って昴を連れ戻さないと自分は安らかな死さえ迎えられないのか。
紅花は益々赤みを増すホスマの花を見て唇を噛みしめた。
|
16 盗まれた髪飾り
冷たい水が足元を撫ぜて岩肌を駆け抜けて行く。
昴はしっかり足を踏ん張って流されないように身構える。
サムが滝に続く狭い流れの前に立って親指を立てて笑いかける。
先に滑り下りたノアは、滝つぼの深い緑色の水に亜麻色の髪の毛を広げ泳ぎながら、こちらに向かって手高く振っている。
サムが雄叫びをあげながらトマトマの滝に出来た天然のウォータースライダーを滑り下りて行く。
サムの体は水しぶきの中に見え隠れしながら下り、急流の終着点の滝つぼにジャブンとほうり出され水の中に消えた。
昴が心配して滝つぼの水面を見ているとノアの隣に白い波を立てて勢い良くサムが浮き上がった。
岩場で見ていたサムの弟のロイとウィルが歓声を上げた。
次は昴の番だ。
「流れに身を任せて、横を向かないように足先を落ちる方向に向けるのよ。昴、頑張ってね」ノアがメッセージを送って来る。
ひんやりした水に腰を沈め、足を滝つぼに向けて座る。
滝の横に出来たビルの三階ほどの高さの谷は上から見ると恐ろしく高い。
怖気づいてためらう昴にサムの兄弟達が指笛ではやし立てる。
「イチ、ニ、サン!」昴は大声で叫びながら支えていた手を離し急流に身を任せた。
体は急流にもみくちゃになり、白い水の泡が視界に現れては消え流れて行く。
初めは慌てて水を飲んだ昴も途中からスリルを楽しむ余裕が出来た。
流れに身を任せてしまえば、水のチューブの中を滑り下りるような楽しさがあった。
岩の滑り台は滝つぼの手前で急角度に変わり、昴は勢い良く滝つぼに落ちた。
滝つぼの底は、深い緑色の世界が広がっている。
水流に逆らって手と足を目いっぱい動かし体を反転して暗い水底の世界から逃れて水面を目指す。
水を通して頭上で輝く太陽の光。
透明な水の中に煌めいて広がってゆく空気の泡。
澄んだ滝壺の水はまばゆい光にあふれている。
力強く水を蹴って、水面に顔を出す。
滝を覆うように茂った木々の間から見える青空。
ノアとサム、ロイ、ウィルの笑い声。
「昴ずいぶん上手になったわね」ノアが乱れた髪を髪飾りで止め直しながら言う。
「緊張するけど、こんなに楽しい滑り台はないよ」昴はいっぱいの笑顔をかえす。
「ねえ、今度は滝の上から飛び込んでみない?」
「僕まだそんな勇気ないよ」
「あら、昴ったら怖がりね、気持ちいいわよ」ノアはそう言って身振り手振りで、サム達兄弟に滝の上から飛び込もうと伝えた。
フレハラスで生まれた難破船の遭難者トムの子供達三人は、耳は聞こえるが言葉を知らない。
ノアのように頭の中に語りかける事も出来ないので、彼らの間では手話のような動きとウォ、ホォウなど鳴き声のような音で独特のコミュニケーションをしている。
四人は昴を残してスルスルと岩場を登り滝の上部に出る。
滝を覆うように茂った木々の間から木漏れ日が落ちて四人の体にまだら模様の影を作っている。
末っ子のウィルが体をクニャクニャさせて変なダンスのような仕草で昴を挑発している。
ウィルは五、六歳ぐらいでチョコレート色の体に長い手足、大きな良く動く目が小猿のような明るいお調子者の子供だ。
サムが長男らしい落ち着いた態度でロイの頭を撫ぜて後ろに押しやって前に出た。
サムは昴よりも三、四歳は年下かもしれない。
サムが弟達とふざけ会ったり、いたわったりしている姿を見ると、今は遠く離れてしまった辰哉と奈津美を思い出してしまう。
昴の思いはトマトマの滝を離れ、なつかしい故郷を見ていた。
急なコンクリートの階段を登ると見える濃い緑の木々の中に埋もれそうな赤い小さな屋根の懐かしい家。
焼けた畳の色、昴の部屋から少しだけ見える海。
台所から立ち昇る香ばしい匂い。
父さんは、母さんは・・・・
あの日に偶然聞いてしまった、父と母の言葉。
自分が養子だったなんて、それも引き取ったのはお金が目当で。
そして、また実の両親にお金を要求するなんて。
母が言った「あの子は喜んで手伝ってたくれたのよ、扱い易い子だから」
家政婦代わりに使った子、何度思い出しても昴の心は縮んで痛みを感じる。
昴は日光に照らされた暑い岩場の上でブルっと身震いした。
現実に戻って再び滝の上に目を向けるとノアとサムの達兄弟が首を反らして頭上を見上げて立っている。
サムは木の枝を手に持って空中に振り回している。
何をしているのだろうと思った瞬間、バサバサと空を切る羽音がして、滝を囲む木々の間から桃色のとてつもなく大きな鳥が現れノアに向かって急降下して襲いかかった。
ノアは急いで身を低くしたが、鳥はノアの頭を突いてあっと言う間に飛び去って行った。
「ノア、大丈夫なの怪我はないの、ノア」昴は声に出して呼びかける。
ノアはしゃがみ込んで動かない。
ウィルは大声で泣き、サムとロイは放心したように頭上を見ている。
昴は急いで、岩場を駆け上がり四人の元に駆けつけた。
「ノア、ノア」昴は震えているノアの肩を抱いた。
岩場には引き抜かれたノアの髪の毛と桃色の鳥の羽根が一枚落ちている。
ノアは肩で荒く息をして昴の胸に顔を埋める。
昴は優しく髪を撫ぜながらノアを抱きしめる。
ノアの乱れた髪から髪飾りが無くなった事に気がついて昴が言った。
「ノア髪飾りはどうしたの?」
ノアはビクンとして顔を上げて、髪の毛を探った。
「キラブルが、キラブルが盗んで行ったんだわ」ノアは泣きそうな顔で言った。
「キラブルって、さっきの大きな鳥の事」
「キラブルは光る物が好きだから私の髪飾りについてる緑の石を狙ったんだわ、どうしょう取り戻さないとママの使っていた大事な髪飾りなの」
「お母さんの大事な形見なんだね、絶対に取り返さなくちゃ」
「キラブルの巣が西の岬にあるの、私行ってみるわ」
「僕も一緒に行くよ」昴は勢い込んで言った。
トマトマの滝と西の岬は島を挟んで反対側の位置にある。
途中までは水のエレベーターで行けるがそこから先は歩きになる。
「今から行けば午後過ぎには着くわ、キラブルは日が暮れると巣から離れないから急がないと」ノアが言った。
西の岬までは遠出になるし、キラブルの巣に近づくのは危険があるので小さい子供は連れて行けない。
どうしても行きたいと言うロイとウィルをやっとなだめて、サムとノア、昴の三人が西の岬に向かった。
トマネ川の上流まで行き、そこからジャングルを歩いてホンドラの森に到着した頃には太陽が真上に来ていた、ホンドラの実を拾って昼食代わりに少し食べた。
ここから西の岬へ続く道は昴にとっては初めての場所だった。
昴は、森の木が風でザワザワと音を立てる度に森の成長に襲われた記憶が蘇って嫌な気分がした。
背丈ほどもあるシダの葉をかき分けて西を目指して森を進む。
三人は鞭のように跳ね返るシダの葉で顔や手足に切り傷を作りながらも口を真一文字に結んで前だけを見て歩いた。
途中、トムが蔦に足をとられて転んだ時に手をついて右の手首を痛めてしまった。
森を抜けるのに思ったより時間がかかって西の岬にたどり着いた時は、太陽が低く成りかかっていた。
トムが「ホーホォゥ」と言って崖を指さす。
海面から垂直に近い切り立った岩場が西日に照らされて影を長くしている。
サムの示した位置に目を凝すと岩が窪んだ場所がありそこから藁のような固まりが少し見える。
昴はあまりの高さに、ごくりと唾を飲み込んだ。
「登って巣の中を見て来るわ」ノアが言った。
「キラブルが戻って来たら一人じゃ危ないから僕も行くよ」覚悟を決めて昴が言った。
手首を痛めたサムは見張り役で残る事になった。
風と波で風化した花崗岩のざらざらした岩の凹みに慎重に足を掛けて一歩ずつ上に登る。
ノアが登った場所を頼りに手と足を蜘蛛のように開いて体を押し上げる。
崖を吹き上げる風が駆け抜けて首筋を撫ぜて行く。
頭上を登っているノアが昴の顔を覗き込んで目をクリクリさせて悪戯っぽい顔で言った。
「絶対に下を見てはダメよ」
ノアは平気らしいが昴には崖登りは大冒険だ。
昴は目の前の岩だけを見て気持ちを落ち着かせる。
こんな厳しい場所にも岩の割れ目に根を張って小さな花が咲いている。
昴は花に手を伸ばそうとして、バランスを崩し慌てて下を見てしまった。
足が掛った僅かな岩の窪みの遥か下には濃紺の海が見えた。
余りの高さに体から全身の血液が一瞬でなくなったような感じがた。
昴は、足も手もガタガタと震えて目を強くつぶって岩にしがみついた。
「もう少しよ、頑張って」その時ノアが昴の手首を掴んだ。
上を見るとノアはキラブルの巣のある岩のテーブルに着いていて、そこから手を伸ばしてくれていた。
「助かったよ、ありがとう」昴は腕を最上部の岩に乗せ力を振り絞って体を引き上げた。
巣から続いた岩はキラブルの排泄物で白く変色して酷い匂いがする。
排泄物を踏まないように進むと、つい立のような岩と岩の間に守られた場所にキラブルの巨大な巣が姿を現した。
キラブルの巣の外側は植物と泥が混じった物で外側が固められている。
入口だけでも六畳はありそうな広さの巣の内側は深く傾斜のついた横穴のようになっていて、奥の場所はシダの枯葉やキラブルの桃色の胸毛が敷れた柔らかなベッドになっている。
ノアが巣のフチに手を掛けて中を覗きこんだが、入口からは小さな髪飾りは見えそうにもない。
キラブルが髪飾りを巣に持ち込んだのなら奥の方に置いてあるに違いない。
ノアはためらいもなく巣の中に入って奥に向かって歩いて行く。
昴が巣の上に登った時サム鋭い声がした。 |
「大変、キラブルが帰って来たわ」ノアが言った。
振り返って見るとグライダーのように大きく羽根を広げたキラブルが空の上で円を描いて回っている。
「早く下りて岩の陰に隠れよう」昴が言った。
「待って、奥の方で何か光る物が見えたの髪飾りかもしれない」
「そんな事言ってる場合じゃ無いよ、まず隠れよう」
「でも、今を逃したらキラブルが警戒して巣に近づけないから」
「ノア危ないから」
昴とノアが言い争いをしている間にキラブルは円を描きながらだんだんと高度を下げて迫って来る。
昴はノアの手を強引に掴んで、巣の入り口まで引き戻した。
ギャーオゥと鋭い声とともに風を切る羽音がして昴はとっさに体を伏せた。
キラブルは羽ばたいて空中でホバーリングしながら近距離で昴達を睨んでいる。
テニスボールより大きな淡い水色の目が鋭い眼光で睨んでいる。
鋭い爪と大きなクチバシの中に並んだとがったナイフのような歯にふれたら一瞬で肉は引き裂さかれてしまう。 |
 |
桃色の鳥は頭を下げて、再び二人に向かって突っ込んで来た。
昴はとっさに、ノアを巣の淵に突き飛ばし自分はキラブルの攻撃から少しでも逃れようと横に飛んだ。
キラブルは昴だけに攻撃の標準を合わせた。
キラブルは着地して昴に向かってギャア、ギャアと鳴きながらクチバシを伸ばす。
頭の毛が逆立って、先の長いクチバシが迫って来る。
肩に鈍い痛みがはしって、昴は飛ばされ巣の奥に転がり落ちた。
キラブルは益々怒り狂って鳴きわめき羽根をバタつかせ頭を左右に振りながら昴を突こうと懸命になる。
昴は枯葉のベッドに潜り込んで体を隠す。
ドスドスと枯葉を突くキラブルを避けながら巣の奥まで腹這いになりながら進むと、綺麗に整えられた枯葉の窪みに萌黄色の三個の卵が寄り添うように置かれていた。
もしかしたら卵の影に隠れたらキラブルは攻撃して来ないかもしれない。
昴は思いついて、自分の背丈の半分ほどの三個の卵の中心に体を滑りこませた。
キラブルの攻撃が一瞬止まった。
思ったとおり、自分の卵には攻撃はしてこない。
昴はほっとして腰を落とそうした時に三個の卵の中心にもう一つ違う卵があるのを見つけた。
「何て綺麗なんだ」昴は思わず呟いた。
四番目の卵は萌黄色の卵の半分ほどの大きさで虹色の縞模様が全体に入っている。
入口から奥まったほの暗い場所にも関わらず虹色の卵は発光しているかのように、ぼんやりとした光が卵を包んでいる。
昴は思わず卵に手を伸ばし触れてみた。
卵はひんやりとした無機質な感じで、まるで生命を感じない。
拳で叩いてみても中が空洞のようには思えなくて本物の卵じゃないと昴は思った。
これもキラブルの収集物かも知れない。
束の間攻撃を休んでいたキラブルが凄まじい声で鳴きわめいて、卵の周りを手あたり次第ドスドスと突き始めた。
昴は卵の中心で息を殺してしゃがみ込んだ。
「昴、聞こえる」ノアの声が頭の中に飛び込んだ。
「ああ聞こえるよ、キラブルの卵の影に隠れているよ」
「無事だったのね、良かった怪我は無いの」
「大丈夫だよ、でもここからどうやって出たらいいのかな」
「私キラブルの巣の裏側に居るの、さっきキラブルが巣を突いた時に穴が出来たのよ、たぶんそこから遠くないと思うんだけど」
「私が穴から棒を出して場所を教えるから、そこから降りて来て」
「解った、キラブルに見つからないように注意して」昴は言った。
キラブルは怒り狂って巣穴の中で羽ばたきながら鳴いている。
昴は枯葉のベッドの間から木の枝が動いているのを見つけた。
枝の出た場所から僅かな光が洩れている。
昴は枯葉をかき分けの穴の中に潜り込んだ。
穴に体を沈め足先が空を切って下に落ちかけた時、足の裏に柔らかい物を感じた。
「昴、サムの肩に足が乗っているのよ。大丈夫だからそのまま降りて」
サムの腕が昴の太股をしっかり掴む。
ゆっくりと岩場の上に降ろされる。
三人は、キラブルが巣の中で暴れている間に崖を降りた。
ジャングルを抜けて、ホンドラの森に着いた時は夜もふけて月が東の空高く登っていた。
みんな、口も開けないほど疲れていた。
|
17 君に眠るもの
ホンドラの森の入り口にブナとマキ、サムの父親トムが迎えに来ていた。
先に帰ったロイとウィルから話を聞いたのだろう。
サムとノアはトムからこっ酷く叱られて、しょんぼりと帰って行った。
ブナは耳を低くして不機嫌な顔をしているが昴には何も言わなかった。
ブナの機嫌の悪さは、全身から滲み出ていてキラブルの巣での出来事を話したかったが、とてもそんな雰囲気になれない。
この黒猫は仲良くなった今でも気軽な仲間ではなくて目上の教師のような存在だった。
ブナの顔を見ているのも辛いので昴は帰って早々に床についが、疲れ過ぎたせいで崖から真っ逆さまに海に落ちる夢を見て夜中に目覚めてしまった。
目が覚めても落ちて行く恐怖が体からぬけない。
寝汗をぬぐって、ベッドから身を起こして窓を開ける。
風が無く蒸し暑い夜だった。
真夜中の部屋の窓から遠くの木々が身動きしない黒々した姿で立っている。
空には消え入りそうな三日月が浮かび、虫達が競って鳴いている。
ブナは部屋の中にはいない、屋外の涼しい場所で寝ているのだろう。
目を閉じるとキラブルの淡い水色の眼が浮かぶ。
けたたましい鳴き声、風を巻き起こす羽音。
胸は息苦しく痛み体は鉛のように重たい。
昴は自然に優衣が御守りだと言ってくれたペンダントを握りしめた。
「僕はいつになったら夢が覚められるのだろう」昴は呟いた。
優衣の姿をなぞるように思い出す。
黒目がちな瞳、陶器のような肌、髪から漂う甘い匂。
「優衣さん、優衣、早く逢いたい」昴はキラブルの恐怖から逃げるように優衣の思いを膨らませる。
昴は優衣への思いが心を満たして気持ちが和みやがて眠りに落ちていった。
優衣の腕が伸びて昴を優しく包んだ夢を見た。
明け方近く、昴が握りしめたままのペンダントについている青い石が手の中でわずかな光を放っていた。
昴が余りの空腹に目覚めたのは、昼も近い時間だった。
寝汗で湿ったベッドから身を起こしたものの、全身に力が入らない。
だるい体をやっと起こして、バナナを三本とホンドラの実を食べたがまだ食べ足り無い。
何か食べる物は無いかと、戸棚の中をあちこち探してようやく固くなった干魚を見つけて齧った。
空腹が満たされると、汗でベタベタの体が気になり出した。
泉のある広場までは、水のエレベーターで行けばたいした距離ではないが、頭はすっきりとしているのに体は重石がつたように、動かない。
昴は再びベッドに横になったが、さっき食べた干魚の辛さで喉が渇いた。
水瓶は空っぽで、やっぱり泉まで行くしかなかった。
重い足を引きずって、水のエレベーターを降りて洞穴の通路を進むと出口近くでブナを囲んでマキ、トゴ、シォンの四匹が何か話していた。
昴の方を向いていたマキが昴を見つけると目をしばたいた。 |
ブナとトゴが振り返って昴の姿を見るとお互いに顔を見合わせて、何か言った。
昴は自分の事が話に出ていたと思って気まずい気持ちで猫達に近づいた。
「おはよう、昨日はどうもすみませんでした」昴は言った。
「怪我がなくて良かったですね」マキが胸の毛をせわしく舐めた後に言った。
ブナは昴の方を見ないで知らんぷりしている。
「この際だから、皆で」 |
 |
「いいんだ、任せておけ」シォンが言いかけた言葉をブナが遮った。
ブナは相当に怒っているらしい。
昴は仕方なく、広場の方へ向って歩き出した。
「違うんですよ、グレイが倒れてしまって」マキが慌てて昴の背中に言った。
「グレイが、どうしたんですか?」
いつも元気で、ブーツと一緒に走り回っている悪戯好きのグレイが倒れたと聞いて昴は心配した。
「今朝うちのブーツがグレイを迎えに行ったら、倒れていたんだ」トゴが言った。
「悪い物でも食べたのか、未だに目を覚まさないのだよ」シォンが言った。
「そうでしたか僕も見に行きますよ、何か出来る事があったら言って下さい」昴は言った。
「水を汲んだら家に戻っていろ、話があるから」ブナが命令口調で言った。
昴はブナの態度に少し腹を立てながらも渋々うなずいて泉に向かった。
いつもなら桶に水を汲んでの帰るのは水のエレベーターを使えば苦な似る事はないのに、昴は疲れた体を途中何度も休んで家に到着した。
瓶に水を移すと、耐えきれずベッドに倒れ込んでしまった。
ほんの数分寝たつもりが、目を開くと部屋の中は薄暗く成り始めていた。
ブナは椅子の上で頭を脇腹に伸ばして毛づくろいをしている。
昴はだるい体を起こして、ブナの向かいの椅子に座った。
「グレイはどうなったの」
「ああ、目を覚ましたから大丈夫のようだ」
「そう、良かったね、でもどうしたんだろうね」
「原因は解らないが、元気になったから心配はないだろう」ブナは昴を見ないで言った。
「ブナ、まだ怒っているの、言わないで出かけた僕が悪かったけど」
「いや」ブナはそう言ったまま、夕暮れに染まった窓の外を見ている。
ブナが尾を左右に振って椅子の座面を叩いている音が響く。
黒猫の機嫌が悪い時の仕草だ。
永い沈黙の時が続いて青い夕闇が空を覆い、部屋の中では皿に入れたライラの蜜に誘われたハウラ虫が集まって明かりを灯し始めた。
ブナは冷え始めた外気に鼻をヒクヒクさせてやっと口を開いた。
「やっぱり、初めに話しておけば良かったのかも知れない」
昴は黒猫が何を言おうとしてるのか、解らなかった。
「嵐の夜から随分と長い夢を見ていると思わないか」ブナが言った。
「夢だからね、覚めてしまえば次の朝だし・・・・確かに永い夢だね」
昴は夢から覚めたいとはブナに言えなかった。
「夢だと思っていた方がここでの生活を受け入れやすいと思っていたんだ」ブナは緑色の目を細めて言った。
「キラブルの巣に潜り込んでも夢だから、危ない事も無いと思ったんだろう」ブナが言った。
「だって、夢だよね」昴は言った。
「やはり俺の考えが間違っていたらしいな、今さら言うのも遅いと思うが、ここでの生活は夢の中じゃ無いんだ」ブナは緑の目で昴をまっすぐに見た。
「ブナぁ、嫌だよ僕をからかっているんでしょ、そんな事言っても信じないよ、紅花先生の部屋がなんでフレハラスに繋がっているの、夢に決まってるでしょ」昴は無理に笑い顔を作って言った。
「夢の中で、喋る猫にからかわれたと思っているのか、本当にそう思うのか」ブナは静かに言った。
昴はフレハラスでの出来事に思いをめぐらす。
猫が暮らす南の島、難破船の人々、熱帯の森の不思議な成長、キラブルの巣での恐怖。
「痛みは・・・・確かに、ここで怪我をすると現実に痛いし、それは変だと思ってる・・・でも」
「昴、フレハラスは理解しにくい場所かも知れない、でも現実に存在する場所なんだ、受け入れて欲しい」
「嘘だよ、だいたい猫が喋るなんて僕、信じないよ」
「昴・・・・これが現実なんだ」ブナは悲しそうな顔で言った。
「どうして! 何でなの! 何で僕がこんな所に居ないといけないの! 僕、帰りたい」昴は大声でわめいた。
「落ち着くんだ、どうしてここに来たか覚えているだろう」ブナは言った。
嵐の夜に紅花に追われて屋根裏に登った、そんな事当然覚えている。
昴のナトランを奪おうとした紅花、これが現実なんて信じられない。
昴の目から大粒の涙が流れ頬を濡らした。
不安に思っていた事が現実と聞かされ、今まで抑えていた感情が抑えきれなくなり肩を揺らして激しく泣いた。
ブナはいつまでも黙って昴に寄りそっていた。
泣きながら眠ってしまった昴の頬をブナはザラザラの舌で繰り返し舐めている。
ブナは迷っていた。
この子が背負っているものを・・・・自らの意志とは関係なく決められてしまった宿命を話してしまって良いのだろうか。
幼子が偶然に出会ってしまったバルクによって科された重荷は、この子の人生を変えてしまうのだろう。
それが、この子の運命なのかと思うとブナは暗い気持ちになった。
昴にすべてを話して理解させるには、猫達の秘密を話さなくてならない。
ブナの気持ちは揺れ動いて答えには届かない。
どう考えても一度に全部を打ち明けても理解など出来るはずがない。
バルク様に教えを請う事が出来たら。
ブナは大きなため息をついて消え入りそうな三日月を見上げた。
ともかく、この子が少しでも安全に暮らせるようにしなくはては。
ブナは泣き疲れて眠る昴にもたれ背を丸くして目を閉じた。
夜明け近く森から数羽の鳥が一斉に羽音を立てて舞いあがった。
ブナは気配を感じて目を覚まし、頭を起こして森を見た。
薄暗い空には濃い色の筋状の雲がフレハラス山に集まるようにたなびいている。
髭の先に微妙に伝わる感覚・・・・何か変だ。
棚の上の木皿がカタカタと小刻みな音を立てた。
「起きろ!」ブナが叫んだ瞬間に大地を震わす地響きと共に貫くような揺れがフレハラスを襲った。
昴は目を覚ました瞬間、何が起きたのか解らなかった。
薄暗い部屋の中で自分の体が上に浮き上がって飛ばされそうになり慌ててベッドの背にしがみついた。
次の瞬間ベッドは床に叩き付けられ数メートルも滑って壁に激突し昴は床の上に転がり落ちた。
台所の天井から崩れた頭ほどの大きさの石がゴロドロと転がって部屋の中に散乱した。
石を止めてあった漆喰が壊れて土煙がもんもんと立ち上がっている。
鍋や皿が音を立てて落ち、瓶、椅子、机、棚などが一瞬でひっくり反って部屋はゴミ箱のようになった。
「おい、大丈夫か?」ブナが逃げ込んだ籐の籠の中から姿を現した。
土埃を全身に被って黒い体が灰色になっている。
昴はベッドの下から這い上がって埃で汚れた顔を手でぬぐった。
「凄い地震だったね、あ〜部屋の中がめちゃめちゃだ」昴が言った。
「昴、急いで外に出るんだ」ブナは後ろ足を強く蹴って窓のフチに飛び乗りそのまま外へジャンプした。
昴も続いて窓から外に飛び出た瞬間、二度目の揺れが起きた。
遺跡の石組が音をたてて崩れ、階段状のゾハランの遺跡から砂煙が舞い上がった。
ブナの家も二度目の揺れに力なく崩れ、後かたもなく落石の中に埋もれてしまった。
フレハラス山から立ち昇った黒煙が怪物のような形でどんどん空に広がってゆく。
東の空から顔を出し始めた朝日が、黒雲を照らし光っている。
昴は立ち上がる気力もなく茫然と大地に座り込んでいた。
|
18 祈り
明け方から降り始めた強い雨は埃まみれの大地を洗い流していた。
地震の後のゾハランの町は酷いありさまだった。
階段状の遺跡の西側で地滑りが起きて土砂が遺跡を押し流し、西側に或る住居の半分はその中に中に消えていた。
危うく残った住居もその殆どは天井が潰れ、岩石の塊になっていた。
ブナの家も崩れた岩石に押しつぶされ跡型なかった。
ブナと昴は岩陰で雨を避けながら、明るくなるに従って次第に浮かび上がるゾハランの惨状を茫然と見つめていた。
ブナの家があった場所の崩れた岩の間から玄関の木のドアが見える。
新宿とフレハラスを繋ぐ扉は瓦礫の中に埋もれてしまった。
「皆は助かっただろうか」ブナが口を開いた。
崩れてしまった遺跡の西側にも数匹の猫が住んでいた。
遺跡上部から押し流された土砂は谷の下まで届いて、その中で動く物など居ようにはとても見えない。
激しい雨がいく筋もの流れとなって谷を下って行く。
フレハラス山は黒い煙を空に吐き続けている。
時々襲う余震に身を縮ませ、降り注ぐ雨をぼんやりと見ている。
「雨が止んだら、皆を探しに行こうよ、ブナの家族の無事を確かめないとね」昴が言った。
「そうだな、雨が止まない事にはな」ブナが言った。
「大丈夫だよ、きっと皆んな元気だよ」昴は自分に言い聞かせるように言った。
ノアやサム達クグルの人々、マキ、トゴそして西の遺跡の住んでいたシォン、皆と逢える日は来るのたろうか。
「昴、お前に話しておきたい事がある」ブナは雨の向こうに霞む森を見ながら言った。
「そうだね、僕も聞きたい事があるよ」昴はブナの横顔に言った。
「お前の聞きたい事と俺の言いたい事はおそらく繋がった話だが、それは単純な事じゃ無いんだ、まず俺達とどうして関わってしまったのかを話そうと思う」
ブナは、きちんと前足を揃え座りなおしてから話を始めた。
話は遠い昔にさかのぼった。
古代の深い森に白い毛の長い猫の一族が人間の目を避けて暮らしていた。
或る時、一族の狩りの名手のバルクと言う猫が山火事のあった窪地に迷い込んで永い間行方不明となり季節が変わる頃ようやく一族の元に帰った。
戻ったバルクは以前とは違う様子で、体は二まわりも大きくなり青かった目は緑色に輝き全身から力がみなぎったような素晴らしい雄猫になっていた。
バルクはたちまた群れのリーダーになり猫達を変えていった。
それまで簡単な言葉しか持っていたなかった猫はバルクの授ける物によって思念で話が出来るようになった。
バルクは何世紀にも渡って生き続けた。
バルクは、いやバルク様は人間の言葉で言うなら神のような存在になって猫達の頂点で居続けた。
バルク様から授け物を受けた猫達は前世の記憶を持って生き死にを繰り返した。
授け物を受けた猫達は世界中に広がり数を増やして繋がりを持ち組織のようなものが出来上がっていった。
ブナはおとぎ話を語るようにバルクの事を話した。
「ねえブナ、その猫の神様が僕といった何の関係があるの」
「もう少し話を聞きなさい、俺を含めたフレハラスに居る言葉を話す猫は、バルク様から授け物を受けた猫なんだ」
「授け物って何なの、それを貰ったから話せるようになって、それに前世の記憶を持って居るって言ったよね」
「ああ、俺達は過去から続く思いを忘れないでいる、授け物自体が何かは俺自身も良く解らないのだ」ブナは言った。
「だって、ブナは授け物を貰ったんでしょ」昴は言った。
「昴、お前も授け物を受けているのだよ」
「僕が?僕そんな物、貰って無いよ!」昴は驚いて言った。
「お前は小さかったので覚えて居ないかも知れないが、子供の頃にバルク様から偶然の形で授け物を頂いてしまったんだ」
「どう言う事なの、だって僕、生まれる前の記憶なんて無いし、それに・・・・」
「そう、猫の言葉は理解できるだろう」ブナは緑の目を細めた。
昴は幼い頃の記憶に大きな猫に飛び掛られた思い出がある。
その時の怖かった思いが猫嫌いのきっかけだった。
もしかしたら、あの時の事が関係あるのかも知れない。
「バルク様って、もしかして白い大きな猫なの?」
「長く美しい白い毛を持つ、とても大きな猫だ」
「僕、何となく覚えているよ草むらから大きな猫が急に出て僕に飛びかかったんだ」昴は言った。
「バルク様は飛びかかった訳じゃない、時空の裂け目から出た場所にお前が居て衝突してしまったのだ。お前の体にバルク様の前足が触れてしまい偶然にも授け物を授かってしまった、こんな事故は今までに無い事だった、猫以外の人間に授け物をしてまうなんて考えられない事だ」ブナは南から昴を追って来た見守り猫のチャスケに頼んでバルク様との関わりを調べていた。
「僕そんな物要らないよ、返す方法は無いの」昴は言った。
「事は簡単じゃ無い、授け物の正体すら解らないのに返すなんて不可能だ」ブナは言った。
「でも僕どうしたらいいの」
「バルク様の前足には不思議な力が備わっている、言い伝えでは山火事のあった窪地で妙な石を踏んでから前足の肉
球が変化して不思議な力が備わったらしい、普通は台座の上に居られるバルク様の前で授け物を受ける。猫が頭を垂
れて離れた場所から肉球の力を受ける事になっている、それなのにお前はその肉球に直接触れてしまったのだ、それがどんなに重大な事か想像もつかないだろう」
「でも僕今まで普通に暮らして来たし、他の人と変わった所も無いと思うよ」
「昴、お前には何も見えて居なかっただけだ我々はあの事故の後からずっとお前を見守って来た、授け物を受けたお前からは普通の人間ではあり得ない量のナトランを持ってしまった」
「ナトランって僕には見えないし何の役にも立って居ないよ」
「そうだな、お前には多量のナトランは邪魔なだけかも知れない、そんな物が有るから紅花に狙われたのだからな」
「僕、普通でいいんだ、普通に暮らしたいんだ」昴は言った。
「普通か、そうだなそれが一番幸せかもしれない」ブナはポツリと言った。
「僕、元の場所に帰りたい」昴は吐きだすように言った。
雨は激しさを増して降り続いている。
雨で霞んだ色の無い景色の中でフレハラス山だけが黒い怪物のような姿を見せて居る。
ブナと昴はそれきり口をつぐんで黙って座っていた。
雨が止んだのは地震から三日目の朝だった。
フレハラス山の黒煙も収まり、体に感じる余震も殆ど無く成っていた。
ブナは夜明け前に出かけて朝日が昇る頃ホンドラの実を持って戻って来た。
ブナの奥さんと子供達はぎりぎりの所で落石から難を退かれて、マキとトゴも無事だったが西の遺跡に住むシォンが行方不明になっている。
午前中の時間は瞬く間に過ぎた。
昴は西の遺跡に住んで居た猫達の捜索に加わり、谷に押し流された土砂を掘り返した。
照りつける日差しの中、汗まみれになって土を掘り返したが遺跡の上部から流れ落ちた土砂の圧倒的な量の前では猫や昴の力は余りにも非力だった。
ブナは今夜違う方法を試すからと言って捜索を打ち切った。
午後からはクグルの村に出かけた。
地震で所々、水のエレベーターが壊れていて思ったより時間がかかって村に到着した。
出迎えたノアは人が変わったようにやつれ、やせ細った顔にうつろな青い目が悲しそうで立って居るのさえ辛そうだった。
村は異様にしずまり嫌な焦げ臭い匂が漂っていた。
ノアの椰子の小屋は歪んでいたが、何とか立って居た。
村の外れの広場はバナナの葉や花弁が絨毯のように敷かれ、その中心の土がうず高くなって居た。
早朝、亡くなった人の埋葬がここでおこなわれたそうだ。
その中にノアのおじいさんも居た。
山肌に出来た洞窟ではその殆で落盤があってその中で暮らしていた人達は押し潰され怪我をし、その中の何人かは手当のかいも無く亡くなってしまった。
トムは腕を骨折してしまったが、三人の子供達は無事だった。
ノアは涙を見せていない、怯えた小動物のように自分の内に心を隠してしまって昴には何も語らない。
昴は一人ぼっちになってしまった心細さや辛さを自分の事を重ねて胸が痛んだ。
肉親が誰も居いと知らされた時の気持ちは、一人ぼっちで世界中から置き去りにされたような、身の置き所の無い不安でいっぱいだった。
ノアもきっとそんな辛い気持でいっぱいなのだろう。
昴は何も言わずにノアの肩を抱いた。
その夜フレハラスに生き残った猫達とクグルの人間達が遺跡の上部に集った。
三日月の薄い月明かりの中、クグルの人達の持つハウラ虫のランプが草むらの中にぼんやりと光っている。
遠巻きに座っている猫達の黒い影が動いている。
ブナはテラスの縁の少し高くなった所に座って全員を見渡していた。
報告では死亡が確認された猫は五匹、行方不明が三匹、怪我をした者が十五匹でこの集会に参加出来たのは全体の猫の三分の二程度の数だった。
人間のクグルの村でも三人のが亡くなり四人が怪我をした。
人間達に見えるようにブナの両脇にハウラ虫のランプが置かれた。
遠巻きにしていた猫達が人間をすり抜けて前に進みブナの前に集まった。
昴は猫達の後ろに回りノアの隣に立った。
ブナが口をきって、簡単な挨拶をした。
その後で、トゴが地震の被害状況と水のエレベーターなどの復旧に関わる仕事の分担などを話した。
太った三毛猫のミスは仔猫のように痩せた姿になって現れ、食料の被害状況と今後の分配方法などについて話した。
ブナが再びテラスの上に立った。
「これから回帰の祈りを始める。本来ならシオンが行う儀式なのだが皆もご存じの通り西の遺跡の崩落からシオンを見つけ出す事は出来ないでいる、私では力不足かも知れないので皆も心を一つにして欲しい」ブナは低い声で静かに言った。
ブナは皆に背を向けて谷に向かって背筋を正して座った。
ハウラ虫の明かりが消されて、黒猫の姿は三日月の頼りない光の中で影のように見える。
ブナは頭を胸に埋めるほどうつむいて耳を伏せ、喉を鳴らし祈る。
全身の毛がわずかに逆立って震えている。
猫達も全員が同じように頭を下げ、ごろごろと喉を鳴らし祈る。
猫達の喉鳴らしの音はだんだん大きくなってあたりの空気を振動せる。
ブナの耳は微かに揺れ髭が何度もピクピクと動いた。
「無理なのかも知れない」ノアがポツリと言った。
永い祈り中ブナはため息を付くように大きく息を吸い、顔を上げて消え入りそうな三日月を見上げた。
ブナはゆっくりと目を閉じて優しい声で鳴きはじめた。
憂いを含んだ鳴き声は低く高く歌うように谷間に響く。
やがて回りに居た猫達も次々と顔を上げて歌声に参加する。
猫達の織りなす歌声が心に沁み昴の頬から訳もなく涙が流れ落ちた。
ノアも泣いている、昴はノアの手を握りしめた。
漆黒の西の遺跡から数匹のハウラ虫が飛び立った。
ハウラ虫かと思われた光は歌声に導かれるようにゆらゆらと谷間を登り近づいて徐々に大きくなって近づく。
拳ほどの大きさの光の一つがブナの数メートルまで迫った時、昴はそれがシオンだと感じた。
シオンのナトランは埋もれた地中から体を離れ天高く舞い上がりブナ達の待つ場所にたどり着いた。
ブナは後ろ足で立ち上がって、光の球に手を伸ばした。
白と淡い青の濃淡が美しいシオンのナトランはブナに何度も近寄りそして弧を描いて猫達の頭上に留まった。
西の遺跡に埋もれていた二匹の猫のナトランも白い光の球になって
集まった猫達の間を擦り寄るように飛びシオンと共に上空に留まった。
猫達の歌声は続き、北東の空から薄緑を帯びた光の球が三個寄り添うようにゆるゆると遺跡に近づいて来る。
クグルの村で亡くなった人のナトランかも知れない。
北の森からも南の海の方角からも星屑のようなちいさな光が地上から湧き上がり銀河のように流れをなして遺跡の上部に集まって来る。
北東の空から来た薄緑の光の球はノアをめがけて降下する。
昴はノアに寄り添う光の球がノアの祖父だと感じた。
ノアは肩を震わせ泣いている。
温かく優しいナトランの思いが傷口を塞ぐように心に沁みていく。
頭上ではシオンのナトランを中心に無数の大小の光が渦を巻いている。
亡くなった獣や鳥、虫達のナトランは回帰の祈りに呼応して朽ちた体を離れ空に踊った。
猫達の歌声は途切れて、皆がごろごろと喉を鳴らした。
ブナは中心に居るシオンを見つめ髭を震わせ全身でごろごろと音をたてる。
猫達の喉笛が空に届くと、シオンの光は大きく円を描いてから北の空に向かって飛び出した。
満点の星空の中、星になった魂の行列が北のフレハラス山を目指して飛んで行く。
やがてシオンの光はフレハラス山の黒い影に飲み込まれていった。
ブナがふうと大きなため息をついた。
これで回帰の祈りが終わったのだと誰もが思った時、フレハラス山の黒い影から無数の光が弾かれるように夜空に飛び出し夜空の四方に散って行った。
猫達は慌てて怯え草陰に伏せ、ある者は身動きできずただ天を見上げた。
「ブナどうしたの、何があったの」昴が言った。
「大変だ! 帰れない、ナトランが帰れないなんて世が滅びてしまう」ブナは桃色の口を開いて凍りついたように言った。
集まったナトランは一瞬でちりぢりになって夜空に紛れ後には何事も無かったように空には満点の星が瞬いていた。

|
19 プニハ鉱山
ブナ、マキ、トゴによる話し合いは朝日が昇るようになってようやく終わった。
昴とノアは猫達の後ろに座り事の成り行きを黙って聞いていた。
話が進むにつれて回帰の祈りが失敗してしまった事がどんなに重大な事なのか昴にも解ってきた。
人も猫もすべての生き物は命の源のナトランを持って生を受ける。
ナトランは生の源となり生きて行く事により消耗しその量を減らして行く。
最後に核となったナトランは体から離れコククウと言われる場所を通り再び物に宿り物は生き物となる。
そのコククウの入り口がフレハラス山にあり猫達はナトランを守る者としてこの島を監視して来た。
太古の昔はコククウの入り口は多く人々の営みの近くに存在していた。
生命の循環は自然に行われ、役目を果たしたナトランはコククウに向かって進み新しい命となって淀む事はなかった。
文明が進み命に人の手が入るようになってからはクココウの入り口は数を減らし近年では回帰の祈りを行わないとナトランがコククウに戻れない事が多くなった。
その事で命の循環がうまくゆかず子供が出来づらくなって人口が妙に減ったりまた或る地域では増えすぎたりする原因の一端になっているとブナは言う。
昨夜の回帰の祈りが失敗したのは、フレハラス山のコククウの入り口が何らかの原因で閉じてしまったらしいと言うのが三匹の達した推測だった。
「私が口を挟むべきじゃないのは解っているけど、聞かせて下さい。昨夜コククウに入れなかったナトランはどうなるのですか?」ノアが口を開いた。
「原因がフレハラス山の入り口が閉じた事と仮定しての話だが、コククウの入り口はまだ他にもある、確実にとは言えないが他の入り口からコククウに入れる可能性も残っている」ブナが言った。
「可能性ですか、可能性ってそれは少ないって事に聞こえるけど」ノアが言った。
「君がお祖父さんの事を心配しているのは解る、俺達もシオンやルル、ブッチがコククウに戻れるかとても心配している、信じる他は無いのだ。シオンはバルク様の血を遠く受け継いだ猫だからきっと皆を導いてくれると思う」ブナが言った。
「フレハラス山の入り口が開けば、もう一度回帰の祈りをする事も出来ますよ」マキが言った。
「その為にも一刻も早く様子を見に行こう、プニハ鉱山から入ればコククウの入り口に行けると聞いている」トゴが言った。
「マキ、トゴそれに昴も一緒に来てもらう午前には出発して今夜はプニハ鉱山の入り口で仮眠して明け方を待つ」ブナが言った。
「何とか今の季節ならぎりぎり明け方で大丈夫でしょう、赤星の位置を調べ直しておきますよ」マキが言った。
「あの、赤星って火星の事ですか?」昴が遠慮がちに言った。
「確かに火星も赤く見えますが赤星は牛の形をした星座の中に或る赤い星です、太陽や月、惑星にじゃまされて見えない事がたまにあるのですが明日の夜は大丈夫かと思います」マキは髭をヒクヒクさせて言った。
「その赤星の位置とコクトウの入り口に行くのに何の関係があるですか?」昴は言った。
「今ここで細かい説明をしている時間は無い、ともかく赤星の位置によってコクトウの入り口までたどり着けないって事だ」ブナが不機嫌に言った。
「急いで戻って必要な装備は用意して置きます、ホンドラの森の入り口で正午に逢いましょう」トゴが言った。
皆が帰ろうと立ちあがった時にノアが口を開いた。
「私も行っていいですか?」
「それは駄目だ、昴は特別だが当然人間にコクトウの入り口を教える事は出来ない」ブナがきっぱりと言った。
「途中まででも行きたいの、もし地震の落石で入り口が塞がっていたら昴一人で石を取り除くのは大変だし私も何か出来るかも知れない」ノアが言った。
ブナとマキ、トゴは昴達に解らないように小声で鳴いて話合いをした後で言った。
「仕方がないな、プニハ鉱山の入り口までなら許そう」永い話し合いの後でブナがやっと答えを出した。
|
ホンドラの森の入り口に集まった三匹と二人は森で昼食を済ませた後、森を抜けてプニハ鉱山に向かった。
トマネ川の上流で休憩をとり、沼地を迂回してアシの間を進む頃には太陽が西に傾き始めた。
ここまで来るとフレハラス山はまじかに迫り赤い岩肌の急斜面がそそり立っている。
プニハ鉱山は水のエレベーターを作った古代の人の作業場で、本当に鉱山だったのかは定かではなく、坑道らしい人工的な洞穴がある事からプニハ鉱山と呼ばれてきたと言う。
今は猫達ですら訪れる者はない。 |
 |
家ほどの大きさのある石が取り残されたように転がっている道を縫って進む。
途中幾度も行き止まりの岩に阻まれて、後戻りをしながらやっと入り口らしい場所に辿りついた。
坑道の入り口と示された場所は岩肌に取り付くようにシダや木が多い茂り、奥に続く僅かな暗闇しか見えない。
ブナとトゴはさっそく茂みに入り暗闇の中に姿を消したが、昴もノアも目の前の暗闇が不気味に思えて入るのをためらった。
マキの指示で昴とノアはキラブルや野獣に襲われないように、また落石を避ける安全な場所を探し仮眠の為の寝床を用意した。
しばらくしてブナとトゴが毛に草の実を沢山付け汚れた姿で戻ってきた。
あたりは夕闇が迫り目の前に迫るフレハラス山が巨大な影となる。
「中はどんな様子でした」マキが言った。
「途中までは何とか行けますよ、後は赤星が昇ってからでないと」トゴが言った。
「明日に備えて腹ごしらえをして早く仮眠をとろう」ブナが言った。
ハウラ虫の明かりを灯して持ってきた、干魚とホンドラの実を食べていると向かい岩陰から何かがキラリと光った。
ブナもトゴも毛を逆立てて低いうなり声を上げる。
昴もノアに続いて立ちあがって身構えた。
四つの光が近付いて来ると三匹は鼻をヒクヒクとさせ、途端に警戒を解いた。
「グレイ、ブーツ!」ブナは怒鳴った。
二匹の若い猫は軽い足取りで尾を揺らしながら皆に近づいて来る。
「お前ら何しに来た」トゴが言った。
「僕らもコククウを見たくて」ブーツが無邪気に言った。
「大バカ物!お前らの来るような所じゃない帰れ!」ブナは爆発しそうに怒って言った。
グレイもブーツも悪びれた様子もなくお互いに顔を見合わせている。
「でも、ここまで来ちゃったんだから、二人だけで今から帰るのは怖いし、それに腹ペコなんだ」グレイが言った。
「グレイ、この前は倒れたばかりでこんな遠くまで来て仕方の無い奴だな」トゴが言った。
「もう元気だから大丈夫だよ僕達もコククウの入り口まで一緒にいっていいでしょ」グレイが言った。
「お前らを連れて行くなんてとんでもないぞ、邪魔になるだけだ、帰れ!」ブナは目を吊り上げて凄んで言った。
「まぁ今すぐに二人だけで帰るのも危ないから夜が明けたらノアと一緒に帰りなさい」トゴが言った。
「やれやれ、とんだお荷物が増えたものだ。お前達今夜はここから一歩も動くんじゃないぞ」ブナは諦め顔で言った。
グレイとブーツが来てから緊張していた皆の気持ちが和らいだのは事実だった。
仔猫を卒業したばかりの若いグレイとブーツはすべての物が楽しい年頃で皆の周りを飛び跳ねて遊んだり二匹で組み合って転がったり騒々しく動いてからスイッチが切れたように無邪気に眠った。
疲れ果てた昴とノアも猫達と寄り添って眠りについた。
眠りの中で昴は優衣の黒い瞳に見つめられているような気がして幸せな気持ちで微笑んだ。
靄のような優衣の姿にもう少しで手が届きそうになった時、何かに邪魔されるように目が覚めてしまった。
目を開くと空から星が落ちてきそうなほどの満点の星空が目の前に広がっていた。
空にこんなに沢山の星があるなんてフレハラスに来る前は想像も出来なかった。
優衣さんもに、この星空を見せてあげたい。
昴は自然に胸元のペンダントを指でふれた。
手の中に実在するペンダントの感触、フレハラスが現実ならここに存在するペンダントは何なだろう、ふと疑問が浮かんだその時に誰かが声をかけた。
「昴さん目が覚めましたか?」突然の声に目をやるとマキが皆から少し離れた石の上でハウラ虫のランプを灯して小さな本を手にしている。
「夜明けまでまだ時間がありますか」昴は言った。
「今は真夜中を少し過ぎた所です、まだ寝ていても大丈夫ですよ」
「何の本を読んでいるのですか」昴は立ちあがってマキの隣に座った。
「星の座標の本ですよ、赤星の位置を正確に見つけないといけないのでね」マキが言った。
「そんな事が解るなんて凄いな僕は空に或る星の名前もどれ一つも解りませんよ」昴が言った。
「オイラにはこんな事しか役に立てないのでね。そう言えば昴さんの名前の由来は星の名前ですよね」
「昴と言う星は聞いた事がありますね、でも僕は名前を付けてくれた両親を知らないので昴が星の名前かどうかは聞いてないんです」
「それは残念ですね、昴と言う星はおうし座の中にあるプレアデス星団の和名です。地球から四百光年のかなたにある星の集まりですよ」
「あの、おうし座って牛の形をした星座だと昨日の夜マキさんが言っていた赤星がある星座ですか?」
「そうですよ偶然ですね、赤星はアルデバランと言って牛の心臓とも言われる赤い星です。もう少したったらあの辺から見えますから教えますよ」マキが言った。
その後マキは、北斗七星やいて座、さそり座などの場所を示して星座にまつわるいろいろな話を聞かせてくれた。
夜明け前に全員が起きてマキを中心に円陣を組んだ。
「皆さん私が赤星をとらえますから思念を合わせて下さい」マキが言った。
やがて東の地平線からおうし座が昇り始める。
マキが背中の毛を逆立せて一心に夜空を見つめる。
「後に続くものをお導き下さい」マキは赤星に思念を送ると自分のナトランをひとかけら赤星に向かって放った。
マキから放たれた一粒のナトランはルビーのように赤く輝き暗黒の夜空に吸い込まれて行く。
猫達はナトランが赤星に届くように力を合わせて思念を送る。
一瞬、赤星が瞬いたように見えた。
「今です、すぐに坑道に入って下さい」マキはそう言って崩れるように足を折った。
ブナ、トゴに続いて昴も生い茂るシダの葉を分けて坑道の中に入った。
ハウラ虫のランプのたよりない光に照らされた坑道は人がやっと通れる広さで壁は黄土色の岩を覆って苔が生い茂り壁からはたえず地下水が滲みでて地面に流れぬかるみにないる。
所々に落盤を防ぐために組まれた石がはめ込んであり、人の手で造られた洞窟だと言う事が解る。
ぬかるみに足をとられないように注意して歩く、しばらく歩いて坂を上るとぬかるみは終わり、乾いた岩の地面になった。
苔の壁は無くなり、黄土色の岩盤に所々斜めに茶色やベージュの地層が入りマーブル模様を作っている。
前方の闇の中にぼんやりと光る楕円の赤い輪が見える。
赤い輪は暗闇の空間に浮いていて呼吸をするような速度で洞窟いっぱいに広がりまた半分ほどの大きさに縮まったり、を繰り返している。
「マキは成功したらしい」ブナが言った。
「あの赤い輪がコククウの場所に続く入り口ですよ」トゴが昴に教えた。
ブナの指示でハウラ虫のランプを地面に置いて真っ暗な坑道の中を赤い輪目指して進む。
先にたどり着いたブナは宙に浮いた赤い輪の中に飛び込むように入って行った。
「まっすぐに進めばいいだけですよ」そう言ってトゴも輪の中に入った。
暗闇で淡く光る赤い輪は生き物の唇のようで気味が悪い。
昴は恐る恐る、輪の中の暗闇に手を入れると向こう側は、ひんやりと冷たい感触がする。
思いきって体を入れると全身がするりと中に入ったと思った瞬間、後ろから首を絞められて昴は輪の中で宙刷りになってもがいた。
体は輪の中に入ったのに、誰かに首を絞められているようで両手をバダバタと動かすが手は宙をきって何にも当たらない。
「助けて、助けて!」苦しい、息が出来ない、昴は無我夢中で叫んだ。
「紐だ、首に鎖が引っ掛かっている!」ブナが叫んだ。
昴が首に手をやると、優衣からもらったペンダントの鎖が輪の何かに引っ掛かって首を絞めていた。
猫達は昴の肩まで登って鎖を食いちぎろうと必死になるが昴が暴れるので鎖に歯がかからない。
ブナの前足がやっと鎖にかかって、強引に頭から抜くとペンダントは勢い良く輪の外に飛ばされて行った。
昴はゼイゼイと息をして座り込む。
ブナとドゴも地面に腰を降ろして、荒い息をする。
昴は恐ろしさで震えが止まらない。
「まっくどう言う訳なんだ、何かに鎖が絡まったのかな」トゴが言った。
ブナはむっつりと黙りこんで、何か考えている。
昴は輪の外側に飛ばされて行ったペンダントの事が気になっていた、優衣からもらった大事なペンダントだ戻って探したいと思った。
「ともかく、無事で良かった先に進もう」ブナが言った。
昴は気持ちを落ちつけて立ちあがって始めて気がついた。
暗闇の中で立ちあがった昴の足元には地面が無かった。
|
20 狭間の部屋
隣に居るはずのブナを探して暗闇の中で目を凝らすとトゴの白い足先が目に止まった。
「トゴ天井に張り付いて何をしているの」昴は逆さまになって歩いているトゴを見上げて言った。
「昴さんこそ、逆さまになって・・・でも変だなぁ足の下に地面がある感触が無い」トゴが答えた。
「ここは、まったく変な場所だ床も壁も天井も何も無いようだ」ブナが空間をらせん状に歩いて昴の目の前に現れた。
赤い輪の内側の真っ暗な場所では猫や昴自身のナトランが発光体のように光を帯びて見える。
発光体に包まれた深海魚のような猫達が空間を自由に横断している様はとても奇妙だった。
輪の中の暗黒の部屋は天地が定まっていない、だが無重力のようにふわふわした感じでもない。
自分の足が地に或る感覚は不確かでどこまでが地面でどこからが壁なのかまったくの不明だった。
「困ったな、地面が解らないのではどっちに進むのか解らない」ブナが言った。
「むやみやたらに歩いたら迷子になってしまいますよ」トゴが言った。
「ここに前に来た人は居ないの?」昴が言った。 |
「コククウを知る者はバルク様だけなのだ」ブナが言った。
「そのバルク様は今何処に居るの、行き方を聞けないの」昴が言った。
「聞くことが出来れは良いのだが・・・・・お前だから話してもいいだろう。この事は絶対の秘密なのだ、くれぐれも他には話さないように・・・・・バルク様は現の御姿を無くされてしまったのだよ」ブナは吐きだすように言った。
「現って現実にあるって意味でしょ、じゃぁバルク様は死んでしまったって事なの」昴が言った。
「いや、それとは違う。そもそも死とは何だと思う」
「死は命が・・・・ナトランが無くなるって事?」
「昴、少しはナトランが解ってきたな。体から離れたナトランは次の場所へと旅立ち別の体に同化する、残された体は活動を止めてやがて朽ち
果てる、それを普通死と呼ぶ。しかしバルク様は体が朽ちてもナトランがバルク様であり続けているのだよ」ブナが言った。
「体は実在しないけど、バルク様は生きているって事」
「そう、その通りだ」
「だったら、バルク様は何処に居るの?」昴は言った。
「それが・・・・」ブナは言葉に詰まった。 |
 |
「ここ数年御姿が見えないんだよ、どうもナトランの力が減った事が原因らしいのだが、このままだと青の組織が増えてしまう」トゴが言った。
「トゴ!」ブナが怒鳴った。
「何かまだ僕に隠しているね、残らず教えてよ僕だって危険を承知で来ているんだ青の組織って何なの?」昴は強く言った。
「ナトランを食らう奴らだ」ブナが言った。
「紅花先生もその仲間なの?」昴が言った。
「紅花は下っ端だがな」ブナが言った。
「昴さん君も青の組織に狙われているから僕らはかえって秘密にしてきたんだ、青の組織はナトランを盗んで永遠の命をむさぼるだけの組織ではないって事が最近解って来たから」トゴが言った。
「青の組織はナトランを大量に集めているのは事実だ、でも今はその目的が掴めない」ブナが言った。
「紅花先生が下っ端だったら、青の組織のボスは誰なの」昴は言った。
「それが、解れば攻めようもあるのだが・・・・」ブナはうなった。
「ともかく今私達がしなければいけない事はフレハラスのコククウの入り口が開いているかを確認する事です」トゴが言った。
「危険だが、この部屋を調べない事には前に進めないな、昴は入り口の輪の所に留まってくれ、俺達は連なってらせん状にだんだん遠くに距離を伸ばして探索を行う、戻る道が解らなくならないように昴には思念を送って欲しい」ブナが言った。
昴は赤い輪の前に立って、遠ざかるブナとトゴを見ている。
真っ暗な世界に、夜光虫のような光が二つらせんを描きながら遠ざかって行く。
昴は猫達が迷わないように赤い輪の位置を思念で教える。
何処までも続く暗黒の世界で昴は青の組織の事を考えていた。
昴には紅花が自分のナトランを奪おうとした青の組織のメンバーだと知らされた今も紅花をなぜか恨んだり憎んだりする気持ちはなかった。
食べる物もなくて困っていたあの新宿の町で手を差し伸べてくれた紅花。
とりつきの悪い人ではあっても、優しい所のある人だと昴は思っていた。
気になるのはあの台風の日、フェアリーローズで紅花先生は誰に突き飛ばされたのだろう。
紅花の怯えた顔を思い出すと誰かに脅されていたように思えてならなかった。
もしかしたら、紅花先生は青の組織に脅されていたのかも知れない。
きっとそだ、昴は紅花に同情を感じていた。
フェアリーローズに青の組織の人が来ていたなら、優衣は大丈夫だろうか。
優衣さんに何かあったら、そう考えると昴は一刻も早く元の場所に戻りたかった。
夢だと思っていた世界が現実で、現実だと思ってい事が夢なのか。
実家を飛び出して新宿の町をさまよって紅花の家で暮らし、優衣と出会ってその全部が夢だなんてあり得ない。
フレハラスが現実ならここに来たきっかけになった全ての事は現実なんだ。
でも・・・・・
昴は暗黒の世界で目を固く閉じて心に描く。
目を開けば実家の成川の古びた部屋が見える事を祈りながら。
「駄目だ、何も見つからない戻るぞ」ブナの声がした。
目を開くと二つの発光体がだんだん大きくなって近づいて来る。
昴は大きく手を振って二匹を迎えた。
「疲れたでしょ、どうでした」昴が言った。
「何処まで行っても同じですよ、真っ暗で何も無いし何も感じない」トゴが言った。
トゴは疲れたように座り込んだ。
「その左腕の印はいつから付いているのだ」ブナが唐突に言った。
昴が言われて見ると、左の二の腕の内側に花のような模様が虹色に輝いている。
「ああこれ、普段は見えないけどブラックライトに当たると出て来るらしんだ、Blue heavenでお客さん言われて始めて気がついたんだよ」昴が言った。
「もしかしたら、それは」トゴが模様を見て言いかけて、そわそわと胸の毛を舐めた。
ブナも緊張を弱めようと軽く毛づくろいをした。
「どうやらその御印はバルク様の足跡に違いないな」ブナが言った。
「バルク様の足跡って、それじゃあ僕が小さい頃に飛びかかられた時に付いたって事なの、でも足跡にしては変な形だよね」昴が言った。
「小さな円が七つと中側に大きな円が一つあるだろう、バルク様は七本指をされているから肉球の跡は普通の猫とは違うのだ」ブナが言った。
「ここの場所で見えたと言う事はもしかして」トゴが言った。
「だぶんそうだろう。昴、御印の位置をしっかり覚えておきなさい輪の外に出るから」ブナが言った。
昴が赤い輪を出ると腕の模様は跡かたもなく消えていた。
匂いも空気の流れも無い輪の内側の異様な暗闇から出た場所は洞窟のカビと埃のまじりあった匂いが生き物の居る場所を感じさせて昴をほっとさせた。
少し先の坑道の闇の中で置いてきたハウラ虫のランプが灯っている。
「御印の位置は解っているな、赤い輪に御印を重ねてごらん」ブナが言った。
昴は怖々と左腕を伸ばして赤い輪に印の位置を押し付ける。
その瞬間に輪が瞬いて赤い色が鮮度を増して紅色に変わった。
「もう一度輪の中に入るんだ」そう言ってブナとドゴは輪の中に体を滑り入れた。
昴も続いてくぐり抜けるように慎重に体を入れる。
寒々とした空気が昴を包んだが、昴は依然と輪の中に居た。
さっきは、一瞬で通り抜けた赤い輪が今はチューブのように長く伸びて暗闇の中で道を作っている。
少し先のチューブの中でブナとトゴが待っていた。
「やっと解ったな、この道がコククウへと繋がっているのだろう」ブナが言った。
昴たちは離れないようにひと固まりになって赤いチューブの道を進む。
半透明のチューブは暗黒の中に浮いているようで外はぐるりと深い闇に覆われている。
道はただまっすぐに伸びて終わる先は見えない。
歩いても歩いても前にも跡にも同じ景色が連なっている。
みな黙って、ただひたすら道を急いだ。
何時間も歩き続けて昴は疲れ果て足が止まってしまった。
ブナもトゴも歩みを止めた。
「この道はどこまで続いて居るのかな、コククウまで何年も歩かないと着かないって事はないよね」昴が言った。
「仕掛けが何かまだあるかも知れないな」ブナが言った。
「この輪は後に続く者の為にバルク様が残してくれた物なのでしょうか」トゴが言った。
「ここで時間が掛りすぎるとノアのお祖父さんやシオンのナトランが迷って戻れなくなっちゃうって事ないの?」昴が言った。
「それはあり得る事だな」ブナは果てしなく続く赤い道を見つめて言った。
昴とブナ、トゴはシオンやお祖父さん亡くなった猫や人達を思った。
「帰りたい」昴の心に誰かがささやいた。
その時何もない空間の中をチューブの奥に向かって一筋の風が吹いて行った。
ブナとトゴもお互いに驚いたような顔で見つめあっている。
「聞こえた?」昴が言った。
「ああ、聞こえた。あれは確かにシオンの思いだった」ブナが言った。
「風が吹いたよね」昴が言った。
「確かに空気の流れが通って行きましたね」トゴが言った。
「解った、きっとそうだよね!心なんだ気持ちがコククウへと運ぶ翼になるんだよ」昴が言った。
「我々は大切な事を忘れていた、コククウは心が・・・ナトランが帰る場所だから気持ちが伴わないと赤い輪はコククウへ導かない」ブナが言った。
「でも、僕達死んでないからコククウ帰りたいって思う気持ちは本物じゃ無いよね」昴が言った。
「その為に回帰の祈りがあるのですよ」トゴが言った。
「昴、俺達が回帰の祈りを行っている間お前はシオンの思いを呼び寄せて欲しいバルク様の御印にひかれてシオンが来れば回帰の祈りが強く成るからな」ブナが言った。
「神経を集中させてシオンを思って下さい、きっと昴さんの御印がシオンには見えますよ」トゴが言った。
昴はシオンの美しい白い長毛の姿を心に描いた、そしてシオンを思った。
温かい思いが心に満たされると昴のナトランが暗闇の中で輝きを増した。
赤いチューブの中で大気が揺れて昴の頬を風が撫ぜる。
白と淡い青の混じったナトランの粒が風と共に現れてシオンの輪郭になる。
昴は涙をぬぐう事もなくシオンを思い続けた。
ブナとトゴはシオンと共に回帰の祈りを始めた。
頭を下げ、耳を伏せ、喉を鳴らして一心に祈った。
三匹の祈りが一体となってコククウに届くように。
|
21 怪鳥キラブル
突然に湧きあがったつむじ風は昴達を飲み込んで一瞬でチューブの奥へと連れ去った。
暗闇の中くるくると上も下も解らないまま飛ばされて落ちた先は足元に霧の立ちこめる場所だった。
気温は真冬のようにとても寒い。
天も地も色の無いぼんやりした世界の中で昴は打ちつけた肩をさすりながら立ちあがった。
二匹の猫達は近くには居ないようだった。
「ブナ、トゴ何処に居るの」昴は声に出して呼んでみたが返事は無かった。
足元に立ちこめる霧は猫達の背丈よりは高く、肉眼で見とおす事は出来ない。
昴は大振りに足を動かして霧を払いながら歩いた。
霧が左右に分かれて僅かに凍りついた白銀の地を見せる。
無彩色の霧の中を方向も解らないまま歩き続けて、昴は目まいを感じた。
目をしはだいても、天も地もすべてはっきりと見える物は何もない。
歩き続ける昴の前方の霧が一か所淡く緑色になっているのに気が付いた。
昴は、色の無い大地の中での緑色に引きつけられて歩みを速めた。
側まで近づくと霧の中で何かが光って回りを緑色に照らしているのが解った。
足を振って霧を払い白銀の地を見ると、そこには見慣れた髪飾りが落ちている。
キラブルが盗んで行った、ノアの髪飾りが何でこんな所に。
昴は髪飾りを手にとって確かめる。
緑石の付いた髪飾りは間違いなくノアの物だった。
この色が目印になればブナとマキにも見えるかも知れない。
昴は髪飾りを手に高く掲げて振りまわした。 |
しばらく髪飾りを振りまわしていると霧を分けてトゴが昴の足元に走り寄り、ほどなくしてブナも霧の中から姿を現した。
「やっと会えたね、迷子になったかと思ったよ」昴が言った。
「合図がなかったら、危ない所でしたね」トゴが言った。
「その緑の光は何だ」ブナが言った。
「ノアの髪飾りだよ、キラブルに盗まれたはずなのにここに落ちていたんだ」
「キラブルに盗まれた物が何でこんな所にどうして、それに何で髪飾りが光っているんでしょうね?」トゴが言った。 |
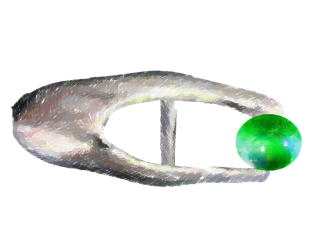 |
「たぶん髪飾りについている石はウランガラスだ、プニハ鉱山ではウランガラスの採掘がおこなわれていたらしいから、そのかけらを何処かで手に入れて作った髪飾りなんだろう」ブナが言った。
「ウランガラスってウランが入っているの?危なそうだね」昴が言った。
「普通のウランガラスは微量なウランが含まれているだけだから、まず何の影響も無いがここで採掘されるウランガラスは別物だ、もしかしたらノアが特別になったはその髪飾りの影響かも知れないな」ブナが言った。
「でもキラブルに盗まれたものが何でここにあるんだろう、巣の中まで探しに行ったのに」昴が言った。
「オレについて来なさい、その事にもしかしたら関係があるかもしれない」ブナはそう言って霧の中を歩き始めた。
昴とトゴはブナを見失わないようにすぐ後ろについて進む。
霧は益々深くなって注意をしていないと黒いブナの姿は霧の中に紛れそうになってしまう。
西も東も定かでない場所でその場所を探すのは困難かと思えたがブナの帰巣能力は確かだった。
前方に窪地に野球場ほどの大きさの霧の渦がゆっくりとした動きを見せている。
渦の中心に向かって進んでみるとだんだんと霧が薄くなり巨大な氷の柱が見えてきた。
渦の中心にあたる氷の大地には十二数本の氷の柱が正確な円形に配置されている。
氷の柱は人の手で造られたように真っすぐに削られた面と曲面が合わさった形が天に向かって伸びている。
それぞれの柱は形が少しづつ違うようだ。
昴は前にテレビのクイズで見た柱になった文字を横や斜めから見て書いてある言葉を当てるゲームを思い出した。
もしかしたらと思い柱の一本の周りを見て文字を頭に描いたが、ローマ字でもひらがなやカタカナ、思いつく限りの世界の文字で創造しても柱の形は当てはまりそうにない。
柱の中心の広場は大地が凍りついてスケートリンクのように白く見える。
「こっちに来て上を見てごらん」ブナが言った。
昴は広場の中心に立って柱の上部を見上げた。
柱の上部の氷の中に虹色の丸い卵型の物体が見える。
気がついて良く見るとどの柱にも一個ずつある虹色の物体が一本の柱にだけ見えない。
柱の真下まで来ると、砕けた虹色の石が散乱していた。
「原因はどうやらこれらしいな」ブナが言った。
「これはウランガラスで出来た玉なのでしょうか?」トゴが言った。
昴は石の破片をまじかで見て確信した。
「僕これ見た事がある」
「何処で見たんだ」
「ノアの髪飾りを探しにキラブルの巣に入った時に卵と一緒に置いてあったんだ」
「キラブルの卵は確か萌黄色でしたよね見間違える事はないと思いますが」
「萌黄色の卵も三個巣の中にあって大きさは虹色の卵の倍はあったから見間違いじゃないよ」昴が言った。
「キラブルがもしかして、いや」ブナが言った。
「何ですか?」トゴが耳をピクピクさせた。
「キラブルはウランガラスを食うと言う話を聞いた事があるのだ」
「キラブルが虹色の卵を産んだって事なの?」
「そうかも知れないし、何処からか持って来たのかも知れない」
「キラブルの巣にあった卵を氷の柱に入れたらコククウの入り口は開くのかな」
「他に試す方法は今のところ考えられないな」
「僕、キラブルの巣に行って卵を持って来るよ」
「一度ここを出て皆でキラブルの巣に行こう」
「シオンたちのナトランが帰るのに時間は間に合うでしょうか」トゴが不安そうな目をして言った。
「ともかく急ごう、虹色の卵は昴の力で持ちあがりそうか?」
「腕でやっと抱えられる大きさだったけど、一人で巣から降ろすの足場も悪いし難しいと思うよ、ノアにも手伝ってもらわないと無理だよ」
「そうか、キラブルとは俺達が戦うからその間に卵を運んでくれ」
「そうと決まったら、早くプニハ鉱山に戻りましょう」
「でも・・・どうやって戻るの?」昴は不安そうにブナを見た。
「ああ戻る時は簡単だ」ブナはそう言って喉を揺すってゲホッと茶色の木の実を吐きだした。
吐き出した木の実をブナに言われて昴が踏みつぶすと、鼻をつく強い匂いがあたりに立ちこめた。
昴は匂いを吸いこんで頭がくらくらし意識が遠くなった。
残されたわずかな意識の中、体が空間を飛ばされて行くのが解った。
カビ臭い土の匂いに気がつくと昴は赤い輪の外側の地面に倒れていた。
ブナもトゴも隣に座って昴が起き上がるのを待っている。
昴はハウラ虫のランプを手に取ると急ぎ足で外に向かって歩き出した。
鉱山の入り口まで戻ってみると太陽は真上に来ていた。
日の光と空の青さが生ある世界に戻ったことを強く感じさせる。
グレイとブーツがいち早く昴達の姿を見つけて走り寄って来た。
ノアに髪飾りを返して坑道の中の様子をおおざっぱに説明する。
髪飾りは、亡くなった父親がトマネ川の河口でを拾った石を使って髪飾りを作り母に贈ったそうだ。
その母親が亡くなって髪飾りは三歳の時からノアの髪を常に飾っていた。
ノアは嬉しそうに髪飾りを亜麻色の髪に戻した。
キラブルの巣はプニハ鉱山の北、歩いて二時間ほどの距離にある。
昴とノア、ブナ、トゴ、マキも加えて急いでキラブルの巣に向けて出発した。
キラブルの巣がある崖は見上げるほどに高くて昴は、一度登った事があっても登り始めると足が震えた。
巣を見上げると鳥の気配はなくキラブルは出かけているようだ。
猫達はとちょっとした岩のでっぱりを見つけて軽々と上へ上と飛び上がる。
キラブルの巣のある岩棚は相変わらず強い排泄物の酷い匂がした。
巣の裏側に回ると前に来た時に昴の抜け出た穴は修復されずに、開いていた。
岩を積み上げて巣の中に入る踏み台を作り全員が巣の中に潜り込んだ。
ブナの指示で、マキが巣の入り口に立ってキラブルの見張り役につく。
奥のシダの枯葉やキラブルの桃色の胸毛が敷れた柔らかなベッドを踏みながら卵の場所に進むと三個の萌黄色の卵は残骸となってキラブルの幼鳥は巣立っていた。
卵の殻が散乱した場所の近くに虹色の卵はただ一つ残されている。
ブナもトゴも氷柱の中の卵と目の前の虹色の卵が同じ物だと思った。
卵を割らずに崖から降ろす為に用意した蔦で編んだ袋を地面に敷き卵を転がして入れようと、昴とノアが力を合わせる。
卵はまるで地面に張り付いたように重くてびくともしない。
ブナもトゴも加わって卵を押しているとマキの甲高い鳴き声がした。
ブナとトゴは巣の入り口に向かって地面を強く蹴って猛ダシュする。
巣の前方はるか遠くに桃色の鳥が四羽大きく羽根を広げてこちらに近づいて来るのが見える。
「昴、急げキラブルが四羽も帰って来るぞ!」ブナが怒鳴った。
卵から孵ったキラブルの事を考えていなかったのは誤算だった。
三匹が力を合わせて思念を送れば一羽のキラブルなら何とか、食い止められると思っていた。それが四羽とは・・・・
昴とノアは渾身の力を込めて卵を押す。
キラブルは親鳥を先頭にして頭を下げ桃色の羽根をグライダーのように広げ気流に乗り巣へと近づいて来る。
ブナは親鳥に集中させて思念を送った。
「止まれ!止まれ!」親鳥は巣の方二十メートル先で風に阻まれたかのように突進を止めてその場でホバーリングしている。
自分の意志とは違う訳の解らない何かに苛立ってギャァーギャァーと鳴いている。
トゴとマキも力を合わせやっと巣立ったばかりの幼鳥三羽に向けて思念を送る。
三羽は思念に押されて数メートル後方に飛ばされ、それでも前に進もうともがいている。
体中の毛を逆立て思念を送っている三匹の足元の崖から二匹の仔猫が這い上がり巣の奥へと走り去った。
「グレイ!」マキの目のはしにグレイのシッポが見えて一瞬集中が途切れた。
一匹の幼鳥が思念から一瞬の隙をついて逃れ、猫達に向かって飛んで来る。
巣に上がるギリギリの所で幼鳥の動きを止めたものの猫達の力もそう長くは続かない。
幼鳥の怒り狂った水色の目が猫達を睨み、突こうとクチバシを伸ばして首を振る。
クチバシの大きさだけでも、猫の体よりは大きい鳥にひと突きされただけでも命はない。
「昴さんお手伝いに来ちゃいました」無邪気に目を輝かせてグレイとブーツは二人の元に走り寄った。
「危ないヤツだなぁ、でも言ってる場合じゃないや、卵を袋に入れるんだ一緒に押して」
「はぁい、やっぱ僕達の来て良かったなぁ」
「何バカな事言ってるの、後でブナに相当怒られるわよ」ノアは顔を真っ赤にして怒った。
声をかけ力を合わせて二人と二匹が力を合わせ虹色の卵を押すが卵はピクリとも動かない。
「もう駄目だ、持ちこたえられない、合図したら一揆に走って卵の所に行くぞ」ブナが言った。
ブナの合図でトゴもマキも思念を止めて卵に向かって走り出した。
後ろでキラブルの恐ろしい鳴き声と地面を突いたらしい地響きが聞こえた。
四羽のキラブルは巣に着地したらしく凄まじい羽音が風になって巣の奥まで吹いて来る。
「ブナはどうしたの?」昴の声に走り寄ったトゴとマキは顔を見合わせている。
勇敢な黒猫は四羽のキラブルを相手に時間を稼いでいるようだった。
「早く今のうちに力を合わせて」トゴとマキは自分の思念で力を増幅させながら卵を押した。
虹色の卵はグラリと揺れて卵の下に暗闇が見えた。
二人と四匹は全身で卵にしがみついて卵を網へと転がした。
卵のあった場所には卵の形に暗い闇が口を開いている。
ごろりと網の上に転がった卵は皆を乗せたまま一瞬で起きあがりこぼしのように立ち上がって暗い闇の中に吸い込まれて行った。
キラブルの攻撃をかわして戦っていたブナは巣の中が一瞬虹色に見えて卵のある方を見た。
卵は昴達を乗せたまま、下へ向かって落ちて行く所だった。
ブナは登って来た穴へうまく戻れたと思い自分も穴に向ってジャンプした。
暗い闇の口が閉じられようとした時、ブナの体は闇の中に消えて行った。
|
22 虹色の卵
卵にしがみついたまま、昴とノアと四匹の猫は暗闇の中をゆっくりと落ちて行く。
ちぎれた霧のかたまりが昴たちをかすめて後ろに飛ばされてゆく。
やがて眼下に霧に覆われた無彩色の世界が現れ、氷の柱に囲まれた円形の広場に卵はゆっくりと着地した。
「そこをどいてくれ!」ブナが叫びながら空から落ちて来る。
卵につかまっていないブナの落ちるスピードは早い。
マキとトゴが急いで思念を送ってブナのスピートを緩める。
ブナは空中で体を回して体制を整えて四本の足でトンと着地した。
ノアやマキ、グレイ、ブーツは氷の柱に囲まれた霧の世界に驚いてキョロキョロとあたりを見回している。
「まったく驚いたな、卵がコククウの入り口に落ちて来るとは」ブナが言った。
「ここが、コククウの入り口なの?」ノアが言った。
「入り口は閉じられているが、コククウの入り口に間違いはないだろう」
「僕達プニハ鉱山から入った時は大変だったのに、こんなに簡単に来られちゃうとはね」
「でも卵を運ぶのに苦労するところでしたから、助かりましたよね」
「あの卵、僕とノアの力じゃ絶対に持ちあがらなかったよ」
「それで、あの卵をどうするの?」ノアが言った。
「あの氷の柱を見てごらん、あの柱だけ卵が乗ってないだろう、落ちて壊れてしまったんだ」昴が氷の柱を指さし言った。
「それは解るけど、あんなに高い所までどうやって持ち上げるのよ」
「たぶん、それは卵自身が解決してくれるさ」ブナは澄ました顔で言った。
全員で力を合わせて転がしながら卵を運ぶ。
卵の落ちた柱に近づくにしがって虹色の卵の色が鮮やかになったように感じられた。
卵を柱の真下に据え置くとブナは卵から離れるように指示した。
全員の目が卵を見つめている。
虹色の卵はますます鮮やかな色になって斜めに入った縞の模様が流れるように変化している。
氷の柱が卵に近づいたのか、卵が氷の柱に近づいたのかは定かでない。
卵は柱に抱かれるように氷の中に入り柱の中で上部へとなめらかに移動して、あるべき位置に留まった。 |
他の十一本の柱にある卵が、戻って来た卵を迎えるように虹色に輝いた。
戻された卵も答えるように輝きを増した。
柱の上で卵達はクリスマスツリーの豆電球のように点滅を繰り返している。
不規則に繰り返される点滅はまるで会話のようだった。
昴たちは美しさにただ見とれていた。
やがて点滅が止まり卵から一筋の光が広場の中心に向って放たれた。
十二個の卵から放たれた光の線は円の中心でぶつかり合い虹色の光線が花火のように湧き上がる。
「コククウが開くぞ! 柱の外側に逃げろ!」ブナが叫んだ。
柱に囲まれた円形の広場の中心が溶けるようになくなって、深い闇の世界が姿を広げ出した。
二人と四匹はコククウに飲み込まれないように全力で柱の外に走った。
足の遅いマキが氷の地面を強く蹴って、柱の外に飛び込んだ瞬間に円形の広場はすべてコククウの入り口に変化していた。 |
 |
氷の大地にぽっかりと開いた別世界への入り口は深い闇の中に虹色のオーロラのような光が地に、いや天に向かってどこまでも遠くまで続いてゆらゆらと揺れている。
見つめているとコククウの中に取り込まれてしまいそうな気持になる。
皆は気が抜けたようにただ茫然とコククウを眺めていた。
どのぐらいの時間が過ぎたのだろう、気がつくと何処から来たのか蛍のような光がふわふわと氷の大地を覆った霧の中から現れコククウへと吸い込まれて行く。
「ナトランが集まり出したな」ブナが言った。
「コククウの入り口が開いたのをナトランが感じ取ったんだね、シオン達もここまで来れるかな」昴が言った。
「きっと大丈夫よ、シオンが導いてお爺ちゃんも皆もきっとコククウに入れるわ」ノアはうれしさでいっぱいだった。
ナトランは益々数を増やして、氷の大地を飛び回り虹色の光の帯に導かれるようにコククウの天をめざして登り見えなくなる。
真っ暗なコククウがナトランで星空のように見える。
昴の視界のはしに妙な方向に飛ぶナトランが映った。
小粒のナトランが数個、氷の柱の陰に吸い込まれて行く。
気になって目をやると鼠色の長い尾が柱の根元から少し見える。
グレイ?昴は数歩近づいて、驚いて足を止めた。
鼻先を氷の地につけてうずくまっているグレイの体にナトランが吸い込まれている。
ナトランを吸い込むたびにグレイの脇腹は妙な形に膨らんで、ぼこぼこと絶えず形を変えながら動いている。
グレイの閉じた目が一瞬見開いて体がビクッと痙攣した時、開いた口から煙のような物が立ちあがった。
薄紫色の煙は周りに浮遊しているナトランを吸い込んで、みるみる形を変えていく。
やがて薄紫の煙は人の形となりナトランを取り込む度に色を増している。
「紅花先生!」昴の声にブナが振り返った。
ブナは一瞬で背中の毛を膨らませ、シャァと鳴いた。
紅花は腕を伸ばして浮遊するナトランかき集めながら昴の方を見て微かに頬を緩めた。
「悪い猫に騙されてこんな所につれてこられたのね、可愛そうな子。私と一緒に戻りましょう」紅花は昴に手を差し伸べながら優しい声で言った。
元の場所へ戻れる、優衣の居るあの新宿の町へ昴の気持ちは大きく傾いた。
「昴騙されるんじゃないぞ、紅花はお前のナトランが欲しいだけだ」ブナが低い声でうなった。
猫達は紅花を囲んで耳を伏せ体の毛を膨らませて、飛びかかろうと身構えている。
「ブナ、なんて悪い猫なんでしょうお前こそ私を騙して見張っていたくせに」紅花はブナに鋭い視線を落とした。
「さあ帰るのよ、皆待っているわ」紅花は言いながら昴に近寄って来る。
帰りたい、でも目の前の紅花はとしても人とは思えないで恐ろしい。
昴はじりじりと後ずさりを続けた。
その時、霧の中から大量のナトランが帯になって飛んで来た。
白と淡い青の濃淡が美しい大きなナトランが先頭になってコククウを目指して飛んでいる。
「シオンだ、シオンが皆を連れて来ました」マキが目を輝かせて言った。
紅花は身をひるがえしてナトランの帯に向って突進した。
「まずい、シオン達が紅花に食われてしまう」トゴが後ろ足を強く蹴って紅花を追った。
紅花はナトランの帯からひと固まりを吸い込んでより鮮明に実在している体のように変化する。
タンポポ色の髪の毛が爆発したように広がり、異様に白い肌に濃い化粧が不気味に見える。
長いドレスの裾が氷の大地から少し浮き上がって、紅花は地に足をつけていなてようだ。
シオンのナトランは紅花の攻撃を避けようとコククウの上空で円を描いて留まっている。
今、無理にコククウに入ろうとすれば多くのナトランは紅花の餌食になってしまうだろう。
ブナが紅花に向ってジャンプし腰のあたりにキックして身をひるがえして着地した。
紅花の体は風船のようにふらりと揺れたものの、すぐに元の体制に戻った。
「このバカ猫がぁ!私をそんな事で倒せると思っているの悪い猫にはお仕置きだよ」紅花は紫色の長い爪をブナに向けて振りおろした。
ブナの黒い毛が白い大地に舞った。
ブナは体じゅうの毛をすべて立ち上がらせて四本の足をふんばり桃色の口を半開きにして低く唸った。
トゴが続いてジャンプし、紅花のドレスを引っ掻いたものの大した攻撃にはならない。
ブナとトゴ、マキが息を合わせて紅花に飛びかかったが紅花はするりと逃げて三匹は地面に叩き付けられた。
紅花は猫達が怯んだ隙に上空に舞い上がって、ナトランの帯に手を伸ばしている。
シオンは仲間のナトランが捕まらないように方向を不規則に変えて皆を誘導しているが、入って来るナトランの数は増える一方でコククウの入り口は大渋滞になってしまった。
ナトランの帯の最後の方に続いている、ひときわ大きい薄緑色のナトランは人のものなのだろう。
三つの薄緑のナトランは先頭の動きに遅れないように後を追うが蛇のように長いナトランの帯は機敏には動けない。
マキがよろよろと起きがって言った。
「物理的な攻撃をしても無駄かもしれません紅花の実態はここには無いみたいです」
「あれをやってみよう」ブナが目で合図した。
ブナ、トゴ、マキの三匹は後ろ足で立ち上がって前足で何かをかき集めるような動作をした。
前足の先に透明な球が出来てそこだけ景色が歪んで見える。
「フギャァーーーオン!」ブナが鳴いた瞬間に透明な球はブナの手を離れ猛スピードで紅花に向う。
猫球をまともに受けた紅花の腹の部分がえぐれて凹んだ。
紅花は怒りに燃えた目でブナを睨んだ。
「ムギャァーオン!」続いてトゴが猫玉を飛ばした。
トゴの猫玉は紅花のドレスをちぎって闇の中に消えて行った。
紅花も負けずに長い爪で空を切って薄紫の風を飛ばして来る。
するどい刃のような突風は猫の体をかすめるたびに毛がちぎれて舞う。
風はブナの耳をかすめ、血吹雪が白い地面を染めた。
紅花の攻撃をまともに受けたらブナも無事ではいられないだろう。
三匹は踊るように前足で猫玉を作って紅花に向けて放つ。
紅花の右の膝から下のドレスは吹き飛ばされて無くなった。
タンポポ色の髪を振り乱して紅花は猫達に急接近してマキに向って爪を振りかざした。
「ギャー!」と悲痛な声がしてマキのひたいから耳にかけて出来た傷口から大量の血が噴き出した。
マキは血が目に入って前が見えない。
紅花は攻撃をゆるめずマキに向って爪を振りおろす。
オレンジの毛が宙に舞って、マキの背中が血で染まる。
マキを攻撃している紅花にブナとトゴがいっせいに猫玉を投げつける。
猫球が紅花の顔に命中して紅花がだじろいだ。
恐ろしい顔が猫玉で左側だけ歪んで不気味さを増した。
昴は紅花がひるんだ隙に飛び出して、マキを抱えて氷の柱の陰に逃げ込んだ。
「痛むよね気をしっかり持って、大丈夫だから」昴はマキを胸に抱いて紅花の攻撃が届かないよう柱の陰に身を隠した。
オレンジ色の毛は血でぐっしょりと染まりマキは目を閉じている。
温かな体温と確かな胸の鼓動が昴の手に伝わって、マキの命はまだ燃えている。
マキ頑張って、強く思う昴の体からナトランがにじみ出てマキを包む。
隣に居たノアが恐怖の声で叫ぶ。
視線の先では、紅花とブナ、トゴの戦いが続いていて紅花は猫球が当たった体のあちこちが歪んで腕が片方だけ妙に長い。
人とはかけ離れた怪物になった紅花が追うのは目の前に浮遊する三個の薄緑色のナトランだった。
ナトランの帯は巧みに円を描いて紅花から逃れようとするが、帯の末端に居る三個の人のナトランは動きが遅くその上、大きくて紅花の標的となってしまった。
ノアは柱の陰から飛出して、紅花を追ってコククウ縁を走る。
「危ない、ノアやめるんだ」昴が叫んだ。
「お爺ちゃんが、お爺ちゃんが」昴の頭の中にノアの泣き声が聞こえる。
紅花の手が薄緑色のナトランを伸ばした瞬間に、ノアは勢いよく氷の大地を蹴って飛びコククウの縁に浮かぶ紅花にしがみ付いた。
ノアに抱きつかれた紅花はバランスを崩して、コククウの闇に倒れそうになって手をバダバタと動かしている。
「ノア手を放すんだ」ブナが叫んだ。
昴は恐怖で金縛りのように体が動かない。
紅花は力まかせにノアを振りほどきコククウの闇ら投げ飛ばして体制を戻して縁に体を戻した。
ノアは落ちる瞬間、昴を見て笑ったように思えた。
全てがスローモーションのように見えた。
ノアはコククウの闇の中に、落ちるとも登るとも解らない黒い世界に吸い込まれて遠く、遠く見えなくなってしまった。
「ノア、ノア」昴の声が音の無い響く。
昴は憤りで体が震え怒りでいっぱいになって、恐怖も忘れて紅花の前に踊り出た。
普通でも多い緑色のナトランが火炎ように昴から立ち上がりゆらめいている。
「危ない、昴だめだ!」ギャオンと鳴き声とともにブナが叫んだ。
紅花は昴を見つめて赤い唇を歪めてニャッと笑って、昴に向って突っ込んで来た。
涙を袖で拭って昴はコククウの縁から離れ氷の大地を走る。
霧を裂いて追いかける紅花の背中にブナ達の猫玉が飛ぶ。
逃げる昴の背中に氷のような冷たい感触がしてぞっとして立ち止まった、足が動かない。
「昴、久しぶりねぇ」紅花の声が耳元で聞こえる。
白い腕が昴の首に絡みつきたんぽぽ色の髪の毛が昴の胸元で揺れている。
「さぁ、心を開いて私と一緒に帰るのよ」紅花は甘い声でささやく。
ここちよい眠りに引き込まれるように、昴は意識を失ってゆく。
さっきまでの怒りが溶けるように消えて心が安らいで行く。
このまま眠って元の世界に戻れば優衣に会えるのかも知れない、優衣、逢いたい。
夢の中の世界に眩しい光が現れてだんだんと近づいて来る。
光の中心には白い猫が居て昴に向って走って来る。
力強く引き締まった筋肉で、真っすぐに走る雄々しい姿。
美しい長い白い毛、輝く緑色の瞳、昴にはその猫がバルクだと解った。
「ギャァー!!」叫びながら紅花が昴から飛びのいた。
昴は一瞬で意識が戻り見ると紅花は氷の大地に倒れてのたうち回っている。
体からシュルシュルと薄紫の気体が抜けて紅花は萎み続け、老婆になり身をよじり昴に救いを求めるように手を伸ばす。
老婆はどんどんとミイラように委縮して益々小さくなり最後は何もない氷の大地だけが残った。
「ブナどうしょう僕、紅花先生を殺しちゃった」
「紅花は死んだ訳じゃない、元々実際の体はここには来て無いのさ、それより昴お前の体は大丈夫か?」ブナが優しい声で言った。
|
23 帰るべき場所
昴の体に不思議な余韻が残った。
体の内側の深いところに熱い物があってそれがジンジンと血流に乗って体を巡っているような、落ち着かない感じ。
しかしそれもすぐに収まり昴は紅花の消えた大地を見つめていた。
目の前を白と淡い青の濃淡が美しいシオンのナトランが別れの挨拶のように近づいて飛ぶ。
「ああシオン、コククウに行っちうんだね」昴がつぶやいた。
ブナとトゴも傷ついたマキも何とか立ち上がってシオンとの別れを惜しんでいる。
コククウの入り口は銀河のような無数のナトランで覆い尽くされている。
ブナが鼻を揺すって髭をピクピクと震わせてから低い優しい声で歌うように鳴き始めた。
トゴもマキも目を覚ましたグレイもブーツもナトランの銀河を見つめ声を合わせた。
先頭のシオンは皆を引き連れて大きく円を描いて飛んでから、虹色の帯に絡みつくようにらせん状に沿って登りコククウの奥へ奥へと飛んで行った。
ナトランの大行列は龍のようにうねりながらコククウの闇を分けて進み最後に人の三つのナトランがひと時、昴の目の前で止まった。
「お爺さんお別れですねノアが先に行きました、よろしくお願いします」昴は薄緑のナトランに話かけた。
ブナは目をしばたいて、合図を送った。
薄緑のナトランが虹色の帯を登って見えなくなると猫達は鳴くの止めて緊張を緩めごろごろと喉を鳴らして胸の毛を舐めた。
昴は一人ノアを飲み込んだコククウを見つめている。
「さあ、戻ろう誰か木の実を吐きだしてくれ」ブナが言った。
トゴがカッカッと苦しそうな声を出して喉を揺すって茶色の木の実を吐き出した。
昴が前と同じように木の実を踏みつぶすと鼻をつく強い匂いがあたりに立ちこめ意識が遠のいた。
わずかな意識の中、体は空間を飛ばされ湿り気のあるカビ臭い暗い場所へと運ばれて行った。
昴は暗闇の中で目を覚ました。
一緒に戻ったはずの猫達の気配はない。
水を含んだ土と岩の壁の手触りは前と同じプニハ鉱山の坑道だと思うがハウラ虫のランプが無くては何一つ見えない。
昴は声に出して、思念を送って猫達に呼びかけたが何の返事もなかった。
昴は僅かな空気の流れをたよりに壁に手を這わせて、暗闇の中を進む。
戻った場所が赤い輪の近くなら、もととうに入り口の光が見えるはずだ。
入り口からぬかるみの坑道に入ってしばらく歩いて坂を上ると乾いた岩の
道が続く。
入り口から赤い輪までは一時間もかからないはずなのに、昴は何時間も坑道の暗闇を歩き続けていた。
喉は渇きと空腹と疲労で暗闇の中に座りこんで昴は目を閉じた。
何処までも続く何も見えない闇はおそろしかった。
自分はこのまま、誰にも発見されずここで死んでしまうのか。
死がすべての終わりではないと知っても、死ぬ事は怖い。
自分の体からナトランの核が抜け出てコククウの中に吸い込まれて行く。
コククウの闇の先には何があるのだろう。
ノアはコククウの先でどうなったのだろう。
猫達が前世の記憶を持って生まれるならコククウに入ったナトランはまた新たな命として地上に帰るはずだ。
生きている今の自分をゲームのようにリセット出来るのが死ならそれもまた有りかなと昴は少し思った。
目を閉じるとノアの笑顔が浮かんだ。
フレハラスでの暮らしはいつまで続くのだろう。
ノアの居ないフレハラスは色あせた場所のような気がした。
心の大事な場所に穴が開いてしまったような虚しさが昴を無気力にした。
何もかも忘れて戻れるなら、もう一度始めから何も知らない自分に戻って家に帰って学校に戻りたい。
もしもフレハラスから脱出できるなら、どんなに叱られても両親に謝って家に戻ろう。
扱い易い良い子として騙されても利用されても、それでも自分の身を置ける場所に戻りたいと昴は心から思っていた。
家族に囲まれて学校に通い平凡で普通の暮らしを取り戻したかった。
昴は暗闇の中で岩の壁にもたれてひと時眠り余りの空腹で目を覚ました。
目を開くと暗闇の中に僅かに坑道の中が見た。
光源の正体を探すと昴の二の腕の内側に残ったバルクの足跡が虹色に輝いているのに気が付いた。
足跡が光るのは坑道の岩石からブラックライトのような光線が出ているのかもしれない。
昴は注意深く左手を動かして確かめた。 |
立った位置では輝きは消え、座った高さの所に手を置いた時だけ足跡が虹色に輝く、低い位置の地層に反応するらしい。
昴は地面に膝をついて左手の明かりをかざして坑道を見渡した。
坑道の地面に同じ足跡が前にも後ろにも続いている。
昴は足跡をたどれば出口に出ると喜んだが、それが間違いだとすぐに気が付いた。
前と後ろに続く足跡は紛れもなく自分のスニーカーの足跡だった。
昴は暗闇の中を同じ場所を何時間も回り続けていた。
昴は右手を壁に這わせて坑道の中を歩いて来た。 |
 |
急なカーブで曲がった記憶もなく壁づたいに一回りしたと言う事は、ここは大きな岩石の部屋なのか、出口は何処にあるのだろう。
昴は岩の壁に目立つように傷を付けて、スタートの位置をしるした。
そして、左手の印が放つわずかな明かりをたよりに空気の流れに神経を集中させて風の吹く方向に膝をついてはいながら進んだ。
坑道の部屋はとても広いようで一時間ほど進んでもスタートの印には戻らない。
膝ではいながら進むのはとても疲れ前に進むのを諦めかけた時、少し先闇の中に何かがちらっと光った。
昴は急いで光る物の場所に歩みよるとそれは見慣れた牛の鼻輪のような形をしたドアの取っ手だった。
ドアは古びた木製で大きめのバスタオルほどのサイズ。
地震で埋もれてしまったブナの家のドアがそのまま付いているように節穴の模様までそっくりだった。
昴はためらわずにドアノブに力を入れてドアを開いた。
ドアは重く、きしんでしまっているらしくなかなか開かない。
昴は立ち上がって両手でドアノブをしっかり掴み足を壁にかけてドアを引いた。
土埃が舞ってドアが鈍い音とともに開く。
昴は左手を差し出してその明かりで扉の外を見る。
右手でドアの中に手を入れて確かめる。
ドアは騙し扉のように岩石の壁に付いていて、開いた扉の外も岩の壁があるだけだった。
昴は膝が折れてその場にしゃがみ込んでしまった。
一滴落ちた涙が堪え切れなくなり、昴は暗闇の中で声を上げて泣いた。
感情が抑えきれなくなって、手に触る石の破片を暗闇の中に向って投げつけた。
石が岩の壁に当たってカラン、カランと虚しい音をてたる。
昴は気の抜けたように扉にもたれて座り込んだ。
背中でかんぬきが外れたような微かな音がして、扉が外側に開き昴の体はバランスを失って扉の外へところがり尻もちをついた。
さっきまで、岩の壁だったはずの場所が外側に開いて違う闇が姿を現した。
昴はフレハラスに来た時の事を思い出した。
納戸の天井裏を這いまわって辿りついた先にあった、古い木の扉を開いたらフレハラスのブナの家だった。
もしかしたら、この闇の先は紅花の家の納戸に続いているかもしれない。
昴は違う闇の中に体を滑り入れて手の感触で慎重に回りを確かめた。
頭上までの高さは一メートルほど、床も天井もまっ平らで人工的な建物の中に間違いがなかった。
困った事に、ここでは左手は光を放す事はなく真っ暗だった。
昴は考えた、ブナはどうして迷わずに暗闇の中を進めたのだろう。
昴は高鳴る気持ちを静めて頭をからっぽにして自然に身をゆだねた。
体の向く方へ五感のおもむくままに闇の中を四つん這いになってゆっくりと進んだ。
昴はこの先、何処に辿りつこうと今は何も望まなかった。
人工的な建造物の先はきっと何処かに出口があるばずだ。
ともかく光のある所に行きたい。
しばらく進むにつれて、フレハラスの蒸し暑さが薄れ気温が下がったのを感じた。
排水管らしいパイプに頭をふっけた時は嬉しさで飛び上がりそうだった。
つるつるした手触りの管に耳を当てると水の流れる音がする。
人の生活の匂いがする。
天井のつなぎ目や釘穴から僅かに光が見える。
薄明かりの中、埃を分けて摺ったような後と猫の肉球の足跡が前に続いている。
紅花に追われ進んだ天井裏に戻った喜びで胸が躍った。
昴は慎重に足跡を追って点検口の入り口に辿りついた。
内側から開くように細工してある紐を恐る恐る開いた。
わずかな隙間は次第に開いて、見慣れた納戸が見える。
倒れたスチールの棚や潰れたダンボール箱、床に新聞紙が散乱した部屋を型ガラスから差し込んだ西日が照らしている。
昴は点検口の渕につかまって体を振子のように振って、ダンボール箱の上に飛び降りた。
納戸の床に足を降ろして見ると、嵐の夜に逃げ出してからこの部屋はそのまま放っておかれたままのようだった。
水を吸ったダンボール箱は黒いカビが生えて歪んで乾いて固まっている。
床に散乱した新聞紙も水で濡れたようで波打って黄色に変色している。
昴はすぐに逃げられるようにロックを外して窓を開いた。
冷たい空気が入って来て一瞬で鳥肌が立った。
三階のビルの隙間から街路灯に付けられたクリスマスの飾りが見える。
嵐の夜に逃げ出してから季節も夏から冬に移ってしまったのか。
時間に追われる事もなく過ごしたフレハラスでの日々。
昴はそんなに永い時が過ぎてしまったとは思っていなかった。
ともかく今の状況を掴まなくては。
昴は納戸の扉を少し開いて占い部屋をのぞく、人の気配は感じられない。
薄暗い部屋に足踏み入れ照明のスイッチを入れると華やかな光が部屋を照らした。
天井から幾重にも折り重なったド淡い色のシフォンのドレープが柔らかなアーチを作って見えるが部屋の中は泥棒が入ったような様子だった。
紅花が座る奇妙な動物の木彫付いた革張りの椅子は横倒しになり、壁際にある螺鈿のチェストの上に置いてあった花瓶が床に転がって朽ち果てた大量の百合の花から悪臭が漂っている。
占い用の六角形のテーブルの上には紅花が占いで使うクリスタルが床まで散らばってシャンデリアの光にキラキラと光っている。
この部屋で紅花に何があったのだろう。
まるで、ここで乱闘でもあったみたいだ。
コククウで見た化け物のような紅花とこの部屋で暮らした紅花は同じ人なのだろうか。
マキはコククウには紅花の実体は無いと言っていた。
もしかしたら、ここで紅花は死んでしまったのでは。
死体は、紅花の部屋にあるかもしれない。
昴は恐怖と好奇心に板挟みにながら好奇心に負けて紅花の部屋のドアを開いた。
嫌な匂いは漂っていたない、紅花の部屋は以前と何も変わらず綺麗にベッドメイクされて整然としていた。
昴はほっとして、台所に行って冷蔵庫を開いた。
冷蔵庫はあきれるほど空っぽだった。
昴はやっと棚の中にあったカップ麺を二個探し出して湯を沸かしそれを持って納戸に戻った。
久しぶりの慣れた味で腹が満たされると睡魔が押し寄せて新聞紙の中に埋もれて眠ってしまった。
|
24 帰郷
昴は電話の音で目を覚ました。
起き上がってみると呼び出し音はすでに途切れて部屋の中は薄暗くなっていた。
くずれかけたダンボール箱の奥の窓で白い影が動いている。
猫だ猫が来ている。
昴は急いで建付けの悪いサッシを開いた。
白い猫は機敏に身をひるがえしてアルミのベランダから隣の軒に飛び移った。
「待って行かないで、ブナの友達でしょ」昴は慌てて言った。
白い猫は驚いた顔で昴を見つめて身構えた。
昴は落ち着くために深く呼吸をしてから声に出さず思念を送った。
「お願いがあるんだ、ブナとはぐれてしまって困っているんだブナに僕がここに居る事を伝えて欲しい」昴は白い猫にゆっくり語りかけた。
白い猫は耳をねじって昴の方に向けて少し口を開いて声を出さないで鳴いたように思えたが、思念で言葉を返す事もなく隣の軒から階下へと去ってしまった。
昴は気落ちして寒さに負けて窓を閉めた。
これからどうしょう。
着ているシャツはフレハラスに居る間中繰り返し洗ってヨレヨレでその上に闇の中を這いまわったお陰で汚れている、これじゃあとても外には出られない。
昴は散乱したダンボールをひっくり返して、衣類が入っていたはずの袋を探した。
自分が家を出た時に着ていたタイリーのプリントのシャツとジーンズを探すとシャワーを浴びて着替えた。
紅花の部屋に入ってエアコンの暖房を入れたが寒くて仕方がない。
ベッドカバーを剥がして体に巻き付けてテレビのスッチ入れた。
夕方のニュースで見慣れたキャスターが喋っている。
時間は六時二十分、日にちはいったい何日なん日だろう。
昴は思いついてリモコンの番組表のボタンを押した。
十二月六日、もう三カ月も過ぎていたのか。
ともかく早くここを出なくては。
優衣さんに会いたい。
最近は夢さえも出て来ない優衣の姿を頭の中に追い求めてみたが、優衣の姿を思い描こうとするとイメージが優衣からノアに変わってしまう。
優衣を好きだった思いは胸の中にあるのに、吸い寄せられるような気持ちがどこか引いてしまった。
ドレッサーの上にある紅花が小銭を投げ込んでいたアルミ缶の貯金箱を開いた。
七千二百円、安いジャンバーを買っても家まで帰る交通費はなんとか足りる。
家を出た時と同じ半そでのシャツでBlue heavenを出て寒さを紛らすため走って古着屋をめざす。
通りに出た昴は歩道を歩く人の姿を見て驚いた。
ニットキャップをかぶった若い男も急ぎ足で通り過ぎる中年の女性も体が淡い色の光で包まれている。
街に見える人それぞれが皆違う色の淡い光をまとって動いている。
皆どうしちゃったんだろう?
僕のせいだ、ナトランが見えるようになってしまったのは自分の目が変わったせいだ。
昴は自分の手から立ち上る濃い緑色のナトランを見つめてビルの壁に背をもたれて目を閉じた。
ブナ僕はどうしたらいいの、僕の体は変になっちゃったみたいだ。
昴はタイル張りの壁に寄りかかり寒さも忘れてしばらく行き交う人を眺めていた。
元気そうな澄んだ青のナトラン、幸せそうな桃色のナトラン、寂しそうなブルグレー、怒りを感じる赤褐色。
何色ものグラデーションのナトランが人々を包む。
見える物は仕方がない、ともかく今は前に進まないと。
昴は自分に言い聞かせて古着屋まで走りジャンバーを買った。
人の賑わう交差点を左折して優衣の居るフェアリーローズまで急いだ。
フェアリーローズのガラスの扉を開きポインセチアや蘭が飾られた店内に足を入れる。
黒いエプロンを付けた見知らぬショートカットの若い女が昴を見て作り笑いをしていらっしゃいませと言った。
「あの、優衣さんは」
若い女は笑顔が固まったように表情が止まって不思議そうな顔で昴を見ている。
「優衣さんは、今日はお休みなんですか?」昴はもう一度言った。
「優衣さんて、誰ですか?」女は言った。
「ここに勤めている並木優衣ですけど」
「並木優衣さんですかぁ聞いた事ないですね、お店を間違ってませんか」女は言った。
「そんなはず無いですよ、僕はここで何回も優衣さんに合っているし、もしかして最近辞めてしまったのかな」
その時ドアが開いてフェアリーローズの店長が戻って来た。
「やあ昴君久しぶりだね」髭面の花屋らしくない店長が言った。
「ああ良かった、しばらくぶりですね」昴はほっとして言った。
「紅花先生は旅行だそうだけど、まだ帰らないの」店長は言った。
「あの僕、ちょっと実家に帰っていたので詳しく解らなくて」
「そうしばらく注文が無いからどうしたのかと思ってね」
「あの、優衣さんは辞めてしまったんですか?」
「優衣さん、誰の事?」店長は言った。
「ここに九月まで勤めていた並木優衣さんですけど」
「えっ?並木優衣さんだって、そんな店員居ないよ昴君何か勘違いしてない」店長は戸惑った顔で言った。
昴は青ざめた顔でフェアリーローズを出た。
いったいどう言う事なんだろう。
優衣さんが居なくなってしまった。
フェアリーローズに勤めて居なかったって、どう言う事なんだろう。
昴は優衣に逢ってからすぐに実家に帰ろうと思っていたが、余りにも気がかりな事を残して帰る訳にもいかずマリアのマンションに向った。
オカマパブに出勤前の濃いメイクをしたマリアは昴の訪問を快く迎えてくれた。
マリアのナトランは白とオレンジ、ブルーが混ざりあったとても優しい色をしている。
マリアの話だと紅花は占いの勉強でしばらく海外に行くとメールを送ってから姿を見て居ないと言う。
以前にもそんな事があったらしく、マリアはいつもの紅花の気まぐれと思っているらしい。
出勤までの僅かな時間の最後に昴は思い切って優衣の事を聞いてみた。
「あの、フェアリーローズの優衣さんがお店を辞めちゃったみたいなんですが行き先を知りませんか?」
「優衣さんて、フェアリーローズにそんな子いたかしら?あそこは店長と直樹君と良美さんと確か若い女の子は由紀江ちゃんて言ったと思うけど」
「由紀江さんって髪の毛の短い人ですよね」昴は言った。
「そうよ、何だか色気の無い子じゃない」マリアが赤い唇で言った。
昴はそれ以上聞くことができずに下を向いた。
「あんたこれからどうするの?」マリアが言った。
「僕、実家に帰ろうと思ってます」
「そうね、紅花が戻らないんじゃぁ仕方が無いわね」
「マリアさん今までありがとうございました」昴はペコリと頭を下げてドアを閉めかけた。
「もしも、もしもよ、どうにも困った事があったら戻っておいで」マリアは昴の背中に野太い声で優しく言った。
新宿から二時間余り電車に揺られ昴はなつかしい駅に降りた。
こんなに近い場所なのに戻るまでなんと遠かった事だろう。
何と言って両親に謝ろうかと思いながら通いなれた道を家に向い急ぐ。
国道を渡って家の明かりが点々と灯る小山のような丘を登る。
急な階段に息をはずませながら赤い屋根のなつかしい家に向う。
何を言われても耐えて謝ろうと昴は思っていた。
利用されてもいい、自分がちゃんと落ち着ける場所が欲しい。
成川と言う家族の中に居て、学校と言う枠に所属して毎日を平穏に送りたい。
自分を囲む枠から逃げ出してみると囲む物の無い暮らしは不安で地に足の付かない暮らしだった。
フレハラスと言う現実とは思えない場所で暮らしてみて、平凡で穏やかな暮らしが懐かしく戻りたいと思っていた。
街頭から離れた場所に成川の家の黒いシルエットが見える。
門燈も消えて寝静まっているようにひっそりとしている。
まだ八時前なのにもう寝ちゃたのかなぁ。
昴は不思議に思い玄関のチャイムを鳴らそうとした時、壁に貼られたプラスチックのボードに気が着いた。
「売家」売家って。
不動産会社の名前の入ったプレートを見ても昴は状況が飲み込めなくて茫然とした。
お父さん、お母さん辰哉、奈津美みんな何処へ行ってしまったんだろう。
やっと決心して家に戻ったのに戻る家が無いなんて。
昴は玄関の前でしゃがみ込んで、手で顔を覆った。
これからどうしょう。
父や母、弟妹の顔が思い出されて涙がこぼれ落ちる。
いつまでも動かない昴から北風が体温を奪って手足の感覚がなくなって行く。
みんな僕を残して行ってしまう、もういいや、何もかも何もかも、うんざりだ。
昴は玄関のコンクリートの上に座り込んで目を閉じた。
ここで一晩過ごしたら凍死できるかな。
頭にふとそんな考えがよぎった。
このまま寝てしまおうと、横になる。
自分の胸の鼓動と聞き慣れた街のざわめきを聞きながら眠りに引き込まれる。
しばらくすると脇腹と首筋のあたりが湯たんぽでも入れたように温かい。
目を開けると首に茶色い縞模様の毛皮が張り付いている。
脇には白黒の毛皮がゆっくりと上下に動いている。
二匹の猫は昴に寄り添って寝息をてたてていた。
「俺たちはいつもお側におります」茶色い猫から声が聞こえる。
昴が驚いて体を起こすと二匹の猫は素早く立ち上がり一瞬昴を見て塀を飛び越えて一目散に走り去った。
昴は猫を追って階段を下り隣りの家の庭をのぞいた。
枯れた芝生の上にパンジーのプランターが置かれた庭には猫の姿は無い。
「誰かと思ったら昴ちゃんじゃないの」ベランダのサッシが開いて聞き慣れた声がした。
「あっ、おばちゃんこんばんわ」昴はあわてて挨拶を返した。
「あんた、どうしたの今何処に住んでいるの」初老の小太りの女は上り口のサンダルをつっかけて庭に出て来た。
「あの、僕・・・おばちゃん、お父さん達は何処に引っ越したかご存じですか?」
「それを聞いているのよ、それじゃぁ、あんた成川さんと一緒じゃなかったの?」
「僕その、事情があって東京の友人のところに居たんです」
「どういう事なの、それじゃぁもしかして成川さんが夜逃げした事知らないの」今井のおばちゃんは目を瞬いて言った。
「夜逃げですか?」
「そうよ十月の末だったかしら突然知らない男が訪ねて来てね、上の成川さんが何処へ行ったか知らないかって、どうも借金踏み倒して逃げたみたいだよ、ぜんぜん引っ越ししたのも気がつかなかったもの驚いたわ」
「そうですか」
「昴ちゃんこれからどうするの、お父さん達の行方が分からないと困るでしょ」
「おばちゃんありがとうございます」昴はぺこりと頭を下げて庭を出ようと後ずさりした。
「あんたまた我慢してるんでしょ、まったく小さい頃から我慢ばっかりする癖がついて、親が息子に居場所も知らせないで雲隠れするなんて許せないね、もっと怒っていいのよ我慢しないで泣きたいなら泣きなさい」
昴はこぼれ落ちそうになる涙を必死で耐えて皺だらけの優しい顔を見た。
「今夜泊る所が無いんだったら、家に泊って行きなさい小さい時から知ってるのにほっとけないよ」
今井のおばちゃんに言われ昴はその夜、自宅の隣家で眠る事になった。
昴はここから数メートルの場所で幼い時からずっと平凡に穏やかな日々を過ごして来た。
その日々にもう戻れないのだと思うと胸が押しつぶされそうだった。
次の日、今井のおばちゃんのアドバイスで昴は市役所に行って成川の住民票とつでに戸籍謄本もとった。
住民票を移していれば両親の居所が分る。
昴は市役所で渡された謄本も住民票もその場で見る勇気がなかった。
市役所から道路を渡った公園に行きベンチに座った。
冬の柔らかな日差しが降りそそぎ噴水の前の石畳みにハトが群れて落ちたパン屑をつついている。
乳母車を押した長い髪の人がパンをちぎってハトを寄せている。
幼稚園児ぐらいの子供がハトを追って笑い声をあげている。
昴は覚悟を決めて、封筒から書類を出す。
住居届は前の住所のまま変更はなくて、父や母の行方は分からない。
落胆しつつ戸籍謄本の用紙を、息を止めて開く。
成川昴 長男、父 成川辰男 成川早苗。
戸籍には養子と記載されて居ると覚悟して見た昴は拍子抜けをした。
父と母の話を聞き違えたはずは無い。
今井のおばさんも、養子だと知っているような口ぶりだった。
養子と記載されていれば本当の両親の名前や居所を掴めたかも知れないと思うと残念なような、¬反面ほっとしたような複雑な思いだった。
住民票も戸籍謄本を丁寧に折って鞄に入れる。
これからどうしょう。
昴は温かな午後の陽に包まれ心は不安の中を彷徨っていた。
家の雑用をする為に学校が終わると忙しく帰宅していた昴は親友と呼べる友も居ない。
「もしも、もしもよ、どうにも困った事があったら戻っておいで」
マリアの言葉を思い出した。
石畳みの広場を、首を前後に動かしながら逃げるハトを追って子供が笑い声をあげて昴の前を過ぎる。
自分もあんな小さな頃に戻る事が出来たら、昴がぼんやりと見ていると、少女は前のめりにバタンと転んだ。
驚いた十数羽のハトが空に舞う。
昴は立ち上がって少女を抱き起こす。
少女は小さな腕を伸ばして一瞬昴に抱きついて微笑んで昴を見つめながら「I know」と言って一目散に昴から身引いて母親の元に走り去った。
ノア?そんな馬鹿な。
亜麻色の長い髪の幼い少女はどこかノアに似た顔立ちをしいる。
でも似ているのは外見じゃない。
昴の体の全部が目の前の少女をノアだと感じている。
昴は走り去る少女の後ろ姿をただ見つめていた。
END

|
 あび猫本舗
あび猫本舗 あび猫本舗
あび猫本舗